ネガティブ思考から抜け出すヒント|アドラー心理学で学ぶ前向きな考え方

一時期、アドラー心理学に基づいた「嫌われる勇気」という本がとても流行ったのを、覚えているママも多いのではないでしょうか。
子どもたちにもすべての子に好かれなくてもいいと伝えたくても、どのように伝えたらいいのかわからないこともあるかと思います。
そこで今回は、ネガティブ思考をポジティブに変えていくためにアドラー心理学の活用法についてお話していきます。
Contents
アドラー心理学の基本的な考えってどんなもの?
アドラー心理学には5大前提と呼ばれる基本的な考えがあります。
- 自己決定性
- 目的論
- 全体論
- 対人関係論
- 認知論
①自己決定性
自己決定性とは、自分の人生は自分で決定するという考え方のことをいいます。
人は、悪いことがあるとどうしても環境のせいや誰かのせいにしたくなりがちです。
しかし、アドラー心理学の考え方では自分がいる環境の中でどのように対応するかは、自分自身の決定によるもので、自分の行動によって今の結果につながっていると考えます。
中には、ハンデだと思えるような環境や状況もあるかもしれません。
それでもそれらの要因は、影響を与えるだけで結果を決定するものではないということが前提になります。
自分の今の環境は、自分の行動によってつながった結果!

②目的論
目的論とは、人は過去の原因によって行動するのではなく、未来の目標に引っ張られるように行動するという考え方のことをいいます。
アドラーは人の行動には無自覚でも目標があり、その目標を自覚して目標に向かって行動すれば、困難を乗り越えられると考えました。
原因ばかりを考えず、問題を解決するために未来に目を向けることが大切!

③全体論
全体論とは、理性と感情、心と体はすべてつながった1つのもので矛盾しないという考え方のことをいいます。
たとえば、ゲームをやめたいけどやめられない状態は心と行動が矛盾しているわけではなく、単純にゲームをやめたくないから続けているという風に考えます。
「頭ではわかっているけどできなかった」
という言い訳は、アドラー心理学の考えでいくとやらないことを自分で選択した結果ということになります。

ただ、子どもに対してこの考えを押し付けすぎてしまうと逃げ場がなくなりやすくなるため、ある程度成長してからこういった考えがあるという一つの選択肢として伝えていただくのがいいと思います。
④対人関係論
対人関係論とは、人のあらゆる行動に相手が存在するという考え方のことをいいます。
人はお互いの行動の影響からさまざまな気持ちになり、その結果としてさまざまな行動を起こします。
相手によって接し方や気持ちも変わるため、相手をより理解するためには相手の行動にどんな目的があるのかを理解することが大切な視点となります。
人との関係によって行動が変化するので、行動の「目的」を理解することが大切!
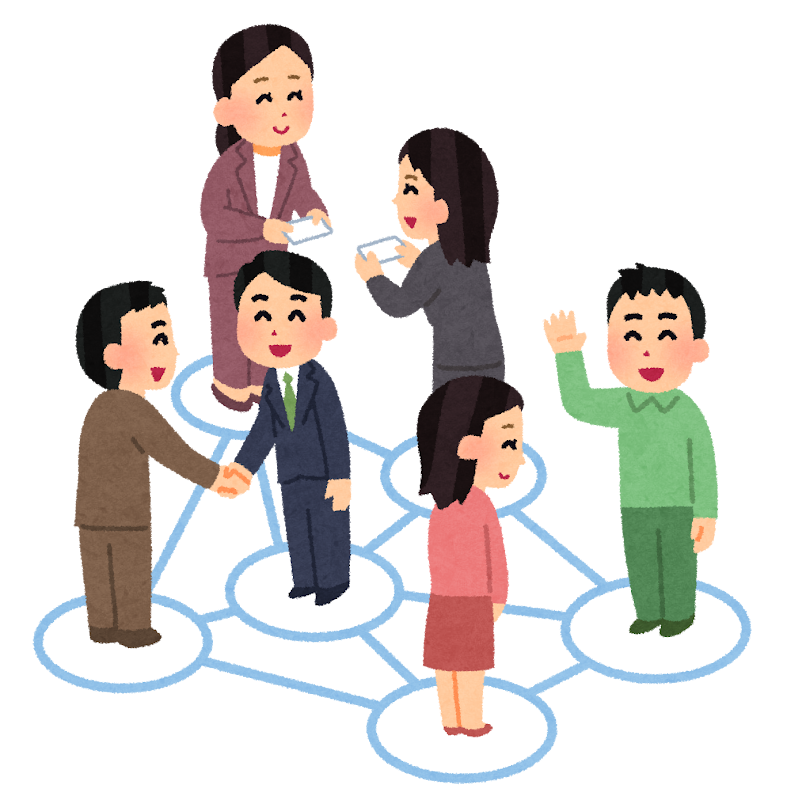
⑤認知論
認知論とは、あらゆる物事を人は主観的に認知しているという考え方のことをいいます。
簡単にいうと、事実をありのままに客観的に理解するということはそもそも難しく、誰もが自分の主観を通して事実を客観的に把握しているつもりになっているという考え方になります。
感じ方は人それぞれで、誰もが思い思いに物事を受け止めている!

では、アドラーは人はどのようにしてネガティブな感情に振り回されてしまうと考えたのでしょうか。
なぜネガティブな感情に振り回されてしまうの?
上記でも少しお話したように、人は悪いことが起きると
「何が悪かったのか」
と原因を探ろうとしがちです。
こうした考え方が悪いというわけではありませんが、あまりにも原因を探しすぎてしまうと過去に振り回されてネガティブな気持ちになりやすくなります。
いくら原因を探しても、過去は変えられません。

原因を探す以外にも、自分以外の誰かや環境のせいにしてしまうこともネガティブな気持ちにつながりやすいです。
自分を守るためには必要なことかもしれませんが、あまりにも原因を自分以外に求めすぎると自分に嘘をつき続けるような状態になってしまいます。
結果的に状況が変わるわけではないので、より苦しい状況が長く続いてしまう要因にもなりかねません。
大事なことは、自分の目標や目的のためにどんな行動ができるのかを考えて実行することです。

では、子どもがネガティブな気持ちに振り回されているときにご家庭では何ができるでしょうか。
子どもが自分の力を信じるための「勇気づけ」
アドラー心理学の中には、「勇気づけ」と呼ばれる技法があります。
勇気づけとは、子どものありのままに受け入れ、いつも見守っているというメッセージを送ることです。
勇気づけは単純に子どものことをほめたり励ましたりするということではなく、子どもの行動に対して感謝の気持ちや行動の過程を認めていることを伝える方法になります。
行動の結果に注目するとどうしても「できた」か「できなかったか」の2択になってしまいがちです。
それだと、どうしても「できなかった」時に子どももママも落ち込んでネガティブな気持ちになってしまうのではないでしょうか。
そんな時に、行動の過程に注目して評価をする勇気づけを行うことによって、少しずつ子ども自身が自分の力を信じられるようになっていきます。

- 結果だけに注目しない
- 子どもへの「共感」「尊重」「信頼」を大事にする
- 子どもの行動をコントロールしようとしない
子どもが失敗してしまったときにも、上記のポイントを意識して挑戦したことを尊重し、次のチャレンジでどうするといいかを一緒に考えるだけでも子どもの気持ちは変わっていきます。
子どもの行動を変えるのに即効性はありませんが、長い目で見て「勇気づけ」の声かけは子どもにとってもママにとってもいいのではないでしょうか。。
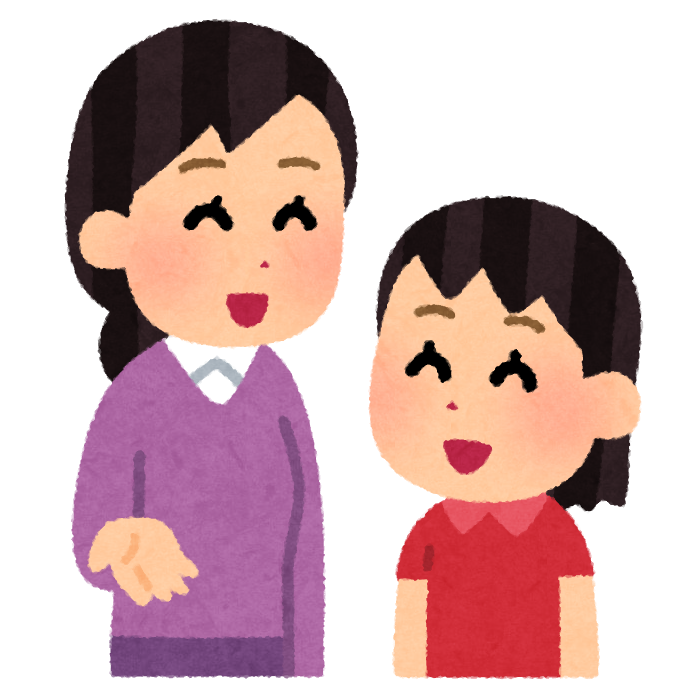
おわりに
今回は、ネガティブ思考をポジティブ思考に変えていくアドラー心理学の活用法についてお話ししていきました。
特に、難しいことをする必要はなく、子どもの行動の結果ではなく過程に注目していくことで少しずつ子どもの意識も変わっていきます。
即効性があるものではないので、途中でくじけてしまうかもしれませんが節目ごとに勇気づけの視点を取り入れるだけでもいいのでやってみるのもおすすめです。
私自身、相談に来ている子たちにも頑張っている過程について、認めていくような声かけを続けていますがなかなか子どもたちの考え方は変わりません。
それでも、続けていくうちに少しずつ
「ここまではできたからそこはよかった」
「できなかったけど、やろうと思えただけでも一歩前進」
そんな言葉が子どもたちから出てくる場面が何度もありました。
子ども自身が自分のことを認めてあげられるようになることによって、子どもたちの生きる力につながると私は信じています。
今回も読んでいただきありがとうございました。







