小1で登校しぶりが始まったら?子どもの不安に寄り添う4つの対処法

新年度が始まって1週間が経ちました。
給食も開始し、普段の学校生活をおくるうちに子ども達の新年度の浮足立った様子が和らいだように感じます。
このような時期に少しずつ増えてくるのが、小学校新1年生の登校渋りの相談です。
- 「ママと一緒じゃないと登校せず、昇降口でもなかなか離れられない」
- 「朝なかなか学校に行きたがらない」
- 「夜になると、次の日の学校が嫌でしくしくと泣いてしまう」
こんな話がよく出てきます。
そこで今回は、小学校新1年生が登校を渋った時にご家庭でできることについてお話ししていきます。
Contents
新1年生が登校を渋る理由は?
今まで相談を受けてきた中で、よく出てきた子ども達が登校を渋る理由は
- さみしくてママと離れたくない
- 給食が全部食べられないかもしれないから不安
- 45分間ずっと座って勉強するのが嫌
- 幼稚園・保育園の先生と違って、小学校の先生は怖い
この4点が多かったように感じます。
①ママと離れるのが不安
さみしくてママと離れたがらないと理由が、今までの相談の中でも特に多かったです。
新しい環境に不安を感じた子どもが、安心できるママの存在を求めることはとても自然なことです。
特に、新しい場所や人に慣れるまでにとても時間がかかる子どもにとっては、学校という場所はとても不安の大きい場所です。
学校という場所に行くことによって、
そうした不安から「学校に行きたくない」

②給食への不安
小学校では、給食の配膳から食べるまでの時間が短くなりがちです。
一年生の最初の頃は、
給食の献立も、家庭で出てくるようなメニューばかりではなく、
それ以外にも学校給食では、必ず牛乳がセットで出されるため、牛乳が苦手な子からすると飲むのがとても大変なことだと思います。
そうした制限時間や食べなれないメニューが子どもにとって負担と
それ以外にも、発達障害などの特性から偏食が強い子どもにとっても、給食の時間はとても苦痛な時間になりやすいです。

③勉強が嫌
小学校と幼稚園や保育園との一番の違いは何といっても、学習の時間をメインとしているところではないでしょうか。
1年生では、生活や図工、体育、音楽などいわゆる座学以外の授業も多いですが、それでも算数や国語などの学習は毎日あります。
そうした中で、漢字がなかなか覚えられない、数の概念が定着しにくいといった理由から勉強への抵抗を示す子も少なくありません。
1年生で学習への苦手意識を持ってしまうと、その後の学校生活もとても苦痛を感じやすくなってしまう要因になってしまいます。
それ以外にも、45分間の授業時間をずっと座って過ごすことに慣れずに、授業中に立ち歩きなどをしてしまう子どもにとっても勉強が苦痛な時間になりやすいです。

授業中に座っているのが苦痛と感じる子どもの中には、ADHDの特性が強い場合があります。この状態ってどうなの?と気になった時にできることについてまとめてみました。
勉強がわからなくて困っている子どもの中には、LDが隠されている場合があります。本人の努力だけで学習の定着が難しいので、頑張っても報われずに無気力な状態になりやすいです。LDっていったいなんだろうということについてまとめてみました。
③小学校の先生が怖い
この理由で学校が嫌になってしまう子は、実は結構多いです。
30人前後の子ども達を一人の先生が指導する小学校のスタイルでは、どうしてもビシッと指導せざるを得ない場面が出てきます。
そうした先生の指導の様子が、幼稚園や保育園の時の先生の姿とのギャップにつながり、先生への恐怖心につながってしまうことも少なくありません。
ママ達からすると「小学校はそういう場所」という考えもあってか、先生が怖いことは当たり前と子どもの不安を聞き流してしまったという話もよく聞きました。
それ以外にも、小学校に入って初めて男性の先生が担任となって、怖い気持ちが出てきたというパターンもあります。
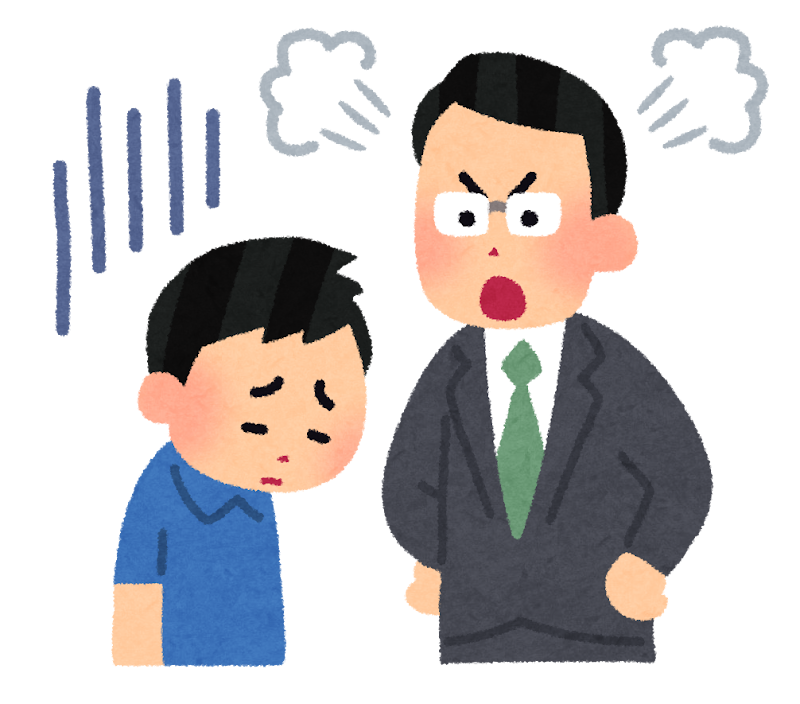
では、こうした不安を訴えて学校に行きたがらない子にどのように対応すればいいのでしょうか。
新1年生の登校渋りの対処法
上記のそれぞれの不安にどう対処していくかをそれぞれお話ししていきます。
ママと離れたくない時
ママと離れるのが不安という子どもの場合、おおむね2つの方法で経過を見ていきます。
- しばらくママも一緒に教室で過ごしてもらう
- ママを身近に感じられるようなお守りを作る
①ママも一緒に教室で過ごしてもらう
この方法は、ママのお仕事の都合や学校の受け入れ状況によっても実現できるかどうかが変わります。
この方法では、スモールステップで少しずつ段階を踏みながら、子どもが一人で学校で過ごすのも大丈夫と思えるように手助けしていきます。
よくある段階としては、
- ママと一緒に登校して、教室で一緒に授業を受ける
- ママと一緒に登校して、ママは廊下で授業の様子を見守る
- ママと一緒に登校して、ママは別の教室で待機する
- 登下校のみママと一緒にして、授業は一人で教室に入る
- 登下校を友達として、ママには家でたくさん甘える
このようなものがあります。
必ずしもこの段階で進むというわけではなく、子どもそれぞれの状態に応じて臨機応変に対応していきます。

②お守り作り
この方法がママと離れたくない子どもへの支援として一番よく使うものです。
ママと離れることへの不安が強い子どもにとって、ママの存在を身近に感じられるお守りがあるととても心強く感じます。
子どもとも相談しながらになりますが、今まで作ってもらったお守りは
- 家族写真をランドセルのポケットに入れる
- 筆箱の蓋の裏にママと取ったプリクラを貼る
- ママが普段使っているハンカチを貸してもらう
- ママと一緒にお絵かきしたカードを筆箱に入れる
- ママから毎日応援メッセージを書いてもらう
このようなものがありました。
特に、ママの写真やママのハンカチのようなものだと、ママの存在を身近に感じられるようで選ぶ子どもも多かったです。

特に1年生は筆箱がしっかりしているものが多いので、蓋の裏など普段からよく見える位置に写真や手紙が貼ってあると安心するようでした。
給食が不安な時
給食への不安は、時間とメニューで対応の仕方が変わります。
- 自分が20分で食べきれる量を把握する
- 家でも20分で食べる練習をする
- 全部食べられないかもしれないと思った時は、減らしてもらうようお願いする
- 献立表を見ながら不安なメニューをチェックする
- 食材と味付けどちらが不安になるのかを確認する
- 家で不安なメニューを食べる練習をする
- どうしても難しければ、不安なメニューの時は量を減らしてもらうようお願いする
それぞれこうした対応の仕方があります。
上記のもの以外にも、子どもから話を聞いて何ができるかを一緒に考えることもよくあります。

以前の私が対応したケースでは、
「おしゃべりに夢中になって、食べるのが遅くなってしまったから、なるべくしゃべらないようにしてみる」
と子ども自身で考えて実行してみて、うまくいった子もいました。
人それぞれ給食が不安に感じる要素は異なりますが、その子がどんなことに不安を感じるかを整理することで解決への糸口が見つかることも少なくありません。
勉強が嫌な時
新1年生にとって慣れない勉強が苦痛になってしまうことはとても自然なことです。
少しずつやっていくうちに理解できるようになって楽しくなってくればいいのですが、中にはなかなか理解できなくて苦しくなってしまう子もいます。
勉強への拒否感が出てきてしまうと、手助けしたくても難しくなってしまうかもしれません。
なので、1年生の間は遊びながら学ぶという点を意識した働きかけが大切になっていきます。
このようなカルタを使ってひらがなの形を覚えられるように工夫したり、おやつの時間にお菓子の個数を一緒に確認するなどして数の概念に触れさせたりすることが抵抗なくできておすすめです。
足し算引き算は具体物があるとやりやすくなるので、実際に家にあるお菓子や果物などを使って一緒にやってみるのもわかりやすくていいかもしれません。

先生が怖い時
幼稚園や保育園の先生は優しかったけど、小学校の先生はよく怒っている気がすると訴える子どもは少なくありません。
中でも、自分が怒られているわけではないけれど、他の子がいたずらをして怒られている姿を見て怖くなってしまった、という話をよく聞きます。
幼稚園や保育園に比べて、守らなければならないルールややらなければならないことが小学校に入ると格段に増えます。
そうした規律を守るように指導する先生の姿を怖く感じてしまう子は一定数います。
子どもが先生への恐怖心を訴えてきたら、まずはそのままの言葉で受け止めていただくことをおすすめします。
ママが否定せずに話を聞いてくれるだけで、落ち着く子どもはとても多いです。

それでもなかなか落ち着かない子には、
- 怖い以外の先生の姿はあるか
- どんな風になったら怖くなくなりそうか
- 学校の中で楽しいと感じる時間はあるか
といった点を話していただくといいと思います。
こうした子どもとの話の中で、担任の先生にも協力してもらえた方がいいこともあるかもしれません。
そうした時には、先生に対する否定的な話はなるべく伝えずに、どんなことを協力してもらいたいかを具体的に話していただくと協力が得られやすいです。
たとえば、
- 休み時間等に先生と一緒に遊べる時間を作ってもらう
- 子どもが登校したタイミングで、やさしく声をかけてもらう
- 連絡帳などで前日の様子を伝えて、そのことを先生から話題に出してもらう
こんな先生との関わりを通して、子どもの先生に対する不安が和らぐことがあります。
どんな風に伝えたらいいのか悩んでしまう、ということがありましたら学校のスクールカウンセラーに相談するのもおすすめです。

それぞれの不安がどのぐらいの強さか自分で客観的に考えられるようになると、不安が小さくなることもあります。
客観的に考える手助けとして、
こうした本を活用してみるのもおすすめです。
おわりに
今回は、小学校新1年生の登校渋りにご家庭でできることについてお話ししていきました。
新年度が始まって一週間も経つと、学校への抵抗感を示す子どもがとても増えます。
不安な気持ちはそのままにしていくと、どんどんと大きくなっていきやすいので、最初の小さな訴えのうちに対処ができると子どもにとっても安心です。
先の見通しがわからない状態では、大人でも不安に感じてしまいます。
子ども自身が、
「これなら何とかなりそう」
という見通しが持てると、不安も小さくなって登校を渋る回数も減っていきます。
今回のお話が少しでも参考になったら嬉しいです。
今回も読んでいただきありがとうございました。







