不登校の子どもの進路を夏休みにどう考える?家庭でできる進学準備

夏休みも折り返しに入ってきました。
不登校の中学校3年生の子どもがいるご家庭では、いろいろと気持ちが落ち着かない日々があったのではないでしょうか。
ただでさえ中学校3年生といえば進路のことで頭を悩ませる時期でもあります。
そこに、子どもが不登校という状態も合わさると心配になってしまう保護者の方も多いと思います。
そこで、今回は不登校の子どもの進路選択のために夏休み中にできることについてお話ししていきます。
不登校の子どもの進路で不安に感じること
子どもが不登校の場合、保護者からさまざまな不安の声を聞くことがあります。
- そもそも高校に行けるのか
- 内申がよくなくても受検はできるのか
- どんな高校を選べばよいのか
このような質問が特に多いように感じます。

そもそも高校に行けるの?
子どもが不登校の時に、保護者の方が一番に気にされるのが”そもそも高校に行けるのか”ということではないでしょうか。
- 勉強もまったくしていない
- 外出もほとんどしない
- 人とのかかわりが薄くなっている
このような子どもの姿を見て不安を募らせるママが非常に多いです。
基本的には、高校は本人が望めば行くことができます。
不登校の中学生のお話を聞く機会も数多くありますが、大半の子は
「とりあえず高校は卒業したい」
という気持ちを持っていることがほとんどでした。
なので、ご家庭でもまずは
- 高校進学の希望の有無
を確認するところから始めていただくといいと思います。
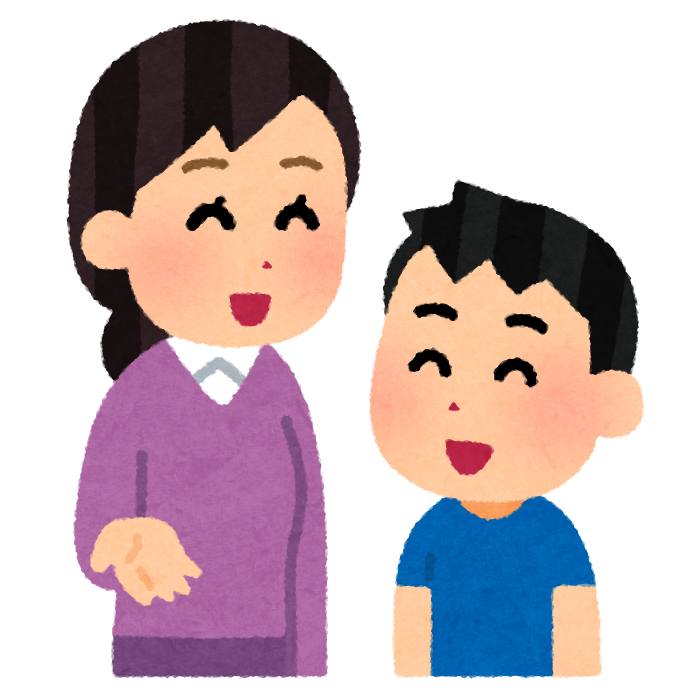
そうした希望を確認した上で、その先の志望校をどこにするのかや受検方法はどうすればいいのかについて考えていくと流れがスムーズになります。
内申書が悪くても大丈夫?
不登校の場合、学校や本人の学習の取り組み状況にもよるかと思いますが、ほとんどの場合は1という成績を付けられることが多いのではないでしょうか。
- 定期テストは必ず受ける
- 課題をこまめに提出する
- 別室に登校する
中には、こうした取り組みをして2がもらえたという事例もあります。
それでも出欠席の欄には、欠席の数が多くなってしまうので、そのことが受検に影響するのではないかと心配になるご家庭が非常に多いです。

地域によって対応はさまざまではありますが、公立高校の受検の際に内申書を重視しない受検方法を選択できるところもあります。
その方法を選択する場合には、子どもが不登校であったことを学校に書面で作成していただくことになります。
そうすると内申書の点数ではなく、学力試験の結果のみで合否を判定してもらえる、ということにつながります。
合否の判断基準が、学力試験の結果のみになるので、子どもには志望校に見合った学力を身に付けてもらう必要があります。
不登校の子どもの中には、「みんなと一緒に勉強するのは苦手だけど、一人で黙々と勉強するのは好き」という子もいるので、そうした場合にはこうした選択肢を選ぶのもいいのではないでしょうか。
しかし、気を付けてほしいことは
「受検もできるし、見合った学力があれば合格もできるが、合格がゴールではない」
ということです。
せっかく合格できた高校も通えなければ意味がありません。
なので、3年間通い続けられるかどうかということを考えた上での学校選びが必要になってきます。
高校合格=ゴールではない!
3年間の学校生活をイメージした高校選びが大切!
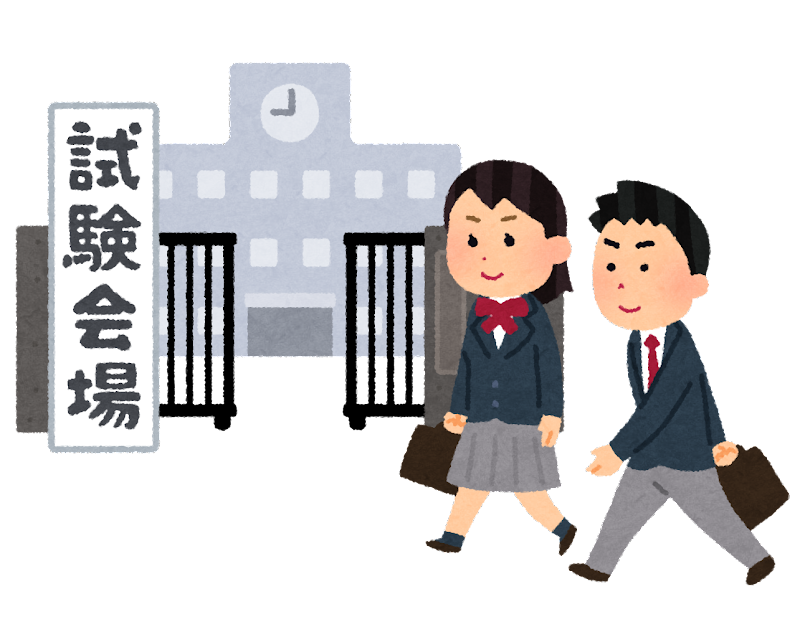
人との交流ができてなくて心配
不登校の子どもの中には、仲の良かった友達との交流を拒む子もいます。
極力、自分を知っている人に会わないよう外出を控える子どもも少なくありません。
そうした子どもの姿を見ていると、
「このまま一生誰ともかかわれないのではないか」
という不安に駆られるママもいるのではないでしょうか。
私自身がこれまで経験した中では、友達との交流が少なくなってしまった子ども達も「このままではよくない」という思いを抱えていることが非常に多かったです。

そうした子ども達は、自分のことを知っている人たちの中に行くことへの不安が強く、だからこそ高校という新しい環境に対して期待感を持っている子も数多くいました。
同じ趣味や価値観を持ち、居心地のいい関係を築ける友達がほしい、そんな願いを持っている子も少なくありません。
なので、どのような環境なら自分がいきいきと生活できるかを考えることによって、より具体的なイメージができるような働きかけがとても重要でした。
「自分らしく生きる場所」
この言葉を指標として、子ども達に高校選びをしてもらうと、それぞれに合った高校を選んで楽しく通える子がほとんどでした。
自分らしくを知るためには、自分のことを深く考える必要があります。
- 好きなものや好きなこと
- 居心地のいい雰囲気はどんなものか
- 得意なこと
- 苦手なこと
- やりたいこと
- やりたくないこと
こんなことを考えながら自分について整理すると、自分らしく過ごせる場所を見つけやすくなります。
子どもだけでは整理が難しい場合があるので、ママ達から見た子ども達についてお話ししていただくのもいいかもしれません。

では、子ども達とさまざまな話をした後、どのように高校選びをすすめていけばいいのでしょうか。
不登校の場合の高校選びのポイント
私が、日頃から相談の中で子ども達やママ達に話しているポイントは、
- そもそも高校に行きたいかどうかの意思確認
- 子どもの生活状況にあった進路選択
- 子どもの興味・関心のある分野を探す
この3つです。
必ずしも高校に行かなければならないというわけではないので、高校に行きたいかどうかの意思確認をすることはとても大切です。
そこで子ども自身が行きたいと考えた時に、②・③のポイントを踏まえて高校を探すとスムーズに行くことが多かったです。
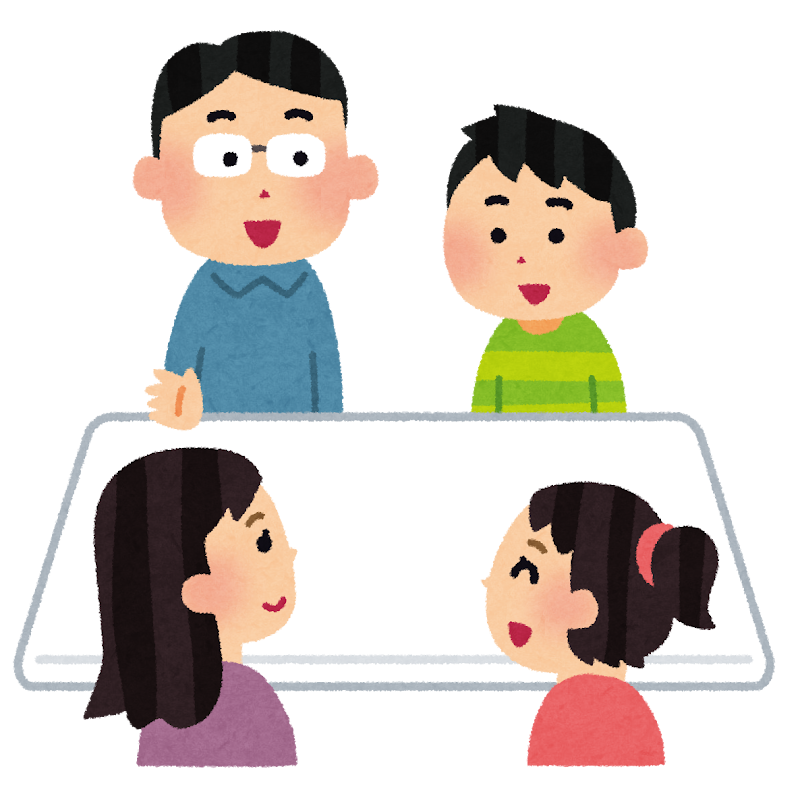
実際に、自分が住んでいる都道府県にどんな高校があるかわからない。
そんな時には、
この本を参考にしていただくと、自分が求めるポイントに合った高校が見つけやすいです。
また、実体験からの不登校の進路探しについて書かれた
こちらの本もわかりやすくておすすめです。
おわりに
今回は、不登校の子どもの進路選択のために夏休み中にできることについておはなししていきました。
不登校の子どもに対して、進路について話を切り出すのはなかなか難しいかもしれません。
せっかく不登校を選択して心穏やかになったのに、いらぬ波風を立ててしまうのではないかと不安に駆られる方も時折いました。
しかし、子ども達自身も「いつかは考えなければならない」という気持ちを抱えています。
なので、少しずつ日々の会話の中で将来の希望について話をしていくことで、自然と高校のことについても触れられるようになっていきます。
時には、感情的になってしまったり内に籠ってしまったりすることもあるかもしれません。
それでも子ども達自身、将来に向けて自分で選択する時が必ずきます。
そうした選択を後押しできるように、ママ達には子ども達のことを信じて待ってもらえたら嬉しいです。
今回も読んでいただきありがとうございました。







