思春期に増える摂食障害とは?過剰なダイエットに気づいたときの対応法

- 「うちの子が最近過剰なダイエットをしているような気がする」
- 「食事を摂ろうとしないで、お弁当もゴミ箱に捨てている」
- 「夜中に冷蔵庫の中の食べ物を漁って食べている」
小学校高学年から中高生の女の子のママからこのような相談を受けることが時折あります。
最初のうちは、
「女の子だし、見た目が気になる年齢になったからダイエットでもしているのかな」
と気楽に考えていたママも、どんどん細くなっていく子どもの姿を見て焦ってしまい相談に来るケースもありました。
そこで今回は、過剰なダイエットの裏に隠れているかもしれない摂食障害についてお話ししていきます。
Contents
そもそも摂食障害って何?
摂食障害と言っても、必ずしも食事がまったく食べられなくなる状態だけというわけではありません。
摂食障害は主に3つのタイプに分けられていて、それぞれ
- 神経性やせ症(拒食症)
- 神経性過食症(過食症)
- 過食性障害
となります。
①神経性やせ症
一般的に摂食障害と聞いて思い浮かべる症状は、この神経性やせ症の症状だと思います。
わかりやすく拒食症とも呼ばれているため、なんとなくイメージもしやすいのではないでしょうか。
この症状の特徴は、太ることに恐怖を感じて食べられなくなったり、食べたものを吐き出そうとしたりしてしまうことにあります。
食事の摂取量も少なくなるため、体重もどんどん軽くなり見た目にも症状があることがわかりやすいです。

- 食事:制限or制限しながら過食
- 嘔吐・下剤使用:制限タイプはしないが、過食タイプは嘔吐と下剤使用がある
- 体重:適正体重よりも軽い場合が多い
②神経性過食症
過食症という言葉も聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
この症状の特徴は、拒食症とは違い体重の変化があまり見られないことにあります。
自分では抑えられないドカ食い(過食)と嘔吐を繰り返しますが、体重にはあまり変化が見られないためなかなか症状の発見につながりにくいものでもあります。

- 食事:過食する
- 嘔吐・下剤使用:ある
- 体重:標準体重か少し重いぐらい
③過食性障害
この症状の特徴は、ドカ食い(過食)はしても嘔吐はしないので体重はどちらかというと増える傾向にあります。
不思議なことに、極端にやせているよりも太っている方があまり危機感を覚えにくいため、病気に気づかれにくいのが過食性障害の怖いところでもあります。
食欲が旺盛な姿を見ていると安心してしまうママも多く、
「こんなに食欲があるなら大丈夫」
と楽観視してしまうケースも少なくありません。
お小遣いやバイト代などをすべて食べ物につぎ込んでしまうケースもあるため、あまりにも過剰に食べる場合は過食性障害の可能性もあるかもしれません。
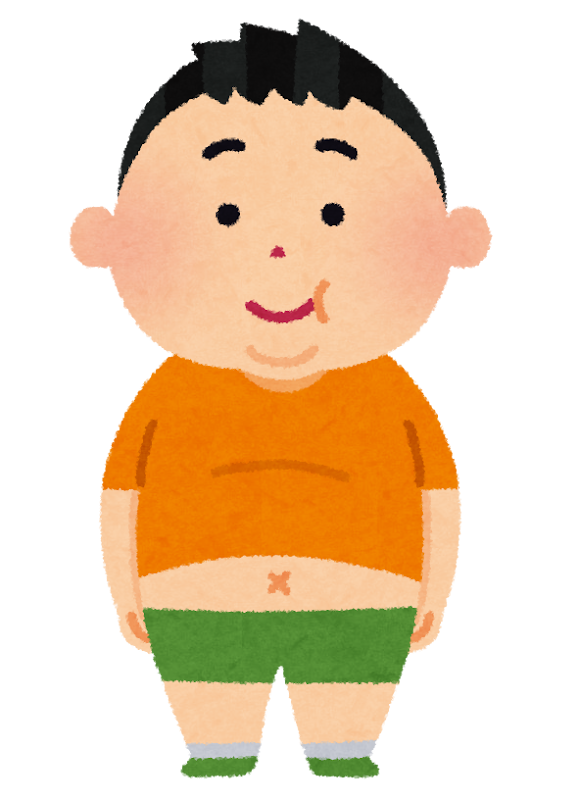
- 食事:過食する
- 嘔吐・下剤使用:ない
- 体重:適正体重よりも重い
では、摂食障害の原因にはどんなものがあるのでしょうか。
摂食障害の原因にはどんなものがあるの?
なんとなく摂食障害になるのはやせたい気持ちが強いから、という考えが根強いと思います。
もちろん「やせたい」から摂食障害になる子も少なくありませんが、それ以外にも日々のストレスから食事に影響が出てしまうことがとても多いです。
特に、真面目で頑張り屋さんな完璧主義の子どもほど、自分の至らなさに苦しんで摂食障害になってしまう危険性があります。
- 「テストでは頑張っても思うような点数が取れなかったけど、ダイエットは頑張れば頑張った分だけ体重が落ちて嬉しい」
- 「友達との関係でむしゃくしゃしても、おいしいものをいっぱい食べたら忘れられる」
- 「いっぱい食べちゃったとしても、吐いたりお薬(下剤)を飲んだりすればリセットできるから大丈夫」
こんな言葉が子ども達から出てくることもあります。
頑張り屋さんな子どもは、自分の不安や悩みを自分だけで解決しようと抱え込んでしまいがちです。
少しでも普段の様子と違うなと感じたら、子どもの話を聞いてみるのもおすすめです。

では、摂食障害が進むと身体にどんな影響があるのでしょうか。
摂食障害は身体にどんな影響があるの?
神経性やせ症と神経性過食症では身体に出てくる影響は違います。
神経性やせ症による身体の影響
食事の量が少ないため、身体を動かすのに必要なエネルギーが足りなくて身体が省エネモードになってしまいます。
省エネモードのため、体温や血圧も低くなり身体を動かすのも億劫にもなります。
栄養が不足するので、髪の毛がパサついたり抜けてしまったりすることもあります。
脳へも必要なエネルギーが行かなくなるため、脳が委縮してしまう危険性もあり脳に障害が残るかもしれません。

神経性過食症による身体の影響
神経性過食症の場合、ドカ食いと嘔吐によって身体への影響は違います。
ドカ食いの時に、ケーキやアイスのような高カロリーな食べ物を短時間でいっぱい食べるケースがよく見られます。
高カロリーな食べ物を過剰に摂取することにより、肝臓に脂肪がついてしまう脂肪肝や膵臓が炎症を起こす急性膵炎などを発症する危険性が高いです。
嘔吐では、頻繁に嘔吐することにより胃液が歯を溶かしたり、吐きだこと呼ばれる傷が手の甲につくこともあります。
それ以外にも、低カリウム血症と呼ばれる身体の中のミネラルのバランスが崩れてしまうこともあります。
めまいや不整脈を起こしやすくなりますが、重症化するまで気づかれにくいため注意が必要です。
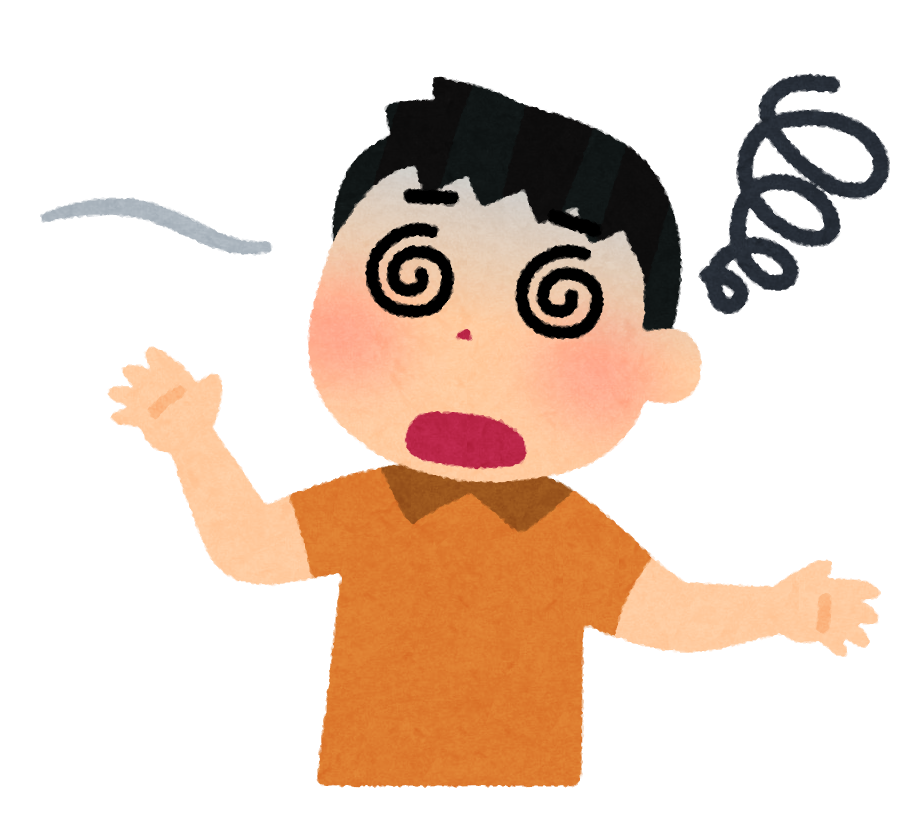
では、子どもが摂食障害かもしれないと感じた時に、どのような治療がひつようなのでしょうか。
摂食障害の治療はどんなものがあるの?
摂食障害は、時間が経てば経つほど命の危険が迫る病気なので早めの治療が必要不可欠です。
- 精神科
- 心療内科
- 内科
- 小児科
このような医療機関を受診することが大切です。
できれば摂食障害を扱ったことのある医師がいる病院が望ましいですが、わからない場合には学校の養護教諭やスクールカウンセラーに相談してみると病院を案内してくれるかもしれません。

病院に行くと、
- 食事指導
- 薬物療法
- 心理療法
といった治療が受けられます。
食事療法
管理栄養士が身体に必要な栄養素などを踏まえて、子ども達それぞれに合わせて食事の指導を行っていきます。
神経性やせ症の子どもは、食べることへの抵抗感も強いため無理に食べさせようとするのではなく、元気になった後の自分の姿をイメージしてもらって治療への意欲も高めることも大切です。
神経性過食症の子どもは、好きなタイミングで食事をしていたのを規則正しいリズムでの食生活に変えていくように指導していきます。
どちらの子どもも大切なことは、無理に治療を推し進めるのではなく、それぞれのペースに合った治療スケジュールを立てていくことです。
そうすることによって、失敗したことへの挫折感を極力感じさせることなく治療を進められます。

薬物療法
拒食や過食に直接効くお薬はありません。
しかし、不安や落ち込みといった気分に作用するお薬やむくみを取るお薬、拒食でなくなってしまった生理を起こすお薬など、症状に合わせてお薬を使うことで気持ちが楽になることもあります。
調子が良くなってくると、ついお薬の量を勝手に減らしたくなってしまいますが、必ず医師の処方通りにお薬を飲むことが大切です。

心理療法
摂食障害の原因は、やせたいという欲求だけではなくストレスなども含まれます。
食事指導や薬物療法で症状が落ち着いても、ストレスを抱えている状況に変わりはありません。
子どもが抱えているストレスを完全になくすことは難しいですが、ストレスにうまく対応する力を伸ばすことが心理療法の目的となります。
自分の中で、ストレスとなっているものは何かや自分の首を絞めているような考え方はあるかなどを整理することによって、少しずつストレスにうまく対応する力を伸ばしていきます。

もっと摂食障害について知りたい
今回は、摂食障害の概要を簡単にまとめたものになるので、もっと知りたいと感じた方は
この本が治療の流れや子ども達の気持ちの変化がわかりやすく、ママ達にもおすすめです。
子どもにも読んでほしい場合には、
この本がイラストを使ってわかりやすく書かれているのでおすすめです。
おわりに
今回は摂食障害についておはなししていきました。
思春期になると、周囲からの目が気になって自分の容姿に自信が持てなくなってしまう子も少なくありません。
最初のうちは気軽に始めたダイエットも、気づいたら過剰な食事制限になってしまったというケースもありました。
子ども自身にやせたい気持ちはなくとも、なんとなく食べる気持ちになれなくてどんどん食事が取れなくなってしまったケースも見ました。
何がきっかけで摂食障害を発症するかは人それぞれです。
少しでも子どもの様子に違和感を覚えたら早めの受診をおすすめします。
今回も読んでいただきありがとうございました。






