子どものコミュニケーション力を育てる!表現力を伸ばすための関わり方3選

子どもとの相談の中で時折、
- 「友達にいじられて嫌な思いをしたけど、相手になんて言ったらいいかわからなかった」
- 「いつも係活動の仕事を押し付けられるから断りたい」
- 「放課後に一緒に遊びたいけど、断られたらと思うと誘えない」
こんな話を聞くことがあります。
興味のあるものや趣味の話などは楽しく話せる子が多いのですが、いざ誘ったり断ったりということになると途端に何を話せばいいのかわからなくなってしまう子も少なくありません。
そこで今回は、子どもの言葉の表現力を高めるためにできることについてお話ししていきます。
Contents
そもそもコミュニケーションってどんなもの?
コミュニケーションは、一般的には他者と意思疎通する力のことを言います。
具体的には、
- 相手の話を理解する力
- 自分の気持ちを表現する力
この2つがコミュニケーションには求められます。

①相手の話を理解する力
コミュニケーションは、一方的に自分の話をするだけでは成り立ちません。
相手の話をしっかりと聞いて、どんな内容だったか理解する力が求められます。
しかし、日本語の表現には比喩表現のような遠回しに伝えるような言葉も数多くあります。
自閉症スペクトラムの子どものように、言葉を文字通りに受け止めてしまう子はそうした表現を真に受けて傷ついてしまう子もいました。
「いつか一緒に遊びに行こうね」
こんな風に友達から言われて、いつかをずっと待ち続けて傷ついてしまったケースやいつかの予定をすぐに決めようと相手に詰め寄ってしまったケースもありました。
相手の話を理解するということは、言葉をそのまま受け止めるということではなく、その言葉の裏側にある相手の気持ちも理解することが必要です。
その場ですぐに相手の話を理解できればいいのですが、実際には難しい場面も多いと思うので、そんな時には相手に聞き返すなどのスキルも求められます。
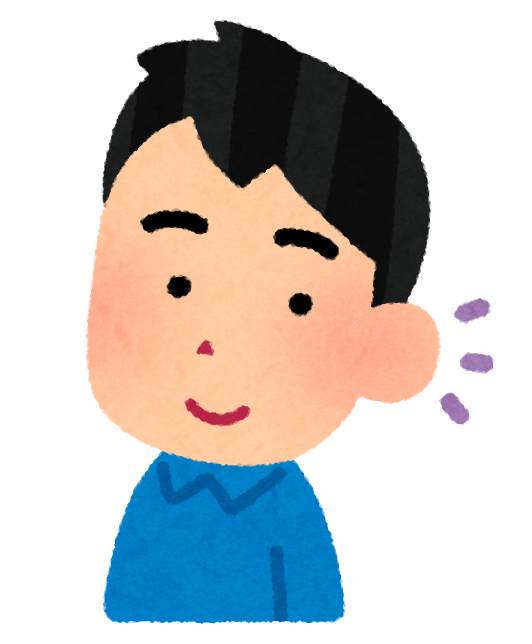
②自分の気持ちを表現する力
相手の話を聞くだけではなく、自分の話をすることもコミュニケーションには大切です。
やみくもに自分の知っていることを話すのではなく、その時の話題に沿って自分の気持ちを織り交ぜて話すことは大人でも難しく感じます。
- 自分が話したい気持ちが強すぎて、一方的に話し過ぎてしまった
- 何を話せばいいかわからなくて、みんなの輪の中でずっと黙ってきいているだけになってしまった
- 「どう思う?」と聞かれてうまく答えられず、友達から「無視してるでしょ」と怒られた
自分の気持ちを上手に表現することができなくて、このようなトラブルにつながってしまったケースもありました。
相手の話を聞くだけでも、自分の話をするだけでもコミュニケーションは成り立ちません。
お互いが程よいバランスで会話を進めることによって、コミュニケーションは作られていきます。
こうしたバランスは会話の積み重ねが必要不可欠なので、一日でどうにかなることではありません。

では、子どもの気持ちを伝える表現力はどのように身に付けていけばいいのでしょうか。
言葉の表現力を身に付けるためにできること3選
子どもが自分の気持ちを表現するために欠かせないものは言葉の表現力です。
言葉の表現力を身に付けるためにご家庭では、
- 家庭内での会話の時間を作る
- 子ども自身が使える言葉の数を増やす
- さまざまな年齢の人と関わる機会を作る
この3点を意識していただくのがいいと思います。
①家庭内での会話の時間を作る
上記でも少し触れましたが、コミュニケーションには会話の積み重ねが欠かせません。
子ども達が、一番緊張しないで会話の経験を積み重ねられるのは家族との会話です。
間違った言葉遣いをした時やうまく表現できない時も、家族ならさりげなくフォローをすることができます。
- 「そんな時は○○という風に言うといいかもね」
- 「今は○○みたいな気持ちって言いたかったのかな」
こんな風に会話の中で伝えられるかもしれません。
こうしたフォローだけではなく、話す際に大事な「いつ・どこで・だれと・何をした」といった会話の流れも作ることも大切です。
話すのが苦手な子どもの場合、言葉で表現する力が弱いケースだけでなく、話す順番がわからないケースも多くあるからです。
その時々で思いつくままに話してしまって、友達から「何が言いたいかわからない」と言われてしまうことが多くなるにつれ、話すことに自信がなくなってしまう子もいます。
なので、家庭内の会話で
- どんな順番で話すと相手に伝わりやすいのか
- こういう時には、どういう言葉で表現するといいのか
こうしたポイントを子どもに意識させるように会話する時間を作るのもおすすめです。
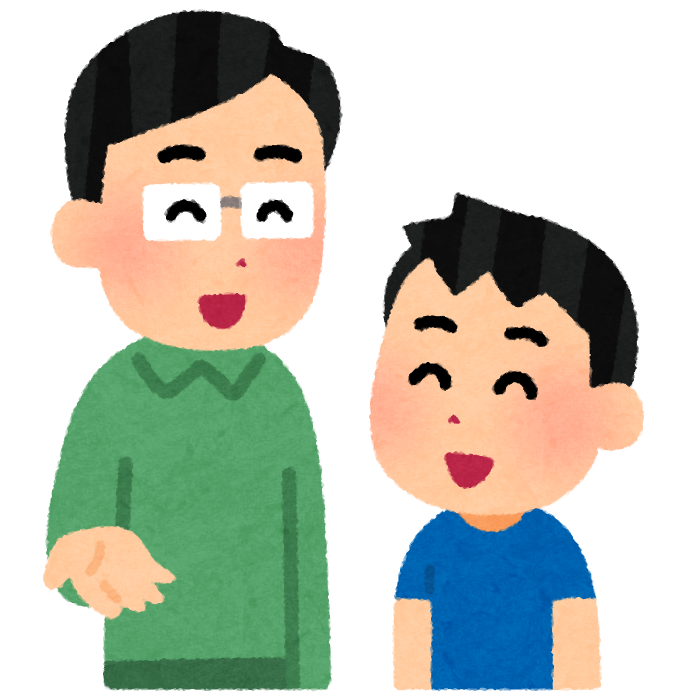
②子ども自身が使える言葉の数を増やす
言葉に限らず、よくわからないものは使おうという気持ちにはならないと思います。
言葉の意味や何のためのものかがわかって初めて、自分も使ってみようという気持ちになるのではないでしょうか。
最近では、「ヤバい」という言葉で「嬉しい」「楽しい」「悲しい」「辛い」などさまざまな意味を持たせて会話する場面が、子ども達の間でよく見られるようになりました。
そうして使う言葉の数が少なくなればなるほど、自分を表現する言葉の数も少なくなってしまいます。
これでは、自分の気持ちが自分でもわからなくなってしまう危険性につながりかねません。
使える言葉の数が増えると自分の今の気持ちを表現する力が高まり、コミュニケーション力の向上にもつながります。
使える言葉の数を増やすためには、本を読むなどして言葉の知識を蓄えることが大切です。
この本はさまざまな場面で、どのような表現をすると相手に伝わりやすいかをわかりやすくまとめてあるため、子ども自身が読んで学ぶのにおすすめです。
③さまざまな年齢の人と関わる機会を作る
最近はコロナ禍の影響もあり地域活動の機会がとても減っていました。
それでも今年から少しずつ地域活動行われるようになってきましたが、まだまだ以前と同じような水準とはいえない部分もあります。
地域活動を通してさまざまな年齢の人や普段の生活では関わらないような人と触れ合うことができると、コミュニケーションの質も高まります。
学校でも最近は縦割り活動という異年齢のグループでの活動を推奨しています。
こうした異年齢での活動を通して、人との付き合い方を身に付けていくことが子ども達にとっても貴重な体験となります。
地域活動以外にも親戚との集まりに参加することも、子どもにとってはさまざまな年齢の人との触れ合いにつながります。
無理に参加した方がいいというわけではありませんが、もし機会があれば参加してみるのもおすすめです。

おわりに
今回は、子どもの言葉の表現力を高めるためにできることについてお話ししていきました。
言葉の表現力という言葉だけで考えるととても難しいもののように感じるかもしれません。
しかし、言葉の表現力は親子で会話をしたり、スキンシップを取りながら遊んだりといった日常的に普通に行っていることで育っていきます。
あまり気負わずに親子の関わりを通して、子どもの言葉の表現力を伸ばしていってもらえるといいと思います。
今回も読んでいただきありがとうございました。







