不登校の子どもが家庭で安心して過ごすためにできることと生活の整え方

不登校の相談でよくある質問の一つに、
「学校を休んでいる時、家ではどんな風に過ごさせたらいいですか?」
というものがあります。
学校を休んで家で1日を過ごすと、時間を持て余してしまう子も中にはいます。
そこで今回は不登校の際の家での過ごし方について、私の経験を基にお話ししていきます。
Contents
不登校中、家にいる時のポイントは?
普段の相談の中では
- 基本的な生活のリズムを保つ
- 学校がある時間帯は、学校でできることだけやる
- 家の中での役割を持たせる
の3つを意識してもらっています。
①基本的な生活のリズムを保つ
この言葉だけ見ると簡単なことのように感じるかもしれませんが、意外と不登校の子どもはここができていません。
中には、起立性調節障害などの疾患があって朝起きられない、という子どももいますが、ほとんどの子が夜中に活動する方が居心地が良くて夜型生活になっています。
不登校の子どもにとって朝の時間はさまざまな葛藤があって居心地がいいものではありません。
朝は学校に行けていない自分と向き合わなければならないような気がして、その時間が苦痛で仕方ないのです。
そうした葛藤から逃れるために、朝はずっと寝て過ごしてしまいます。
一日の中で外からの刺激を一番受けずに済む時間帯は夜中です。
このような流れで不登校の子どもが昼夜逆転の生活になっていくというのが、今までの相談ではとても多かったです。
大事なことは、学校に行かなくてもいいのでせめて生活のリズムは崩さないようにしてほしい、と子どもと話し合っていくことです。
話し合いのポイントとして、生活のリズムを整えてあわよくば学校に行ってもらおう、という気持ちを出さないようにしてください。
こうした親の意図が透けて見えると、途端に子どもの心が離れていってしまうので、そこは意識していただくといいと思います。
ここの基本がしっかりとできていた子どもは、その後の復帰も早かったように感じます。

②学校がある時間帯は、学校でできることだけやる
この言葉だけだとなかなかイメージが湧きにくいかもしれません。
詳しく説明すると、学校がある時間帯は学校でできないこと、たとえば
- YouTubeで動画を見る
- TVを見る
- ゲームをする
- 漫画を読む
のような活動はしないということになります。
なので、家で過ごすときのポイントとして「これは学校でもやるかな?」という視点で考えられるといいと思います。
時々、「外出は学校ではやらないからやってはいけないですか?」と質問されることがあります。
学校でも校外学習がありますし、家庭での外出も社会科見学の一環としてさまざまなところにお出かけするのもいい経験につながるので、私は相談の中でもおすすめしています。

③家の中で役割を持たせる
これは小学校低学年から中学年くらいの不登校の子どもがいる家庭によくお願いしています。
不登校の子どもの中には、「学校に行けてなくて家に居場所がないように感じる」という不安を抱えている子どももいます。
学校に行けていないという罪悪感から、自分が家の中にいてはいけないのではないかと思い詰めてしまうことも相談の中で話が出ます。
そんな時に、家の中で子どもに何か家事をお願いして、子どもに家庭内での居場所を設定してもらうことがあります。
よくやってもらうのが、
- 洗濯
- ご飯作り
- 掃除
の3つです。
子どもがやってみたい、やれそうだな、と思うものでお願いできるといいと思います。
こうした家事のお願いをする時に大事なポイントは、「学校に行ってないんだからせめて家の手伝いぐらいして」、というお願いの仕方をしないことです。
このような言葉を言われてしまうと、ただでさえ不登校で罪悪感がいっぱいな子どもに対してより強い劣等感を与えてしまいます。
なので、あくまで強制ではなくお願いや協力を要請するというイメージで声かけをしていただくといいのではないでしょうか。

では、実際どのように家で過ごすのがいいのでしょうか。
不登校中の家での過ごし方は?
これまで私が受けてきた相談の中で、よく出てきた過ごし方について紹介していきます。
- 家の中での時間割を作って、そのスケジュールで過ごす
- 自分がやりやすい学習教材を使っての学習
- 料理を作る
- 興味のある場所に出かける
この4つが多かったように感じます。
①家の中での時間割作り
これは、特に小学校低学年から中学年の不登校の子どもに多かったです。
この年代はまだ自分で行動を管理する力が弱いところがあります。
なので、親と協力して一日の時間割を作ってそのスケジュール通りに過ごしてもらうようにすると、学校に行っていなくてもある程度生活のスタイルが確立していきます。
小学校低学年から中学年の不登校の子どもは、家にいる間暇を持て余して何をしたらいいかを頻繁に聞きにくることもよくあります。
その都度やることを考えていては、一緒に過ごす親の負担も大きくなってしまうので、一日の初めに今日の時間割を作成するのはおすすめです。

②自分がやりやすい教材での学習
小学校高学年から中学生の不登校の子どもになってくると、学習に対する不安が強くなってくる子も多くいます。
その中で学校から配られたドリルやワークを使って学習を進めてみようと考えられる子は、あまりいません。
学校で配られる教材は、基本的には学校での学習を補うためのものであり、授業を受けていることを前提とした問題つくりをされているため、不登校の子どもが学校の教材を使うのはとてもハードルが高いものになっています。
なので、子どもの理解力に合わせた学習教材選びが、学習意欲を高めるためには必要になってきます。
大事なことは子ども自身の勉強したい、という気持ちを尊重できるようにすることです。
子ども自身がもっといろんなことが知りたい、と思えるような経験を少しずつ積み重ねることによって、学習への意欲は高まってきます。
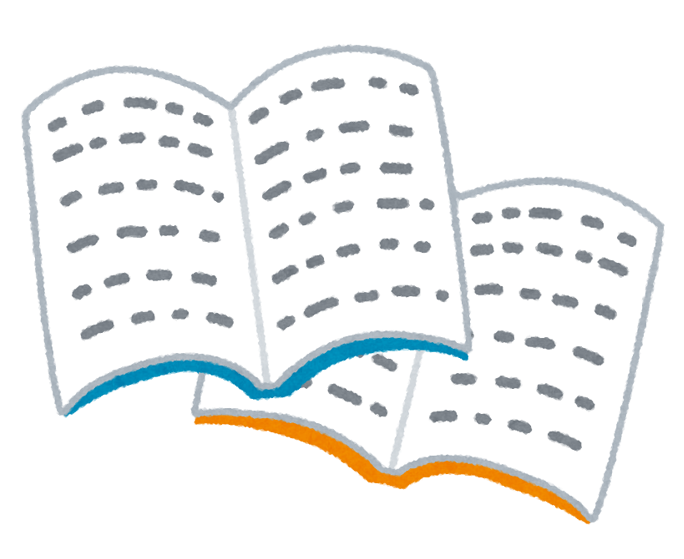
③料理を作る
中学生にもなってくると、子どもたちもある程度料理ができるようになってきます。
女の子だとお菓子作りにハマる子も多かったです。
男の子でも料理系のYouTubeを見て自分でも作ってみたくなった、という話を時々聞きます。
料理を作ることの何がいいのかというと、実際に調理をして料理が完成するという達成感と家族からおいしいと言われる充実感の2つが得られることだと思います。
どうしても家の中だけで過ごしていると、達成感や充実感を味わう機会は減りがちです。
こうした中でも、料理を作ることによってそれらの2つが得られるということがわかると、そこにやりがいを見出す子どももいます。
私自身、相談の中で料理を作る子どもに作った料理を写真に撮って見せてほしいとお願いすることがあります。
最初は、恥ずかしがっている子が多いのですが、回数を重ねていくうちに完成度も上がり、自信に満ち溢れた表情で見せてくれるように変化していくことが多かったです。
子ども達と写真を一緒に見ながら、この料理のどこが大変だったか、家族の反応はどうだったか、などさまざまなことを話すのはとても楽しい時間でした。

④興味のある場所に出かける
不登校の子どもの多くは外出を避ける傾向にあるように感じます。
特に、平日の昼間だと外出するのが悪いことのように感じるからか、なかなか外出に向かう気持ちにはなりにくいです。
そうして外出を避けていくうちに、段々と外に出るのが怖くなりひきこもりになってしまうパターンをこれまでいくつも見てきました。
こうした事態を避けるために、子どもが興味がある場所には積極的に出かけることを相談の中ではおすすめしています。
学校を休んでいるのに遊びに出かけることに罪悪感を覚える子どももいるので、そうした場合には
「今日は遠足のつもりでお出かけしよう」
「社会科見学の気分で行ってみよう」
のような声かけをしていただくのがいいと思います。
こうした経験を積み重ねていくうちに、子ども自身のエネルギーが溜まり次の行動へのステップへとつながっていくのではないでしょうか。

おわりに
今回は、不登校の子どもの家庭内での過ごし方についてお話ししていきました。
今まで、相談の中で家庭内での過ごし方が充実していた子どもは、その後の進路選びも比較的にスムーズに行っていたように感じます。
上記の例が必ずしもすべての子どもに当てはまるというわけではありませんが、少しでも参考になったら嬉しいです。
今回も読んでいただきありがとうございました。







