ネガティブ思考の子どもを前向きに支える声かけと家庭でできる工夫

普段の相談の中で
- 「子どもが物事をネガティブに捉えて困っている」
- 「ちょっとでも嫌なことがあると、それをいつまでもぐちぐちと言ってくる」
のような話を聞くことがあります。
ネガティブなことが印象に残ってしまうことは大人でもあるかと思います。
そこで今回は、ネガティブな気持ちに振り回されずにポジティブな気持ちになるためにどうしたらいいかについてお話ししていきます。
そもそも何でネガティブな気持ちって生まれるの?
心理学の用語でネガティビティバイアスという言葉があります。
この言葉の意味は、人はネガティブな情報の方がポジティブな情報よりも注意を向けやすく、記憶にも残りやすい性質を持つということです。
ママ達の中にも、過去の幸せだった思い出よりも辛い記憶のほうが鮮明に思い出されるという経験があるのではないでしょうか。
これもネガティビティバイアスによって引き起こされることです。
では、何でこのような現象が起きるのでしょうか。

ネガティビティバイアスは、人が生きていくためにさまざまなリスクを回避するために進化の過程で身につけたものではないかと考えられています。
目の前のリスクやトラブルに注意を向けることは、危険を察知して逃げるなどの対策を取るために必要なスキルです。
こうしたスキルが備わっていたからこそ、人はここまで発展し続けられたとも言えます。
しかし、こうしたスキルが子ども達にとってネガティブな気持ちが残りやすい要因にもなってしまうのです。

では、こうしたネガティブな気持ちの対処法についてママ達はどのように子どもに伝えていけばいいのでしょうか。
ネガティブな気持ちの対処法
子どもがネガティブなことを話していると、つい叱咤激励をしてしまうママも少なくないのではないでしょうか。
叱咤激励でネガティブな気持ちを払拭できる子ならばその対応でもいいと思います。
しかし、そういった子ばかりではないのも実情です。
そこで、そんな子たちにも使える叱咤激励以外の方法としては、
- ネガティブな気持ちリフレーミングをする
- ネガティブな気持ちの付き合い方を考える
この2つのやり方が効果的です。
ネガティブな気持ちをリフレーミングする
リフレーミングという言葉だけ聞いてもピンとこないと思います。
リフレーミングとは、別の角度から物事を見るという意味で使われていて、わかりやすく言うと「言い換え」という表現になります。
具体的な例を挙げると、
- 神経質→細かいところに気が付ける
- 打たれ弱い→受け止める力が強い
- 引っ込み思案→周りをよく見て動ける
このような形でネガティブな言葉を言い換えることができます。
無理にこうした考えになりなさい、というわけではなく「こんな考え方・見方もあるよね」という風に伝えていただけると子どもたちも受け取りやすいです。

大人になるとネガティブな言葉を自然とリフレーミングできる人もいると思います。
それは、子どものうちから自然とできたわけではなく、さまざまな経験を積み重ねた上でできるようになってきたスキルの一つだと私は考えています。
子どもには生まれた年数分の経験しかないからこそ、こうしたスキルを身に付けていく練習が必要になります。
ママ達が「これぐらいのことで…」と思えるようになったのも、自分が子供だった頃からの積み重ねの経験があったからこそではないでしょうか。
子ども達も「これぐらい…」と思えるようになるためのたくさんの経験が必要だということを、頭の片隅に置いておいていただけると対応にも余裕が出てくると思います。
- ネガティブな気持ちをポジティブに変えるには、たくさんの経験の積み重ねが必要!
- リフレーミングの声かけで、積み重ねのサポートをしてあげると安心!
ネガティブな気持ちとの付き合い方を伝える
ママ達は、自分のネガティブな気持ちとうまく付き合えていますか?
大人でも自分のネガティブな気持ちに振り回されてしまう人も少なくありません。
ネガティブな気持ちを持つことはとても自然なことで、それ自体が悪いというわけではないです。
しかし、そうしたネガティブな気持ちによって自分が思うように動けなくなってしまうのであれば、そうならないように変えていく必要があります。
ネガティブな気持ちとの付き合い方を考える際には、
- どんな時にネガティブな気持ちが起きやすいか
- どういう風にネガティブな気持ちを表現するといいのか
- ネガティブな気持ちを落ち着かせる方法はあるか
このような観点で話をしていただくといいと思います。
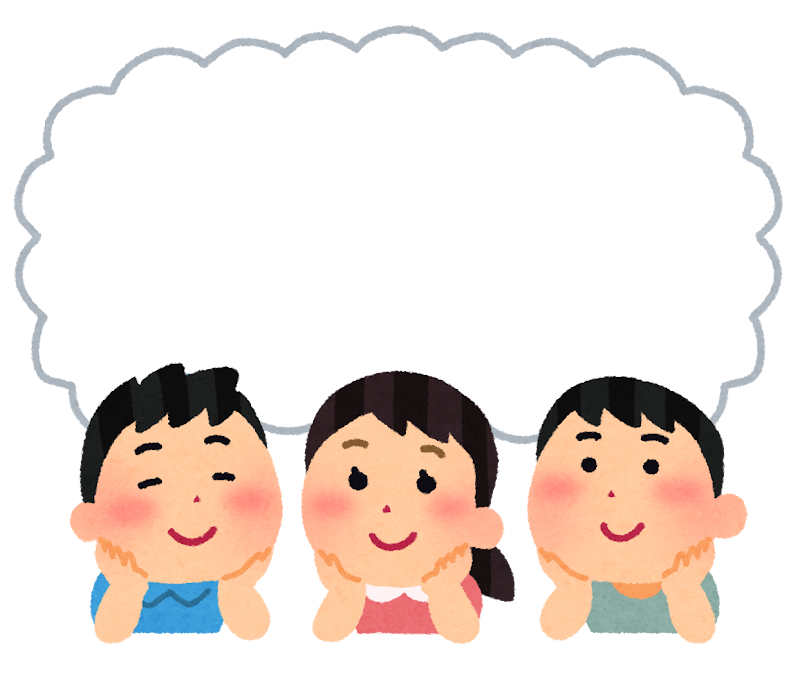
子ども達の中には、気持ちの表現方法がわからずにかんしゃくでしか表現できない子もいます。
かんしゃくを起こすと子ども自身だけではなく、それに付き合うママもへとへとに疲れてしまうのではないでしょうか。
そうならないためにも、かんしゃく以外の気持ちの表現方法を子ども達に伝えることがとても大切になります。
- 気持ちが昂ったら、お気に入りのぬいぐるみに囲まれて静かにする
- 自分が今どういう気持ちかを声に出してみる
- ノートなどに自分の状況を整理してみる
このようなさまざまな表現方法が考えられるので、子どもに合った表現方法を一緒に考えていくことが大切です。

ネガティブな気持ちの落ち着かせ方としては、ストレスコーピングの考え方がとても役立つと思います。
自分にとって「居心地がいい」や「落ち着く」、「楽しい」と思えるような活動があれば、ネガティブな気持ちが起きた時にもそうした活動をして気持ちを切り替えやすくなります。
人それぞれ、活動内容は異なると思うので、家族みんなで一緒に意見を出し合ってみるのも新しい観点が見つかるかもしれないのでおすすめです。
こうした本を活用して、気持ちの切り替えに役立ちそうなスイッチを探してみるのもいいかもしれません。
おわりに
今回は、子どものネガティブな気持ちに対してできることについてお話ししていきました。
大人になると忘れてしまいがちですが、私自身も子どもの頃はささいなことで一喜一憂していました。
友達に無視されたような気がする、失敗したのをみんなに見られた、やりたかった委員会に入れなかった。
こうした今でこそ「それぐらいで…」と思えるようなことも、当時の自分にとってはとても大きなものでした。
大人になる過程の中で、さまざまな経験を積み重ねて「これぐらい」の幅が広がっていったように感じます。
ママ達の中にも似たような感覚を持たれる方もいるかもしれません。
子ども達が「これぐらい」と思えるようになるためには、経験の積み重ねも大事ですがそれ以上に一緒に過ごす人の考え方によっても左右されます。
ネガティブな気持ちに対して、周囲がどんな反応を見せるかによって子どもの考え方も変わってくるので、ママ達自身も自分のネガティブな気持ちとうまく付き合う方法を見つけていけるといいのではないでしょうか。
今回も読んでいただきありがとうございました。







