「いい子」すぎる子どもが心配なときに親ができる声かけと安心の支え方

日頃、私たちは社会で生きていくために和を乱さないように協調性が求められます。
少しでも周囲と違った言動をすると、
- 「あの人は空気が読めない」
- 「自己中過ぎてついていけない」
- 「みんなと違うなんて変」
といった反応をされてしまうため、大人でも気を使って生活しているのではないでしょうか。
こうした社会の中、たとえ心の中では「めんどくさい」と思っていても周囲の空気を読んで生活することはとても自然な流れのように感じます。
そこで今回は、子どもが空気を読んで「いい子」となるのは果たしていいことなのかについてお話ししていきます。
Contents
そもそも空気を読んでしまうのはなぜ?
子どもたちが学校や家庭で怖いと感じることは、自分の存在が認められないことです。
「少しでもみんなと違うことをしたら仲間はずれにされるのではないか」
こうした不安がすべての子ども達には少なからずあると思います。
子ども達が空気を読む背景には、
- 同調圧力
- 自信のなさ
- 守らなければならないルールの多さ
- 心の居場所探し
こういったことが考えられます。

①同調圧力
同調圧力とは、集団における意見や行動において、多数派に合わせるようにするための無言の圧力のことを言います。
特に、学校生活で子ども達はこの同調圧力を感じることが多いと思います。
「仲間はずれになりたくない」
こうした思いから周囲の空気を読んで行動する機会が増えてきます。
友達が傷つかないように自分の気持ちを表現することが難しく感じてしまい、
「自分の気持ちを言わないで我慢して相手に合わせた方が楽」
といった考えになってしまう子も少なくありません。
コロナ禍や少子化の影響で、コミュニケーション力がうまく身に付けられなかった子ども達が増えたのも要因の一つかもしれません。

②自信のなさ
子ども達が空気を読んで過ごすのは、もしかしたら自分の判断に自信が持てないことも影響しているかもしれません、
「間違ったことをして怒られるぐらいなら、みんなと同じことをした方が安心」
こうした気持ちが隠されていることもあります。
自信のなさから自分のことを大切に思えず、自分の気持ちをないがしろにしてしまうことも少なくありません。
自信のなさが長く続くと、挫折体験から立ち直る力が弱くなったり将来に対して希望を持てなくなったりしてしまう危険性もあります。

③ルールの多さ
子ども達は、普段の生活の中で「あれはダメ」「これもダメ」といろんなことを禁止されながら生活をしています。
もちろん社会で生きていくために、ルールはとても大切な役割を担っています。
しかし、中には過剰なルール設定となっているものもあるのではないでしょうか。
- 公園では大きな声を出して遊んではいけない
- 公園の中でボール遊びは禁止
子ども達がのびのびと遊べるはずの公園でこのようなルールがあると、できることも限られてしまいます。
子ども達が自由に過ごしたいと思っていても、「ダメ」と禁止されるなら最初から考えないようにしようと諦めてしまうことにもつながってしまいます。
また、ルールを守りさえすれば周囲から浮くことがなくて安心という気持ちもあるため、どんなに過剰なルールでも子ども達は必死に守ります。

④心の居場所探し
人は誰かから認められることによって、
「自分は大丈夫」
と安心して気持ちが安定していきます。
子ども達も同じような思いを抱えていますが、学校生活であまりにもストレスが多かったり誰も自分の話を聞いてくれないと感じていたりする子がとても多いです。
「自分の居場所はここだ」
そう断言できるような場所が、今の子ども達にはとても少なくなっています。
周りを見てもみんなが何だか忙しそうにしていると、自分の話を聞いてもらえそうにないと諦めてしまう子もいるかもしれません。
社会全体が余裕のない状態が続くと、大人だけではなく子どもにとってもいい影響はないと思います。

では、こうして空気を読み続けてストレスが溜まってしまった子どもにはどんな影響があるのでしょうか。
空気の読み疲れで子どもはどうなる?
ストレスが溜まっても上手に発散できれば、大きな問題はありません。
しかし、最近の子ども達はストレスの発散があまり上手ではない子がとても多いです。
ストレスの発散がうまくいかず限界を迎えると
- ゲーム・ネット依存
- 不登校・ひきこもり
- 不安症
- 摂食障害
こうした様子が見られるかもしれません。
①ゲーム・ネット依存
上記でもお話ししたように、子ども達は心の居場所を求めて空気を読んでいます。
しかし、そうしていても安心できるような心の居場所が見つからなかったときに、心の拠り所になりやすいのはゲームやネットの世界です。
もちろんゲームやネットが楽しくてやっている子もいますが、中には居場所を求めてゲームやネットをやっている子がいることを知ってもらいたいです。
他にも外で思いっきり遊べる場所が減ったことも、子ども達がゲームやネットの世界に行きやすい要因だと思います。

子どものゲーム・ネット依存については
このページも参考にしてみてください。
②不登校・ひきこもり
学校の中で居場所を作れなかった子どもは、学校に行くことがとても苦痛に感じています。
そうした状況が続くと、学校に行きたいと思っていても体が動かなかったり、学校に行くことが嫌になったりしてしまいます。
もちろん居場所を作れなかったことだけが不登校の原因にはなりませんが、こうした要因も影響しているかもしれないと考えておけると対処の仕方も見つけやすいです。
居場所が作れないと感じてしまった子どもの中には、外に出ることに不安を感じることもあります。

不登校やひきこもりについては
このページも参考にしてみてください。
③不安症
自分に自信が持てず、周囲の空気を読んで生活している子どもは絶えず不安な気持ちを抱えています。
不安が表に出やすい子どもは、ママ達も対処がしやすいと思います。
しかし、中には不安が表に出にくい子どももいます。
なかなか不安を表に出せずに、耐えきれなくなってしまった時にママから離れがたい分離不安症や人前で話すことが不安になる社交不安症になってしまう危険性が高まります。

不安症や子どもの不安については
このページも参考にしてみてください。
④摂食障害
自分に自信がない子どもは、自分の容姿も好きになれないことが多いです。
そうした中で、少しやせたことを友達にほめられるなどすると、とても嬉しくもっとほめてほしい気持ちが高くなりやすいです。
最初のうちは適切な範囲でのダイエットだったものが、次第にエスカレートして摂食障害に移行してしまうケースも少なくありません。
やせた姿を認められたことだけがきっかけになるわけではありませんが、自分に自信が持てない子がほめられたことを過剰に受け取ってしまう危険性があることを知ってもらえるといいと思います。

摂食障害については
このページも参考にしてみてください。
では、こうした子どもの姿が見られたらご家庭ではどのように対応すればいいのでしょうか。
子どものためにご家庭でできること
子どもが周囲の空気を読んで疲れすぎないようにご家庭では、
- 子どもの自己肯定感を高める
- 子どもの話に耳を傾ける
- 子どもの環境を振り返る
- 親の生活にもゆとりを作る
この4点を意識していただくのがいいと思います。
①子どもの自己肯定感を高める
子ども達は自信のなさから空気を読んで、周囲に合わせようとして疲れすぎてしまう危険性があることを上記でお話ししていきました。
なかなか子ども自身では、自分のいいところには気づきにくいものです。
そこでママ達には、子ども自身が意識していないような子どものいいところを積極的に子ども達に伝えてほしいです。
- 思うように至らなかった結果でも、それまでに頑張った過程を認める
- たいしたことないと思ってしまうようなことでも、できたことを小さな達成感につなげる
こうした日々の積み重ねが子どもの自己肯定感を高めるのにとても効果的です。

②子どもの話に耳を傾ける
自分に自信が持てず、不安を抱えている子ども達は誰かに自分の気持ちを聞いてもらうことがとても苦手です。
「自分なんかの話を聞いてもつまらないだろうな」
「忙しそうだから迷惑をかけるのはよくないかもしれない」
こんな風にして自分の中でため込んでしまうことがよくあります。
根掘り葉掘りと聞き出そうとする必要はありませんが、子どもの様子が普段と違うと感じた時には、
「いつでも話を聞くからね」
というメッセージを送っていただくことをおすすめします。
低学年などの場合には、軽いスキンシップなども取り入れるとより一層効果的です。
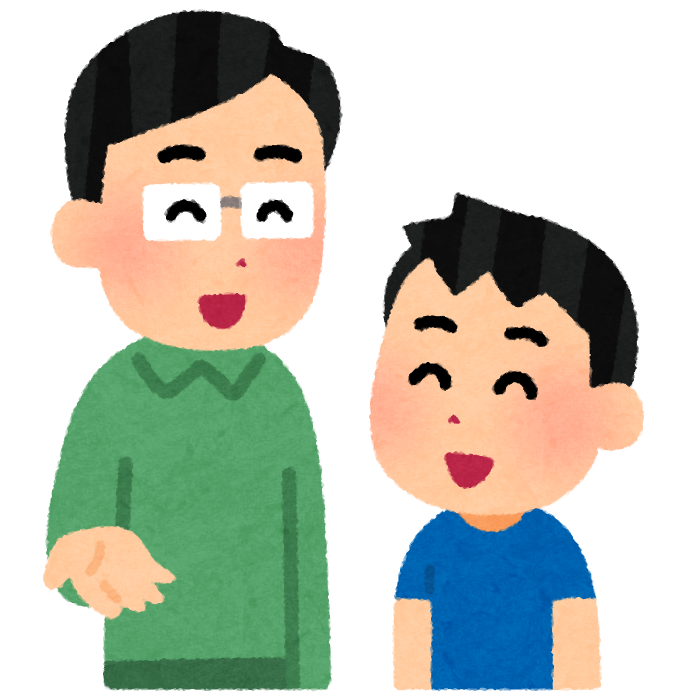
③子どもの環境を振り返る
現代社会では、大人だけでなく子どもも忙しくて疲れ果てていることも少なくありません。
「部活や習い事で予定が詰まっていてなかなか休めない」
「習い事は好きなんだけど、コーチが厳しくて辛くなってきた」
こうした声を子ども達から聞くこともあります。
習い事をすべて辞める必要があるというわけではありませんが、子ども自身が今の状況に疲れ果てていないかということを振り返ることも時には必要かもしれません。

④親の生活にもゆとりを作る
ママ達が忙しそうに動いているのを子ども達はよく見ています。
「これ以上ママに負担をかけたくない」
という思いを抱えている子どもはとても多いです。
大人でも忙しそうにしている人に声をかけることはとても勇気がいることだと思います。
なかなか難しいことだとは思いますが、親自身が生活にゆとりが作れると子ども達も安心して過ごせます。
家族みんなで協力しながらそれぞれがゆとりを作れるように生活ができると、家族全体に余裕がうまれてくるのではないでしょうか。

おわりに
今回は、子どもが空気を読んでいい子になることが果たしていいことなのかについてお話ししていきました。
子どもが空気を読んで生活することは、とても自然なことでそれ自体が悪いことではありません。
周囲とうまくやっていくために、協調して生活することは社会で生きていくために必要なスキルでもあります。
しかし、中には過剰に空気を読み過ぎて疲れてしまう子どももいることを知ってほしくて今回のテーマに選びました。
「子どもがいい子で安心」
そう思える子でも、いっぱいいっぱいの状態で生活しているかもしれません。
そんな時に、今回のお話を思い出してもらえたら嬉しいです。
今回も読んでいただきありがとうございました。







