子どもの困った行動に効果的な親の関わり方とペアレンティングの実践法

SCとして相談を受ける中で、メインとなる相談内容はやはり子どものお家の中での困った行動です。
- 片付けがまったくできない
- ずっとゲームで遊んでいる
- 宿題をなかなかやらない
- 思い通りにならないとかんしゃくを起こす
こうした子どもの困った行動に頭を悩ませているケースは今までにも数多くありました。
こんな風に打ち明けてくれたママも少なくありません。
そこで今回は、子どもの困った行動を減らすために親の行動を変えていくペアレンティングについてお話していきます。
Contents
ペアレンティングってそもそもなんだろう?
ペアレンティングは子育てという意味を持つ言葉です。
なので、普段ママたちが子どもたちに行っているすべての行為がペアレンティングと言えます。
今回お話しするのは、発達障害などの特性がある子どもに対して行う療育的な内容を盛り込んだペアレンティングです。
- 子どもが自分で判断できるように促す
- 親自身の気持ちのコントロールが大切
- 子どもの心ではなく行動に働きかける
- まずは親自身の行動を変える

こうしたポイントを踏まえてご家庭内での対応を変えてみることで、子どもの行動が少しずつ変わっていきます。
ペアレンティングではどんなことをすればいいの?
子どもの行動に対して普段ママたちはどんな反応をしていますか?
今回のペアレンティングでは、子どもの行動に対して
- ほめる
- 無視する
- 罰を与える
この3つを使い分けることがポイントです!
- やってほしい行動をした時
- やってほしくはないが、まあ許せるかなという行動をした時
- 許せないレベルのやってほしくない行動をした時
子どもの行動をこうしたママたちの基準と照らし合わせて、反応を使い分けていきます。

では、具体的に子どものどんな行動に対して、どのように実践していけばいいのでしょうか。
子どもの困った行動への実践集
今回は、普段の相談の中でよくある
- 片付けられない
- ゲームがなかなかやめられない
- 時間通りに動けない
この3つの具体的な場面への対応の仕方について取り上げます。
①片付けられない子どもへの対応例
片付けが苦手で何度「片付けなさい」と声をかけても片付けられない。
こんな子どもの姿に悩まされているご家庭も多いのではないでしょうか。
- 学校からのプリントがランドセルの奥底から発掘された
- ランドセルをその辺に放り投げたままにしている
- 脱ぎ捨てた服を床に放置している
- あちこちに物を置くので必要なものをすぐに取り出せない
こうした声を相談の中ではよく聞きます。
子どもたちに片付けられない理由を聞いてみると
- 後で片付けようと思って忘れてしまった
- 片付ける場所がわかりにくい
- 物が多すぎて片付けられない
こんな答えが返ってきました。

- 親も一緒になって片付けを手伝う
- しまう場所をわかりやすくする
- 持ち物の量を減らす
「片付けなさい」の声かけだけでは、片付けが苦手な子どもはなかなか動きません。
「一緒に片付けてみよう」と片付けのきっかけを作って、どうしたら片付けやすくなるかを一緒に考えて手伝ってあげることで子どもも”片付けられた”という達成感が味わえます。

そうして片付けを手伝う中で、物をしまう場所をわかりやすくしてあげることによって、だんだんと手伝いがなくても一人で片付けられるようになっていきます。
しまう場所を決める際に大事なポイントは、
あまり細かくわけすぎない
ということです。
細かくしすぎると、その都度指示を出さなければならず、子どもも親も片付けが面倒になってしまうので、ある程度ざっくりとした分け方が重要です。

また、片付ける物が多すぎるとなかなか終わらなくて、片付けが嫌になってしまいます。
人それぞれ管理できるものの量には違いがあるため、子どもにとって管理しやすい量を考える必要があります。
- 教科書・ノートなどの学校で使うもの
- おもちゃ・ゲーム
- 洋服
- マンガ・本
- 習い事で使う道具 など
こうした持ち物の中で、量の調整ができるのはおもちゃ・ゲーム類、洋服、マンガ・本だと思います。

全部を減らす必要はありませんが、しまう場所を決めるのと合わせてどのぐらいの量がちょうどいいのかを話してみるのもおすすめです。
しまう場所には、写真やテープラーなどを使ってわかりやすく表示を付けるのもいいかもしれません。
②ゲームがやめられない子どもへの対応例
一度ゲームを始めてしまうと、いくら声をかけてもなかなかやめてくれない。
こんな子どもの姿を見たことはありませんか。
- 友達と一緒にゲームをしているので、付き合いを考えるとやめさせにくい
- 時間になって声をかけると、「このステージが終わってから」とズルズルと時間が延びてしまうことが多い
- 自分の部屋に持ち込んで、夜中もゲームをやっている。
こうした声を相談の中ではよく聞きます。
子どもたちにゲームをやめられない理由を聞いてみると、
- 友達と一緒にゲームをしているから、自分だけやめられない
- ステージが始まってしまうと途中でやめられない
- ミッションなどに切れ目がないので、やめ時がわからない
こんな答えが返ってきました。

- ゲームやスマホのルールを決める
- ルールが守れなかった時の罰をきちんと実行する
- ゲームやスマホ以外の活動を考える
ゲームやスマホのルールは決めているけど、子どもが一向に守らない。
こうしたパターンも多いのではないでしょうか。
最初のうちは守られていても、だんだんとルールがあるけど使われていない状態になってしまったというご家庭も少なくないと思います。
ルール設定の大事なポイントは、
- 子どもと一緒にどんなルールだったら守れるか考える
- ルールが守れなかった時の罰も一緒に考える
- 罰はその時の気分などで変わらないように、親もしっかりと守る
こうしたことが重要です。

年齢が上がるにつれて、子どもなりの考え方も出てきます。
今までは親が考えたルールでやってくれていたことも、だんだんと受け入れられなくなってしまうこともあります。
そうしたことも成長過程では必要なことではありますが、だからといってすべて子どもに任せきりにするということはできません。
話し合いを重ねて、お互いが折り合いをつけられるルールをその時々で考えていくことが大切です。
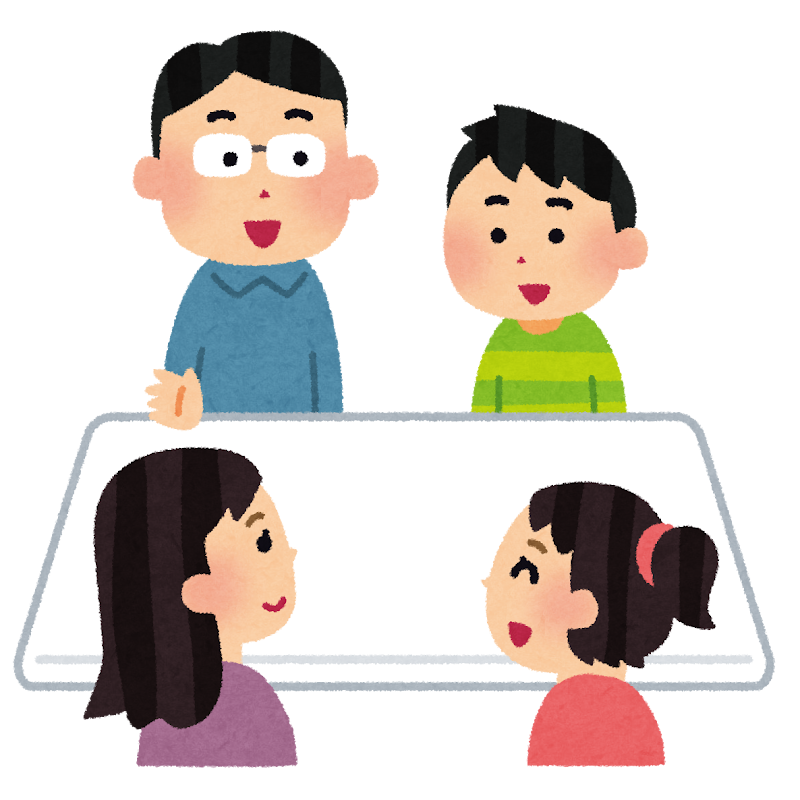
罰の内容も、あまりにも厳しいものだと子どもの反発を招くので、程よいラインを探る必要があります。
「このミッションだけはやらせて」と子どもからの要望があった際には、時間内であれば対応の必要はありませんが、時間を過ぎてしまったら罰の対象になります。
大事なことは、決して例外を作らないことです。
一度、例外を作ってしまうとそこからなし崩しにルールが守られなくなってしまう危険性が高まります。
「これぐらいならいいか・・・」
という判断が、大人もルールを守らないという子どもの考えにつながることを覚えておいてほしいです。

ゲームを無事にやめられたとしても、子どもからするとゲームの誘惑はなくなりません。
ゲーム以外でも、子ども自身が楽しめる活動があると、
「ゲームをやめても別の楽しみがあるからいいか」
とゲームをやめる気持ちにもつながります。
ルールを作ったり罰を与えたりしたけど、あまりにもゲームから離れられない。こうした子どもの姿が見られた時には、ゲーム依存になっているかもしれません。子どもがゲーム依存かもしれないと感じた時に、ご家庭でできることについてまとめてみました。
③時間通りに動けない子どもへの対応例
毎朝声をかけているのに一向に準備が進まず、学校によく遅刻してしまう。
こんな子どもの姿を見たことはありませんか。
- やることを都度指示しなければならないので、朝の余裕がない中イライラしてしまう
- 余裕を持って起こしても、のんびり準備をするので結局間に合わない
- 試しに自分でやらせてみても、焦ることがないからこちらが我慢できなくなってしまう
こうした声を相談の中ではよく聞きます。
子どもたちに時間通りに動けない理由を聞いてみると、
- やることがいっぱいで何から手を付けたらいいのかわからない
- ついTVを見てしまって、気が付いたら時間ギリギリになる
- 準備にどのぐらい時間がかかるかわからない
こんな答えが返ってきました。

- スケジュール表を作る
- TVなど気が散るものはつけない
- 事前に準備できるものは済ませておく
朝はやることが決まっているから、いちいち言わなくても覚えているでしょ。
こんな風に考える方も多いのではないでしょうか。
子どもたちはやることはわかっていても、何をどのタイミングでやったら時間通りにできるのかまではわかっていないことがほとんどです。
大人は、さまざまな経験から時間を逆算して考えられるようになってきますが、まだまだ子どもだとその経験が少ないためタイミングが掴めません。
そのため、子どもが確認しやすい位置に何時に何をするのかというスケジュール表を作って貼っておくと自分で確認できるのでおすすめです。
こうしたグッズを活用して、視覚的にわかりやすいスケジュール表を作ってみてもいいかもしれません。

スケジュール表を作って、いくら時間に余裕を持たせようと思っても、準備する量が多かったら結局は時間ギリギリになってしまいます。
そのため、学校の準備など前もって済ませられるものは前日に済ませておけるようにしておくと、子どもも慌てずに朝の準備ができます。
意外と「着ていく服が決まらない」という理由で、遅刻しがちな女の子も多いので、前日に明日着ていく服を決めておくと安心です。

子どもがスケジュール表を見ながら準備をしようと思っても、TVで気になる情報が流れてきたら意識がそちらに向いてしまいます。
特に、ADHDなどの注意がそれやすい子どもだと、いろいろな情報が入ってきてしまうTVは行動を妨げるものとなりやすいです。
習慣で朝起きたらTVを付けている、というご家庭も多いかとは思いますが、準備が終わるまではTVを消してみるのも子どもにとってはいいかもしれません。
こうしたタイマーを活用して、時間の感覚を意識できるように促してみるのもおすすめです。

今回、私がお話しした内容は、応用行動分析という考えに基づいて実践しています。
普段の相談の中でも、相談に来てくれた人におすすめする本が3冊あるので、よかったら参考にしてみてください。
この本は、 応用行動分析の考え方をわかりやすく解説していて、具体的な例を踏まえて対応についてもまとめてあります。
もう2冊は、セットでおすすめしている本です。
この2冊の本です。
子どもの困った行動の背景に発達障害がある場合、対応の仕方によっては困った行動が増えてしまうことがあります。
この2冊の本では、具体的な困った行動に対してどのように親が対応すればいいのかをわかりやすくまとめてあるため、すぐにでも家庭内で実践したいという方におすすめです。
おわりに
今回は、子どもの困った行動を減らすために親の行動を変えていくペアレンティングについてお話していきました。
ペアレンティングには、特別なことや難しい対応は必要としていません。
しかし、毎日同じように実践していく根気強さは必要になるので、親の気持ちのコントロールが重要になります。
あまりにも最初から完璧にやろうとすると挫折につながりやすいため、
まずは1つの行動から始めてみよう
という気持ちでやってみていただくのが、長く続ける秘訣です。
一人だけでやっているとくじけてしまうかもしれないので、
- パパ・ママで一緒に相談しながら実践してみる
- SCに相談して、実践状況を振り返る
このように、相談したり一緒に振り返ったりしながら実践できるような体制を整えてみてください。
お困りのことがありましたら、コメントをいただけましたらお答えいたします。
今回も読んでいただきありがとうございました。












