「失敗したら嫌だな」
「友達ができなかったらどうしよう」
「給食がなんだか苦手」
こんな不安、お子さんから聞いたことありませんか?
私のところに相談に来てくれたお子さんの中にも、このような不安な気持ちを打ち明けてくれる子が時々います。
今回は、不安な気持ちになったときにどうしたらいいかについてお話ししていきます。
そもそも、不安って何?
不安とは「嬉しい」や「楽しい」、「悲しい」のような、いろんな気持ちの中の一つです。
特別な気持ちというわけではなく、人なら誰しもが持っている当たり前のものです。
でも、不安の気持ちが強すぎると、好きなことを楽しめない、何かをする意欲が湧かない、など心地よい状態とは言えなくなります。
不安が強い子どもは、「不安」な気持ちを持ってはいけない気持ちだと考えている子も多いので、不安な気持ちになることは悪くないということを伝えてあげるのも大事になってきます。
また、低学年のお子さんだと自分の気持ちに名前をつけるのがまだ難しいので、ママたちが「不安なのね」と気持ちに名前を付けてもらえると少し安心する、という場合もあります。
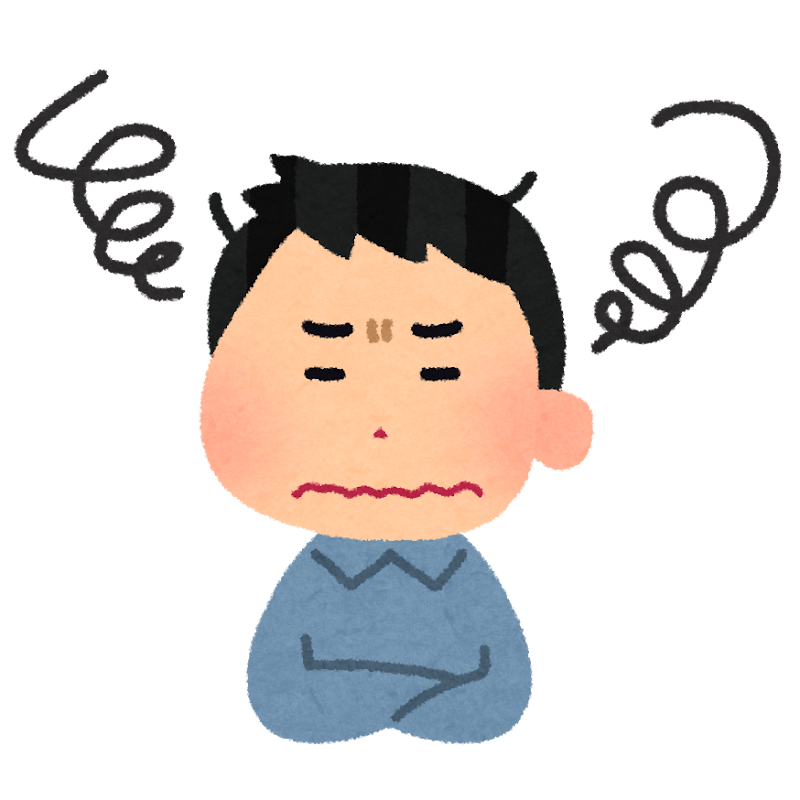
では、不安な気持ちにはどう向き合っていけばいいのでしょうか。
不安な気持ちはどうしたらいいの?
不安な気持ちになると、「もうだめだ」や「どうせ自分なんて」という考えが浮かぶと思います。
そこから、冷や汗をかく、体が強張る、お腹が痛くなる、などのような体の変化が起こることもあります。
そうした体の変化が起こると、その場から逃げ出す、トイレに籠る、うずくまって固まる、などの行動が起きます。
不安、という気持ちから派生して、私たちの頭や体はさまざまな動きをしてしまうのです。
なので、気持ちからいろんな考えが浮かび、体に変化が起きて、何か行動している、ということに気づくことが、不安な気持ちに対応するための第一歩になります。

心と体と行動は全部つながっている!
まずは、どんなパターンがあるのか探してみよう。
不安な気持ちが起こるパターンが見つかると、対処の仕方も探しやすくなると思います。
パターンを見つけたらどうするの?
子どもの中で、不安になりやすいパターンが見つかってきたら、それぞれの不安なパターンに点数をつけてみるのもいいと思います。
「給食の不安は40点」、「お友達とおしゃべりするのは60点」、「教室に入るのは90点」など、点数がつくことによって、それぞれの不安の強さが違うことに気づくはずです。
その中で、不安だったけど頑張れたという場面と、不安が強くてダメだったという場面の点数を比べてみてください。
そうすると、何点までの不安なら頑張れそうという目安が子どもの中で作れるのではないでしょうか。
新しい不安が出てきても、自分の今までの経験と比較することでどのぐらいの状態か、という目安が付けられて取り組みやすくなると思います。

不安を落ち着かせるには?
では、いざ不安な気持ちになってしまい、体にさまざまな変化が起こってきたら、どうしたらいいでしょうか。
大事なのは、体をリラックスさせることです。
お子さんでも簡単にできるやり方は、
- 深呼吸
- 手のひらをギュッと握って、ゆっくり開く
の2つです。
深呼吸
不安な気持ちになると、自然と呼吸が浅く早くなりがちです。
なので、深呼吸を数回するだけでも変わっていきます。
年齢が低いうちはママと一緒に深呼吸してみるのもいいかもしれません。
息を吸う時に、お腹を膨らませる腹式呼吸だとより効果的です。手のひらをお腹に当てて、息を吸った時に膨らんでいることを確認しながらやるとやりやすいです。
低学年の子どもの場合には、ママが先に深呼吸をしてママのお腹を触らせてあげるなどするとイメージしやすいと思います。

手のひらをギュッとする
不安な気持ちになると、体が強張りやすくなります。
なので、意識して手のひらをギュッとさせて、ゆっくりと開くことにより、自然と体の強張りがほぐれやすくなります。
不安だな、と感じたら、手のひらに意識を集中させてゆっくりグーパーする、と覚えておくといいと思います。
不安な気持ちが強いと、無意識に体が強張るので、自分の体が強張っていることを意識して感じ取れるようになってくると、体の緊張をほぐそうと意識して取り組めるようになっていきます。
自分の体の状態を知るということが、自然とできるようになってくると、不安な気持ちをコントロールする力も身に付きやすいのではないでしょうか。

おわりに
今回は、不安な気持ちになったときどうしたらいいかについてお話ししていきました。
このやり方は、大人でも使えるものなので、ぜひママたちも活用していただきたいです。
子ども自身が、今の自分の状態を整理するのはとても大事なことです。
1人では難しいかもしれないので、その時にはママと一緒にやってもらえたらいいのではないでしょうか。
なかなか、うまくいかない時には、スクールカウンセラーなどの専門家にお話を聞いてみるのもいいと思います。
今回も読んでいただきありがとうございました。
また次回も読んでもらえると嬉しいです。








