心配性な子どもが安心できる!不安を和らげる家庭での関わり方3選

小学生の相談を受ける中で、よくあるものの中に
「うちの子はとても心配性で、ささいなことでも不安になってしまう」
という相談があります。
不安や心配な気持ちがあることは悪いことではありませんが、あまりにもその気持ちが強すぎると何かをすることが難しくなってしまいます。
そこで、今回は子どもが不安を感じている時に親ができることについてお話ししていきます。
Contents
子どもはどんな時に不安を感じやすい?
普段の相談の中で、子どもが学校の中で不安を感じる場面でよく出てくるのは
- 登校や教室に入る
- 給食の時間
- 運動会や遠足などの行事
- 苦手な授業
- 友達との関係
が多いです。
登校や教室に入るタイミング
進学や進級など、新しい環境になった時期にこの不安がよく出てきます。
- 「クラスに仲良しの子がいなかった」
- 「新しい担任の先生が怖そう」
こうした不安の訴えもお互いのことを知らないため、いろいろな想像を膨らませてしまいやすいことが理由として考えられます。
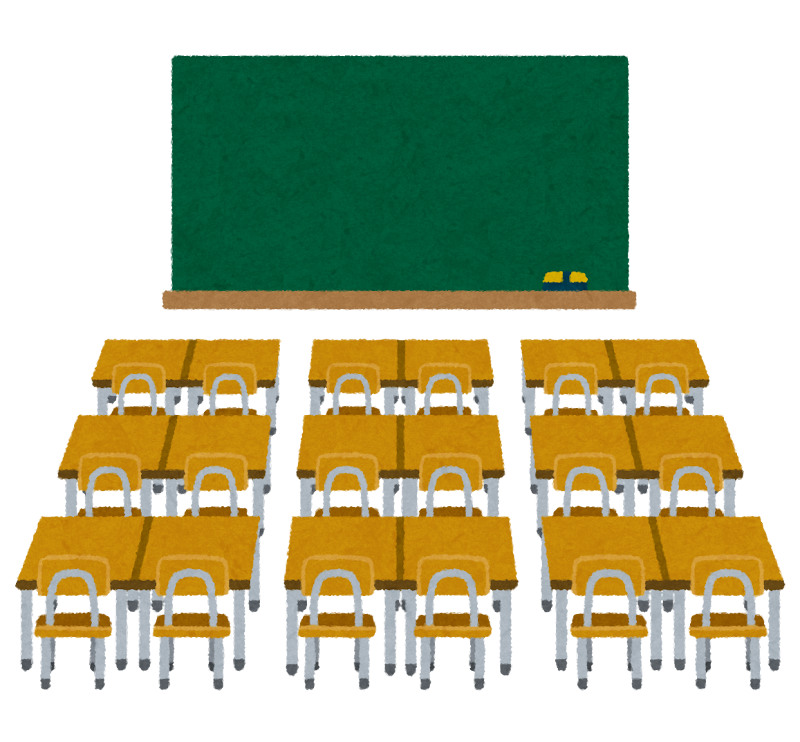
給食の時間
給食の時間は、学校で不安を感じる場面の中で一番多いものではないでしょうか。
- 「苦手なものが出て食べたくない」
- 「給食を食べたら気持ち悪くなって吐いちゃいそう」
- 「食べる時間が短くて食べきれないかも」
こんな言葉がよく子ども達からは出てきます。
最近の給食では、以前よりも完食指導は厳しくなくなってきました。
それでも、一口は食べられるようにと指導されることが多いので、好き嫌いの多い子や少食の子からすると給食の時間はとても不安な気持ちになりやすいです。
給食の中には家庭ではなかなか出てこないメニューもあるので、味の想像がつかなくて不安になるといったこともあるかもしれません。
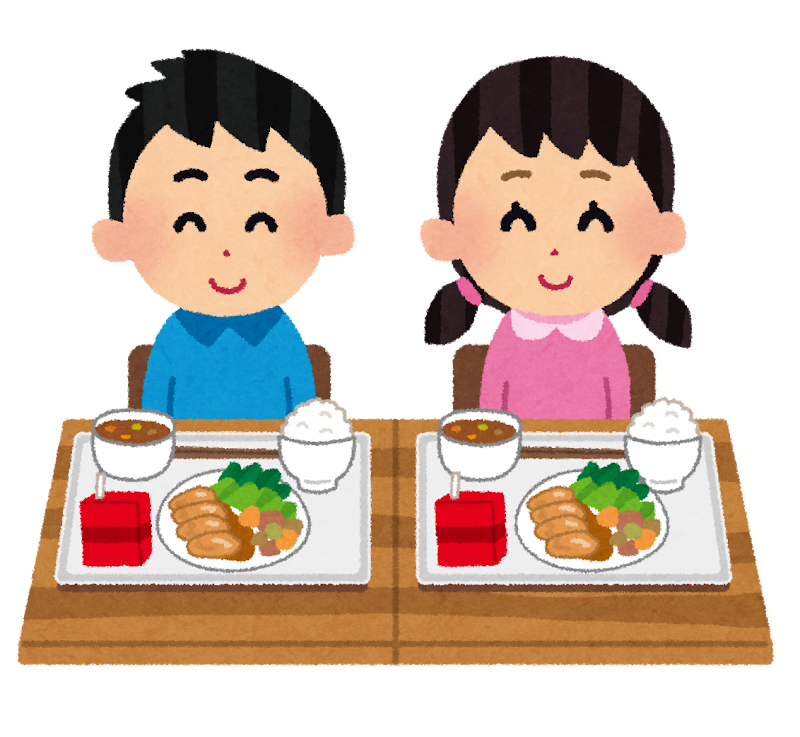
運動会などの学校行事
学校の中では、普段の授業だけではなく運動会や遠足など特別な行事が行われることがあります。
- 「運動会でちゃんとできるか心配」
- 「仲が良くないこと遠足の班が一緒になっちゃった」
- 「全員リレーでみんなの足を引っ張るかも」
運動会や遠足の時には、普段とはまた違った不安の言葉が子ども達からは出てきます。
特に、予定が変わることや環境が変わることに不安を感じる子が、こうした学校行事への不安を訴えることが多いです。

苦手な授業
学校では、さまざまな授業をまんべんなく受けることになるため、苦手な教科がある子どもからするととても不安を感じやすいです。
- 「わからないのに先生にさされたらどうしよう」
- 「跳び箱が跳べないのは自分だけかもしれない」
- 「みんなの前でリコーダーの発表なんてできない」
苦手な授業を受けるだけでも不安な気持ちになるのに、そこにみんなの前での発表などが加わり不安が倍増してしまったという子どもも少なくありません。

友達との関係
友達との関係での不安も子ども達からの訴えとしてよく見られます。
- 「今日、余計なこと言っちゃったかもしれない」
- 「友達から無視されたような気がする」
- 「クラスで仲の良い子ができない」
こんな不安の声が寄せられます。
特に、3,4年生ぐらいの女の子で少しずつ友達のグループを作り始めてきた時期の子ども達からこうした相談が増えてきます。

子どもが不安を感じた時に、学校に要望を出すことによって不安な状況が改善されることがあります。学校に要望を出したいけど、どんな風に出せばいいかわからないときに参考にしてみてください。
どうして不安な気持ちになってしまうの?
不安な気持ちは、以前に失敗してしまった出来事や恐怖を感じた出来事などに関連した場面で起こりやすいものです。
不安な気持ちがあることによって、失敗を防いだり恐怖から逃れられたりと自分の身を守ることができるので、不安な気持ちがあることが悪いこととは限りません。
しかし、そうした不安な気持ちが強すぎるあまりに、気持ちが落ち込んだり動けなくなったりしてしまうということがあるようでしたら不安を和らげる必要があります。
もしかしたら、不安を強く感じてしまう背景には
- マイナス思考
- すべき思考
- レッテル貼り
という考え方のクセみたいなものが影響しているかもしれません。

マイナス思考
子どもの中には、すべての出来事をマイナスに考えてしまう子がいます。
- 「私のことが嫌いだから…」
- 「僕がへたくそだから…」
のように、事実ではないけど、子ども自身がマイナスに考えてしまうことで不安が増してしまうことがあります。

すべき思考
自分に厳しく、真面目な子どもにこうした考えが強い子がいます。
- 「~すべき」
- 「~でなければならない」
という考えが強く、そのルールを自分が守れそうにないとなった時に不安が増してしまうことがあります。
レッテル貼り
人や物事に対して、極端なイメージのレッテルを貼って事実と思い込んでしまう子どもがいます。
- 「あの先生はいつも怒っているから、今日も絶対怒るはず」
- 「あの子は性格が悪いから、私の悪口を言っているはず」
一度貼ってしまったレッテルは、なかなか取り除くことができません。
こうした自分で貼ったレッテルに苦しめられて不安が増してしまうことがあります。

子どもの不安の裏には考え方のクセがあるかもしれない!
考え方のクセに気づいて、自分の気持ちを整えよう!
では、こうした不安に対してどのように対処していけばいいのでしょうか。
子どもの不安に親ができること3選
子どもが不安を感じて苦しんでいる姿を見ていると、居ても立っても居られないママが多いのではないでしょうか。
子どもが不安を感じている時には、ご家庭で
- 不安な気持ちを吐き出せるように聞く
- 不安な状況を整理する
- 不安から切り離されるリフレッシュ方法を考える
といったことを実践していただけるといいのではないでしょうか。
①不安な気持ちを聞く
これはほとんどのママが実践していただいている方法ではないでしょうか。
大人でもそうですが、不安な気持ちを誰かに聞いてもらうだけで不安が和らぐことがあります。
子どもも今自分が抱えている不安をママと共有できると、不安が和らぐことがあります。
不安な気持ちを聞く際には、まずはアドバイスなどはしないでそのままの気持ちを聞いてもらえると、子どもの不安が和らぐかもしれません。
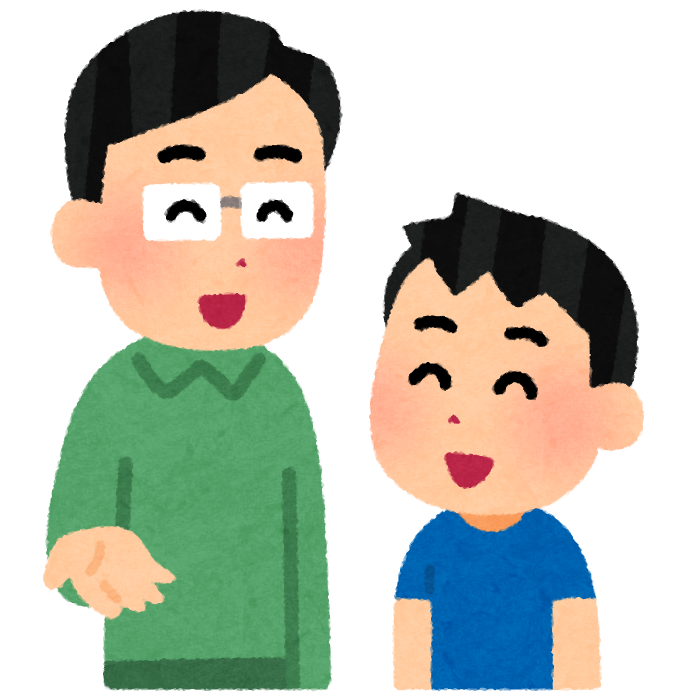
不安な気持ちを言葉にするのが苦手な子やネガティブな気持ちを出すとネガティブな状況から抜け出せないと感じている子にとっては、話をすることがストレスになるので無理に聞き出そうとしなくても大丈夫です。
そんな時には、
こんな本を読んでもらったり、
一緒に楽しくゲームをしたりするだけでも、気持ちは変わります。
②不安な状況を整理する
不安な気持ちを聞くだけでは不安が解消されないこともあるかもしれません。
そうした時には、
どんな時に、どのような不安を感じるのか
といったことを具体的に整理していただくことも効果的です。
その際に、不安な気持ちを点数で表すなどもしてもらうと、さまざまな場面の不安を比較することもできるので子どもにとっての不安の目安が作りやすくなります。
私自身は普段の相談の中で、
この本を使って子どもと不安な状況を整理しています。
本の場面や考え方を見せながら、自分の気持ちに近いものを選んでもらうなどして気持ちの整理をする方法を一緒に練習できるので、ご家庭でも活用できます。
③リフレッシュ方法を考える
いろいろと気持ちを整理したり、不安な状況を整理したりしてもどうしても煮詰まってしまう時もあるかもしれません。
そうした時に、自分の気持ちが上がるリフレッシュの方法がいくつかあると、不安に振り回されずに済むのではないでしょうか。
学年が上がってくると自分の好きがはっきりとしてきて、自分に合ったリフレッシュ方法を見つけることができるようになってきます。
低学年のうちは、どうしても気持ちの切り替えが難しいところがあるので、親子でどんな風にするとリフレッシュがうまくいきそうかを考えていただくのもいいと思います。
上記で紹介した本の中にも、リフレッシュ方法がいくつか載っているのでそうしたものを参考にしていただくのもいいかもしれません。
それ以外にも、ママやパパが普段やっているリフレッシュ方法を一緒にやってみる、ということもおすすめです。

おわりに
今回は、子どもが不安を感じた時に親ができることについておはなししていきました。
不安の内容を学校でのことをメインとしてお話ししていきましたが、実際には家庭の中での不安も数多く寄せられます。
今回の対処法はそうした家庭の中での不安についても使えるので、ぜひ試しに実践していただけるといいのではないでしょうか。
今回も読んでいただきありがとうございました。







