スクールカウンセラーとして勤務している中で、先生たちから
- 子どもが掃除中にふざけていて困る
- クラスメイトにちょっかいをかけてしまうのを止めさせたい
- 何度注意をしても同じ失敗を繰り返す
のような話を聞くことがあります。
このような状況は学校の中だけではなく、家庭の中でも起こっているのではないでしょうか。
普段の生活の中でも子ども達の行動を見ていて、
「何でこんなことするの?」
と思うことがよくあるかと思います。
そこで、今回は子どもの行動に着目して支援につなげていく応用行動分析という理論についてお話ししていきます。
そもそも応用行動分析って何?
心理学の中には、「心」を理解するために「行動」に着目して「心」を理解しようとする行動分析という考え方があります。
「心」を見ることはできませんが、「行動」なら見て何をしているのかがわかります。
また、「行動」ならば誰が見てもわかりやすいため、子どもの状態を共有しやすくなるのもいいところだと思います。
応用行動分析では、【子どもの行動】や、【行動のきっかけ】と【行動の結果】に注目することで、子どもに対する理解を深めることを目的としています。
たとえば、日常のお手伝いの場面を見てみると、「手伝ってほしいな」とママに声をかけられ、「子どもがお手伝いをした」結果、ママに「ありがとう」と言われたというようなことがよくあるのではないでしょうか。
これを応用行動分析的に考えると、
【きっかけ】
ママからの「手伝ってほしいな」という声かけ
【行動】
子どもがお手伝いをした
【結果】
ママから「ありがとう」と言われた
というような考え方になります。
人が何か行動を起こすのには、必ず何かしらのきっかけがあります。
たとえば「ママがたくさんの荷物を抱えているのに気づく」「お友達が泣いているのを見つけた」のようなきっかけが子どもの行動の裏にはあるのではないでしょうか。
子どもが行動を起こした結果、嬉しいことが起きたとなると繰り返しその行動をするようになります。
- 行動を維持するためには、何かしらのいいことが起こることが必要
- 何が行動の維持に影響しているのか、見極めることが大切
。 
応用行動分析の支援方法
応用行動分析の理論を使った支援を行うには
- 行動の「きっかけ」にアプローチする
- 行動の「結果」にアプローチする
の2つの観点が挙げられます。
今回はこの2つの観点から、
- 「してほしい行動」を「増やす」
- 「してほしくない行動」を「減らす」
のやり方についてそれぞれお話ししていきます。

「してほしい行動」を「増やす」にはどうしたらいいの?
子どものしてほしい行動を増やしたいときのやり方は、
- 行動の「きっかけ」を出してあげる
- 行動の「結果」に「いいこと」を示してあげる
の2つになります。
ご家庭では、
- お手伝いをしてほしい時に「手伝ってほしいな」と声をかける
- 自分のおもちゃを片付けてほしい時に「おもちゃを片付けて」と声をかけながら、おもちゃ箱を渡す
のようなやり方ができると思います。
大事なことは、「してほしい行動」のきっかけになりそうなものは何か、ということをその子に合わせたやり方を考えてあげることです。

- 行動に対して「ありがとう」や「上手にできたね」とほめられた
- お手伝いの結果、おいしいご飯が食べられた
のようなやり方ができると思います。

「してほしくない行動」を「減らす」にはどうしたらいいの?
子どものしてほしくない行動を減らしたいときのやり方は、
- 行動の「きっかけ」をなくす
- 行動の「結果」に「いいこと」をなくす
の2つになります。
してほしい行動を増やすときには「いいこと」を示してあげますが、してほしくない行動を減らすときには「いいこと」をなくして行動が起こる回数を減らすようにしていきます。
ご家庭では、
- おもちゃの取り合いにならないように、同じおもちゃを用意する
- 宿題中に遊ばないように、机の周りにはおもちゃなどを置かないようにする
のようなやり方ができると思います。
行動を起こすきっかけがなくなるだけでも、子ども達からするとしてほしくない行動を起こしにくくなります。
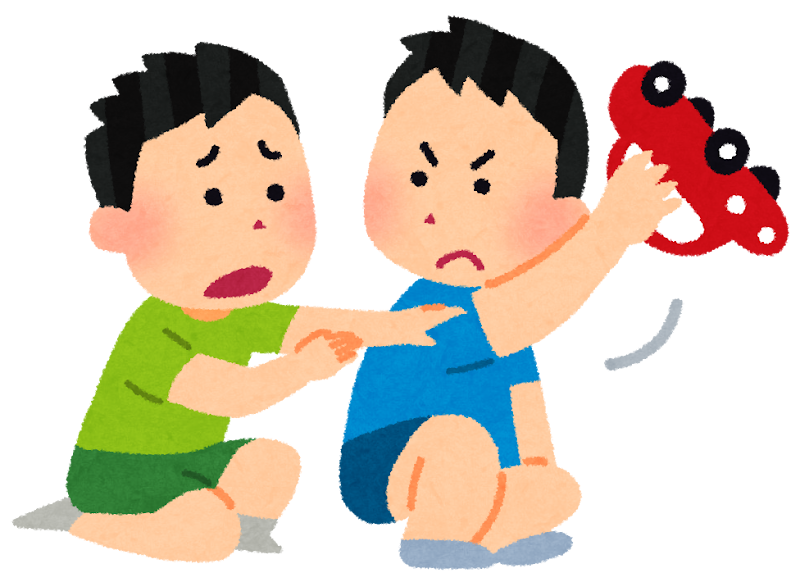
- 買い物中にお菓子を買ってほしいと駄々をこねるとお菓子を買ってもらえない
- おもちゃを取り合ったら、どちらにも渡さない
のようなやり方ができると思います。
また、「無理やり引っ張ってほしいおもちゃをとろうとする」などの行動が見られたときに、「貸して」「終わったらやらせて」とのような「してほしい行動」を身につけられるように促すやり方も効果的です。

行動のきっかけと結果に注目して、
増やしたい行動のアプローチの仕方を工夫しよう!
おわりに
今回は子どもの行動に着目する、応用行動分析についてお話ししていきました。
私自身、学生の頃に応用行動分析を使った療育機関で実習をしていたこともあり、応用行動分析は非常になじみ深い理論でもあります。
子ども自身の「できた」にアプローチできるのも応用行動分析ならではのやり方でもあるので、子どもの自信にもつながるのが一緒にやってきてとても嬉しかったのを今でも覚えています。
応用行動分析にはさまざまな技法があり、それらを使った療育を行っている機関もあるので、もし気になる方がいれば調べていただくのもいいと思います。
また、もっと応用行動分析のことを知りたいと思った方には、
のような本もおすすめです。
今回も読んでいただきありがとうございました。








