小学校の入学式も終わり、新しい生活にわくわくした気持ちでいっぱいの子どもも多いのではないでしょうか。
しかし、入学後新しい生活に馴染めずに
「学校に行きたくない」
と訴える子どもも少なからずいます。
そこで、今回は小学校入学後に登校を渋る子どもへの対処法についてお話ししていきます。
Contents
そもそも登校渋りって何?
登校渋りは文字で見ると何となくイメージができるかと思いますが、耳馴染みがなくどういう状態なのかわからない方もいるのではないでしょうか。
学校では、不登校のように「学校に行きたくない」「学校に行けない」という気持ちがあるものの、周囲の励ましなどでなんとか学校に行っている状態を登校渋りと言います。
ほとんどの場合、登校渋りの子どもは登校さえできればあとは学校で元気に過ごせてしまいます。
そのため、保護者や先生も「学校に来ちゃえば大丈夫なのだから…」と、なんとか休ませないようにあの手この手で登校につなげようとしているパターンが非常に多いです。
そうした状態がいつまで続くのかわからずに、疲弊してしまったママ達の相談を小学校ではよく受けます。
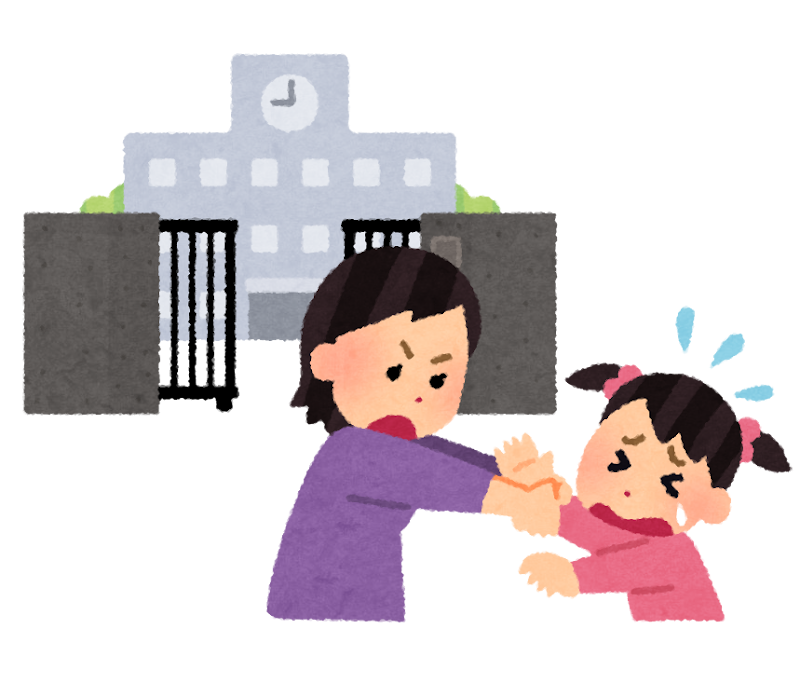
どうして子どもは登校を渋るの?
「学校に行きたくない」と訴えている子どもに対して、
- 「甘えているからそんな気持ちになる」
- 「社会に出たらそんなに簡単に休めない」
- 「わがままばかり言っていたら、この先社会で生きていけない」
のような考えを持つ大人は少なくないのではないでしょうか。
しかし、子ども達なりに学校に行きたくない理由はあります。
日頃、私が相談を受けている中でよく聞く理由で小学校1年生に多いものは、
- 母子分離不安
- 集団生活の苦手さ
- エネルギーの低下
の3つです。
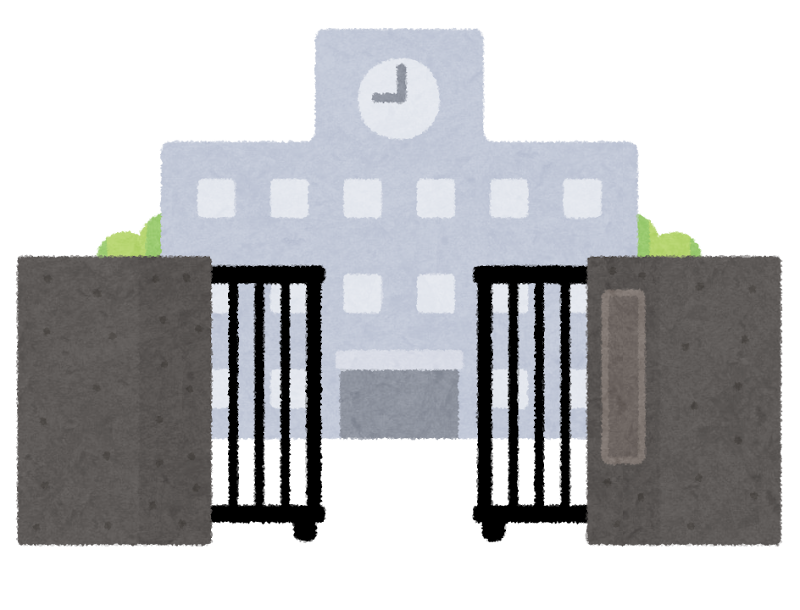
①母子分離不安
これは、低学年の子どもに多い理由で「ママから離れるのが不安」という気持ちが強くなってしまい、学校に行きたくない気持ちになってしまうことがあります。
特に低学年の子どもの場合、自分の気持ちを具体的に言葉で表現する力がまだ弱いので、さまざまな不安な気持ちを合わせて「ママから離れるのが不安」という表現をしていることも非常に多いです。
こうしたママから離れたくない、という子どもの姿が周囲の人から見ると「甘え」のように感じてしまうかもしれませんが、子どもなりの不安な気持ちを表現していると考えていただくといいかもしれません。

②集団生活の苦手さ
発達障害のような特性のある子どもの中には、
- 授業中に立ち歩く子や騒ぐ子
- 自分には関係なくても、叱られている声
- 給食の時間(完食指導への不安・短い食事時間の難しさ)
- 席替えや急な授業変更など、環境の変化が多い
- 慣れない初めての活動
- 保育園や幼稚園の時とは違う担任の先生の雰囲気
- 興味がない活動への参加が必須
- 学校のザワザワした雰囲気や、突然鳴るチャイムなどの音
のような些細なことが非常に気になってしまい、学校に行きたくない気持ちになってしまう子もいます。
もちろん、すべての子どもが上記のことを気にするわけではありませんが、こうしたことが気になってしまう子もいるんだと念頭に置くだけでも子どもの気持ちも変わってきます。
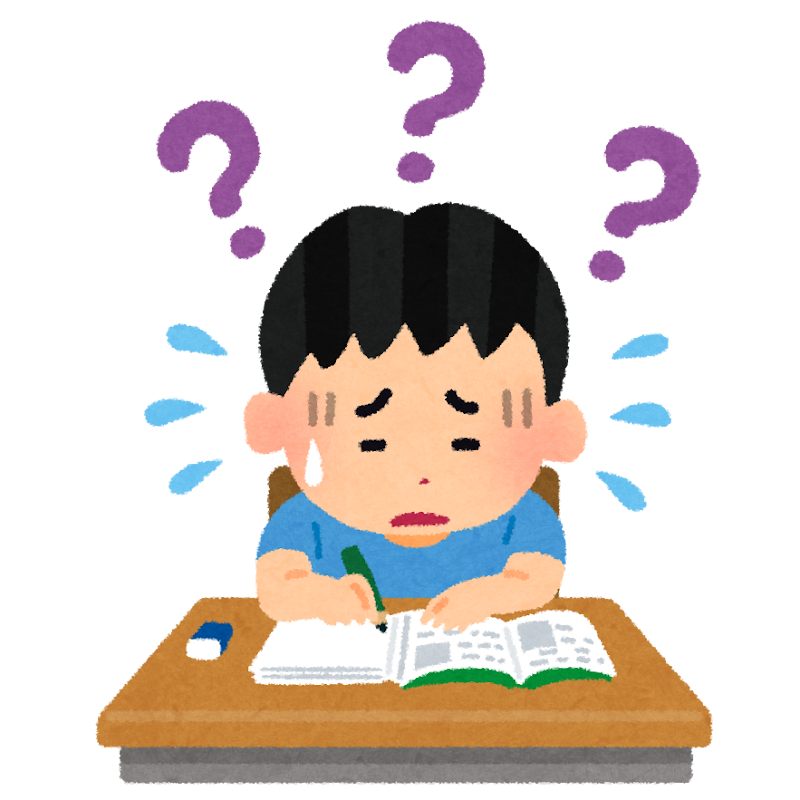
③エネルギーの低下
今までの相談の中から、登校渋りの原因として子どものエネルギーが低下していることが非常に多く挙げられてきました。
子ども達が学校生活を送るためには、かなりの量のエネルギーが必要になります。
まして、今までとは違う新しい環境での生活となると、それに必要なエネルギーを考えて不安になってしまい行きたくないと感じる子どもも少なくありません。
また、入学前はわくわくした気持ちでいっぱいの子どもも、入学後に学校生活が楽しいことばかりではないことに気づいてしまいます。
2年生以降に登校を渋ってしまうのも、そうした現実に直面してしまったことが原因として考えられます。
それ以外にも、
- 習い事が多くて、学校で頑張る気力が湧かない
- クラスの中に仲の良い友達がいない
のような立ち向かうためのエネルギーを溜めにくい時に、登校しぶりが起きる可能性が高くなります。

登校渋りの対処法 3選
これまでお話ししてきた登校渋りの要因に、ご家庭でできることは
- 子どもの話をじっくり聞く
- 子どもが安心できる環境づくり
- 信頼できる相談先を見つける
の3つです。
①子どもの話をじっくり聞く
登校渋りの時に子どもの話を聞くとなると、とことん原因を追究するように話を聞かねばならないと考えてしまう方も多いのではないでしょうか。
原因が何かを探るのはもちろん大切なことですが、それよりも大切なことは子どもの不安な気持ちに寄り添って一緒に解決法を考えるように話を聞いてあげることです。
登校渋りの子ども達はうまく言葉で表現できないさまざまな不安を抱えていることが非常に多いです。
そうした不安を「これぐらいで…」や「どうせ…」のような大人の価値観で決めつけずに、子どもの気持ちをそのまま受け止めてあげることが子ども達の安心感へとつながります。
実際に、私のところに登校渋りの子ども自身が話に来た時にも、その子自身の表現を使って状況を整理してあげたら少しずつ登校を渋る回数が減ってきたことがありました。
その場で解決策が見つからなくても、「いい案が出るまでいつでも一緒に作戦会議をしようね」と声をかけてあげるだけでも子ども達からすると安心できます。

②子どもが安心できる環境づくり
登校渋りの対応で、よく学校までママについてきてもらったり、授業中にもそばにいてもらったりすることがあります。
これは子どもを甘やかすためにやるものではなく、少しでも子どもにとって安心できる環境を作るための手段としてママの付き添いをお願いしています。
それ以外にも、最近の子ども達は小学校低学年のうちから習い事をたくさんしていることがよくあるため、習い事のスケジュール調整をしてもらうこともあります。
学校で頑張らなければ、と考えていても、そのための体力がなかったらやる気が出てきません。
- 習い事が多くて体力が続かない
- 学校でも家庭でも楽しいことが少なくてエネルギーが溜まらない
登校渋りの子どもには、このような状態になっている子が非常に多いです。
なので、ご家庭では休みの日にお出かけして楽しく過ごす、のような楽しい活動を増やすことを意識していただけるといいかもしれません。

③信頼できる相談先を見つける
②でもお話ししたように、登校渋りの対応で非常にママ達への負担が大きくなってしまうことがよくあります。
登校渋りの原因もはっきりすることが少ないため、先の見えない不安から疲弊してしまったママ達を相談の中でたくさん見てきました。
そうした時に、子どもの様子もよくわかっていて一緒に方針を考えてくれる相談相手が一人でも多くいると非常に心強いのではないでしょうか。
相談先としては、
- 担任の先生
- 学校のスクールカウンセラー
- 教育相談センター
- 児童相談所
などが選択肢として入ってくると思います。
上記の選択肢に入っていなくても、ママ達自身がこの人に相談したら気持ちが落ち着く、と思える相手であればどんな人でもOKです。

おわりに
今回は登校渋りの時にできる対処法について3つお話ししていきました。
今までスクールカウンセラーとして相談を受けてきて、かかる時間は個人差がありますが、どの子も少しずつ登校渋りが減ってきていることがほとんどでした。
段階の踏み方も子どもの様子に合わせて考えていき、時には子ども自身にもどのような段階がいいかを一緒に考えてもらったこともあります。
子ども自身で段階を考えられると、納得感も得られやすく自分でやらなければという気持ちにつながりやすいので、そうした作戦会議も登校渋りの子どもにはおすすめです
ご家庭の中だけで話をするのは難しい…
そんな時には、ぜひ最寄りのスクールカウンセラーに相談していただけるといいのではないでしょうか。
今回も読んでいただきありがとうございました。








