「できない!」と感じる子どもを支えるスモールステップの取り入れ方

普段の相談の中で、
- 子どもに学校の準備を一人でさせたいが、なかなかできない
- 宿題を自分からやらなくて困っている
- 部屋の片づけなどをいくら言ってもやらない
のような話を聞く機会が時折あります。
そうした話の中で、
「どうやったら、子どもが一人できちんとできるようになりますか?」
と質問されることもとても多いです。
そこで今回は、子どもの課題をスモールステップで段階的に解決していく方法についてお話ししていきます。
そもそもスモールステップって何?
スモールステップとは、目標を段階的にわけてひとつひとつのステップを確実に達成することで、最終的な目標に近付くという、目標達成のための方法のことを言います。
以前、このブログでお話しした応用行動分析の理論でも使われる方法で、行動分析と呼ばれる分野の考え方からスモールステップは生まれました。
日常場面で例えると、自転車の練習をイメージしていただくとわかりやすいと思います。
自転車に乗れるようになるために、
- 補助輪を2つ付けて、親が手で支える
- 補助輪を付けたままの状態で、親が手を離す
- 乗れたら補助輪を片方だけ外してみる
- 上手く乗れたら、両輪外して親の手の支えだけで乗る
- 最後に親の手の支えもなしに乗る
のようなステップがあるのではないでしょうか。
子どもの実状に合わせた、ほどよいサポートがスモールステップにはかかせません。
子どもをよく見て、できない部分をサポートする
サポートのしすぎは、子どもの成長の妨げになる
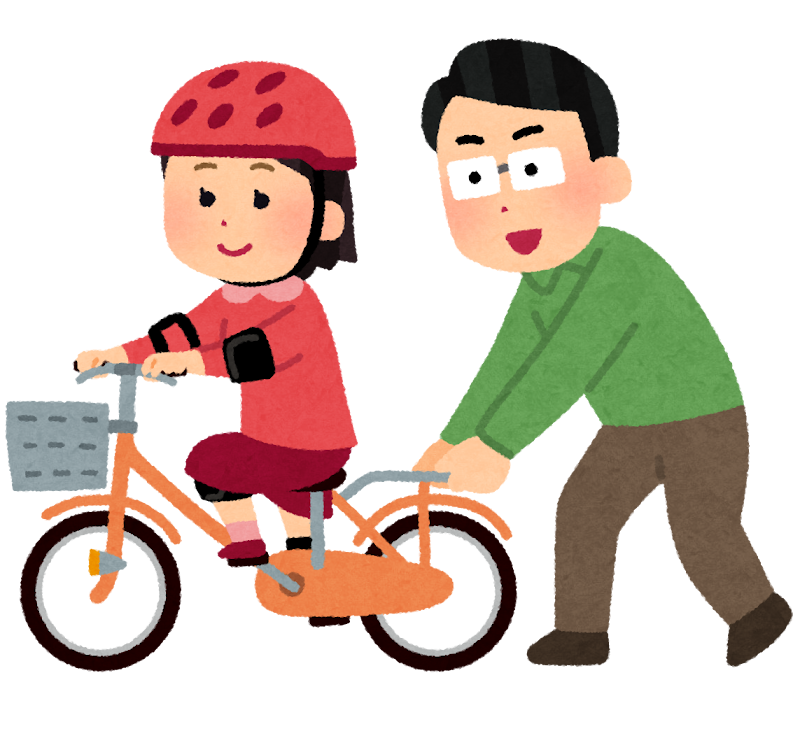
スモールステップの効果は?
スモールステップには、
- 達成しやすくて自己肯定感が得られやすい
- つまずきのポイントがわかりやすい
の2つの効果があります。
①達成しやすく、自己肯定感が得やすい
最終目標までのステップを細かくしていくことによって、子どもの「できた」が得られやすい課題設定にできます。
そうして小さな「できた」を積み重ねていくことで、子ども達の自信へとつながり結果として自己肯定感が得られます。
ここで気を付けてほしいポイントは、ママ達が「できてほしいな」と思う水準と、子どもの「できそうだな」と思う水準がズレていないかどうかです。
そこのズレが生じてしまうと、子どもにとっては難しくて、失敗ばかりしてしまう可能性もあります。
失敗ばかりの状態になってしまうと、課題そのものを嫌いになってしまったり、自信を無くしてモチベーションが下がってしまったりする危険性があります。
そうならないためにも、子どもの「できた」が得られそうなポイントを見極めて、そこからスタートしていくことが、子どもにとってもママ達にとっても安心だと思います。
そうしてたくさんの「できた」を実感することで、ほめられる経験も増えて自分に自信が持てるようになり、自己肯定感を高められます。
小さな「できた」の積み重ねが、子どもにとっての自信の積み重ね!

②つまずきのポイントがわかりやすい
スモールステップで細かく課題を設定して取り組んでいくことによって、どの段階でつまずいているのかがわかりやすいのもこの方法の利点です。
たとえば、「明日の準備」を細かくわけていくと
- ランドセルの中身を取り出す
- 連絡帳で明日の持ち物を確認する
- 確認した持ち物を準備する
- 準備した持ち物をランドセルにしまう
- 準備できたランドセルをわかりやすいところに置いておく
のような段階になるのではないでしょうか。
こうした段階があると踏まえた上で、子どもの準備の様子を見ていくと①の中身を取り出すところはスムーズにできているけど、②の連絡帳での持ち物確認は連絡帳がきちんと書けていないから難しそう、ということが見えてくるかもしれません。
あるいは、一人で③の準備は難しいけれど、ママと一緒に準備をすれば④以降は一人でできる、ということもあるかもしれません。

こうして課題を細かくわけていくことによって、つまずきのポイントがわかり、どこに焦点を当てて支援していけばいいのかの検討を付けやすくなるのがスモールステップのいいところでもあります。
細かく課題をわけることで、つまずきポイントがはっきりして支援の方向性が定まりやすい!
スモールステップを取り入れる際の注意点
ここまで、スモールステップのやり方と効果についてお話ししていきましたが、スモールステップを取り入れる際の注意点もあります。
それは、子どもにかかわる人がスモールステップの課題を把握して、一貫したかかわりをしていく、ということになります。
ご家庭内の中で、子どもから「ママはほめてくれるけど、パパは怒ってばかりいる」や「○○先生は優しくしてくれるけど、△△先生はすごく厳しい」のような反応が出てくることもあるのではないでしょうか。
子どもからすると、同じ行動をしているにもかかわらず、人によって返ってくる反応が違う、ということが一番混乱してしまいます。
そうならないためにも、スモールステップの課題設定をしていく場合には、ご家庭内や学校との共通理解がとても重要なものになってきます。
もし、当事者間では共通理解が難しい、そのような場合にはぜひスクールカウンセラーに相談していただけるといいのではないでしょうか。
一貫したかかわりが、子どもの成長への近道!

おわりに
今回は、子どもの「できない」に支援していくスモールステップの方法についてお話ししていきました。
この方法だと、子どもにとって少ない課題量で進められるため、あまり嫌がることなく進められるのがいいところだと思います。
また、この方法を実践していただいた方の中には
- 「子どものできたを意識的に見られるようになった」
- 「小さな変化を見逃さなくなった」
- 「たくさんほめられるようになって、母子ともに楽しく過ごせている」
のような変化を感じられた方も非常に多かったです。
どうしても、日々の生活の中で子どもの「できた」を見てあげたいけれど、時間にも気持ちにも余裕がなくてできない、というママも多いのではないでしょうか。
そんな時には、子どもの課題を細かくわけて見るポイントが絞れるようになってくると、「できた」が見えやすくなるかもしれません。
ご家庭の中だけで、スモールステップの課題をわけることが難しい、そんな時にはぜひスクールカウンセラーをご活用していただけると幸いです。
今回も読んでいただきありがとうございました。







