子どものネットトラブルに直面したときの保護者の対応と予防策

夏休み中、普段よりもネットとつながる時間が長くなった子ども達も多いのではないでしょうか。
普段の相談でもネットについて、
- 子どもがいつの間にかネットで友達を作っていた
- SNSで自分の写真をアップしている
- スマホやタブレットを長時間使っている
- ネットやゲームに高額の課金をしてしまった
のような話を聞く機会も少なくありません。
そこで今回は、子どものネットでのトラブルの内容とその対処法についてお話ししていきます。
Contents
子どものネットトラブルってどんなもの?
スマートフォンの登場により、子ども達が低年齢のうちからネット通信機器に触れる機会が増えてきました。
内閣府の調査によると、自分専用のスマートフォンなどの通信機器を持っている子どもの割合が年々増加してきています。
内閣府が行った「令和2年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」によると、自分専用のスマートフォンを利用している割合は、小学生で41.0%、中学生で84.3%、高校生では99.1%となっています。
小学生では約半数、中・高生になるとほとんどの子どもが自分専用のスマートフォンを持っていることがわかります。
こうした自分専用のスマートフォンを使って子ども達は、
のような活動を行っています。
小学生のうちは、動画視聴やゲームなどに使い、中・高生になるとコミュニケーションツールとして自分専用のスマートフォンを使っていることがわかります。
しかし、子ども達それぞれに管理を任せているため、どのようなトラブルが発生しているのかママ達の目には見えてきません。
普段の相談の中で、よく出てくるトラブルの内容は
- ネット上の友達との交友関係
- SNSでの対人トラブル
- ゲームやアプリでの高額課金
が挙げられます。

ネット上の交友関係
最近、ニュースでも取り上げられましたが、子ども達はネット上の友達、通称「ネッ友」と呼ばれる友達を持っていることがとても多いです。
親にどんな人とネットでつながっているかを話してくれる子は大丈夫だと思いますが、今までの相談の中ではどんな人とネットでつながっているかを知らないご家庭が非常に多かったです。
TwitterやInstagram、TikTokなど子ども達はさまざまなツールを活用して世界を広げています。
それらのツールは自分の趣味や悩み事などから、世界中の似たような境遇や趣味の子とつながれるとても魅力的なものです。
しかし、ネットでのつながりは相手がどのような人なのか顔が見えないところが怖い面でもあります。
子ども達に話を聞いてみると、
- 「私はしっかりと選別しているから大丈夫」
- 「相手の身元はちゃんと確認している」
- 「自分の個人情報は明かしていない」
と自信満々な回答をすることが非常に多かったです。
しかし、よくよく話を聞いていくと
- 相手が同い年って言っていた
- 相手の写真を確認した
- 制服姿の写真を相手に送った
のようなやり取りをしていることもありました。
本当に相手が言っている通りの人物である可能性もありますが、なりすましである危険性も非常に高いです。
今はまだトラブルになっていなくても、いずれトラブルにつながるかもしれないという危険性がネッ友との関係にはあるのではないでしょうか。
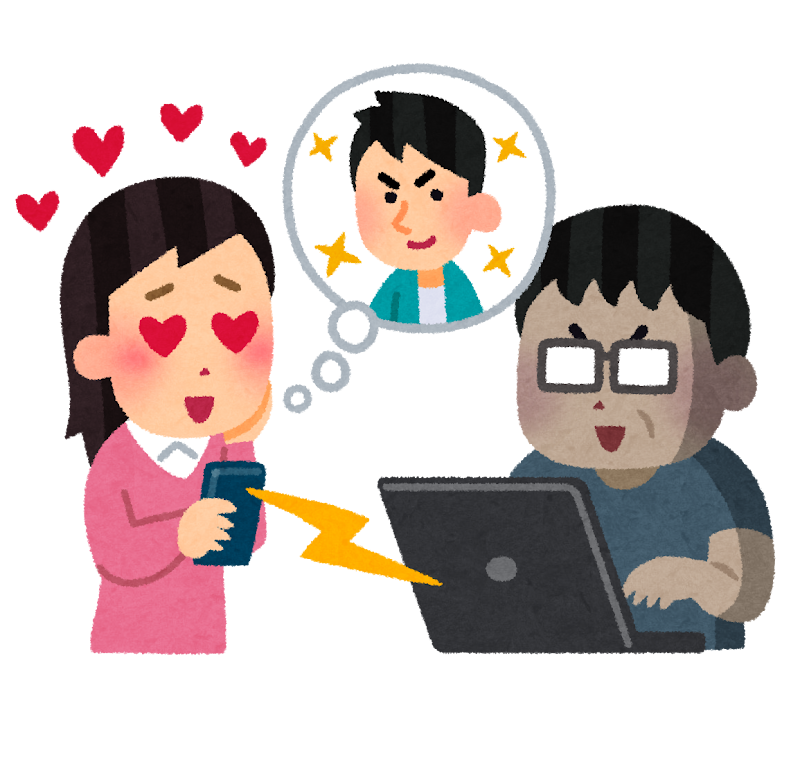
SNSでの対人トラブル
携帯電話やスマートフォンの流通が広まってきた頃から、ネットいじめと呼ばれるものに注目が集まるようになりました。
中学生になると、部活動の連絡をLINEで行ったり、進級の度にクラスごとのグループLINEを使ったりとSNSでのやりとりが盛んになります。
そうした中で、LINEのグループ外しや悪口などをネットなどに書き込まれる、といったトラブルにつながることがあります。
それ以外にも、実際にあった事例として友達同士のやり取りの一環で自分の下着姿を相手に送ってしまい、それが他の人にまで広がってしまったということもありました。
SNSでのコミュニケーションは、対面でのコミュニケーションと違って文字という限られた情報だけで相手の気持ちを考えなければなりません。
「そんなつもりはなかった」と、トラブルの聞き取りをした時に話す子どもが非常に多いです。
しかし、ネットでは「そんなつもり」が通用しない世界であることを、しっかりと認識しないと思いもよらないトラブルにつながりかねません。

ゲームやアプリなどの高額課金
スマートフォンを使って、アプリやゲームをしている子どもはとても多いのではないでしょうか。
無料でできるゲームでも、課金をすることでより強くなれるなど、つい課金したくなってしまう作りになっています。
また、最近ではLIVE配信ができるアプリもあり、そのアプリ内でお気に入りの配信者に投げ銭と呼ばれる課金が問題になっていることもあります。
お小遣いの範囲内で課金している間はいいのですが、中には親の財布からお金を抜き取ってしまう、親のクレジットカードを使ってしまう、といった事態に発展してしまう危険性が出てきます。

では、こうしたトラブルにならないためにご家庭ではどのような対応をすればいいのでしょうか。
子どものネットでのトラブルにどう対応する?
子どものネットでのトラブルに対してできる対応としては大きく分けて
- トラブルを未然に防ぐ対応
- トラブルを処理する対応
の2つになると思います。
①トラブルを未然に防ぐ対応
子どもがネットでのトラブルに遭わないように、ネットを使う際のルール作りが未然に防ぐ対応としては考えられます。
- フィルタリングの設定
- ネット利用のルール作り
- 子どものネットリテラシー教育
これらのことを意識してご家庭では対応していただくのがいいのではないでしょうか。
子どものネットリテラシー教育は、できれば自分専用のスマートフォンを持つ前の段階に少しずつ子どもの年齢に合わせて行っていただくのがおすすめです。
その際に、
のような本を使いながら話をしていくと、子どもの理解にもつながります。
②トラブルを処理する対応
できればネットでのトラブルは未然に防ぎたいですが、中にはどうしてもトラブルが発生してしまったということもあるかもしれません。
そんな時には、トラブルの内容にもよりますが
- 警察
- 消費者庁
- クレジットカード会社
- 弁護士
のような機関に相談していただく必要があります。
個人情報が流出してしまった、のような事態の場合にはプロバイダやサイトの運営会社等に連絡していただくこともあります。
こうした対応が必要な事態にならないことが一番なので、トラブルを未然に防ぐ対応をご家庭ではしっかり取り組んでいただくといいのではないでしょうか。

ネットトラブルは未然に防ぐことが大切!
おわりに
今回は、子どものネットでのトラブルの内容と解決法についておはなししていきました。
夏休み中、子どもとネットの距離が普段よりも近づいてしまったご家庭も多いと思います。
夏休み明けの相談で不登校に次いで多くなるのが、ネット関連の相談です。
正しく使えばネットはとても魅力的で、頼りになる存在でもあります。
子ども達が正しく安全にネットを楽しめるように、ご家庭でもネットとの付き合い方を考えていただけると嬉しいです。
今回も読んでいただきありがとうございました。








