勉強が苦手な子どもの背景にあるLD(学習障害)と不登校の関係を解説

夏休みが明けて2週間がたち、学校も普段の姿に戻ってきたところも多いのではないでしょうか。
そうした中、少しずつ不登校の相談が増えてきています。
相談の中で、
- 「勉強が難しくなってきて、学校に行くのが嫌だと言っている」
- 「夏休み明けの勉強のスピードについていけない」
- 「自分ではやっているつもりなのに、全然勉強ができない」
のような話を聞く機会があります。
そうした話の中で、
「もしかしたらうちの子ってLDですか?」
と質問されることもあるので、今回は不登校の原因にもなるLDについてお話ししていきます。
Contents
どんな時に「うちの子って…?」って感じる?
もしかしてLDかも、と感じたエピソードはさまざまですが、相談の中でよくあるものとしては
- 音読を一文字ずつ確認しながら読むのでゆっくり
- ひらがなや漢字を書くのに、鏡文字や抜けてしまうことがある
- 計算問題は得意なのに、文章問題になると解けない
- きちんと聞いているのに、実際には違う動きをする
のようなエピソードが挙げられます。
こうしたエピソード=LDというわけではありませんが、「もしかして?」の参考にしていただければと思います。
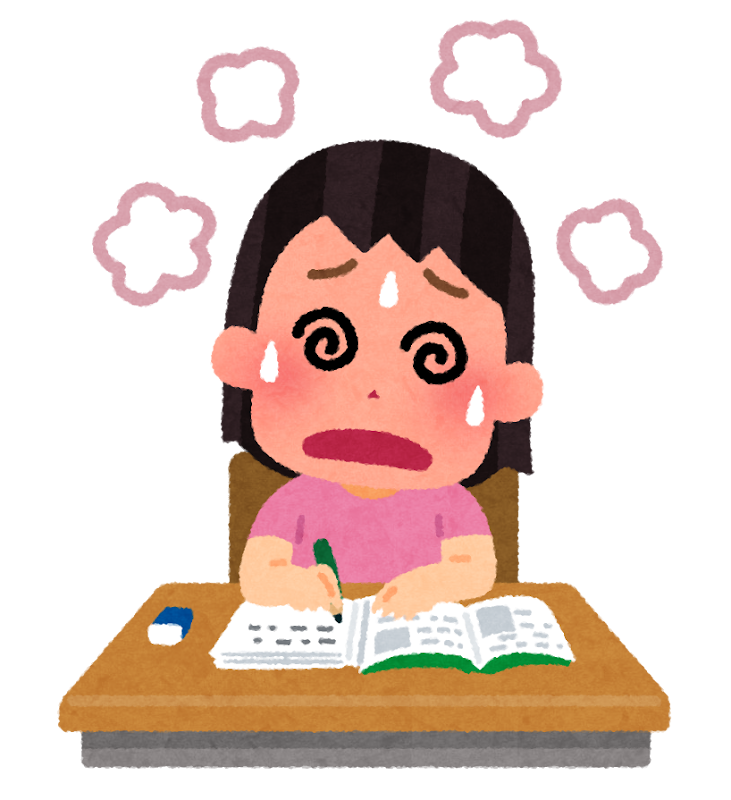
では、そもそもLDとはどんなものなのでしょうか?
LDっていったいどんなもの?
LDは学習障害とも呼ばれ、医療と教育では定義が少し異なります。
共通しているものとしては、知的な能力に問題がないにもかかわらず、勉強面での得意・不得意のバランスが悪く、いくら頑張っても効果が出ない状態をLDと定義しているところです。
同じLDの診断が出ていても、子どもによって出てくる症状はさまざまです。
- 読むことが苦手だけど、計算は得意
- 読むことは得意だけど、文字を書くことが苦手
- 読み書きは得意だけど、計算は苦手
このように出てくる症状が異なります。
なので、子どもがどの部分に困っているかを正しく見極めることがLDへの支援の第一歩となります。
パターン① 書くことが苦手
「わ」や「れ」、「ソ」や「ン」のような似ている文字を見分けることが難しかったり、漢字の線が足りなかったり多かったりする子どもが時折います。
先生が黒板に書いた文字をノートに書き写すのにも時間がかかり、書き終わるよりも前に黒板の文字が消されてしまったという子どももいます。
- 文字の形がなかなか覚えられない
- 文字や単語が抜ける
- 助詞・長音・促音・拗音の書き間違いが多い
- 文字を思い出すのに時間がかかる
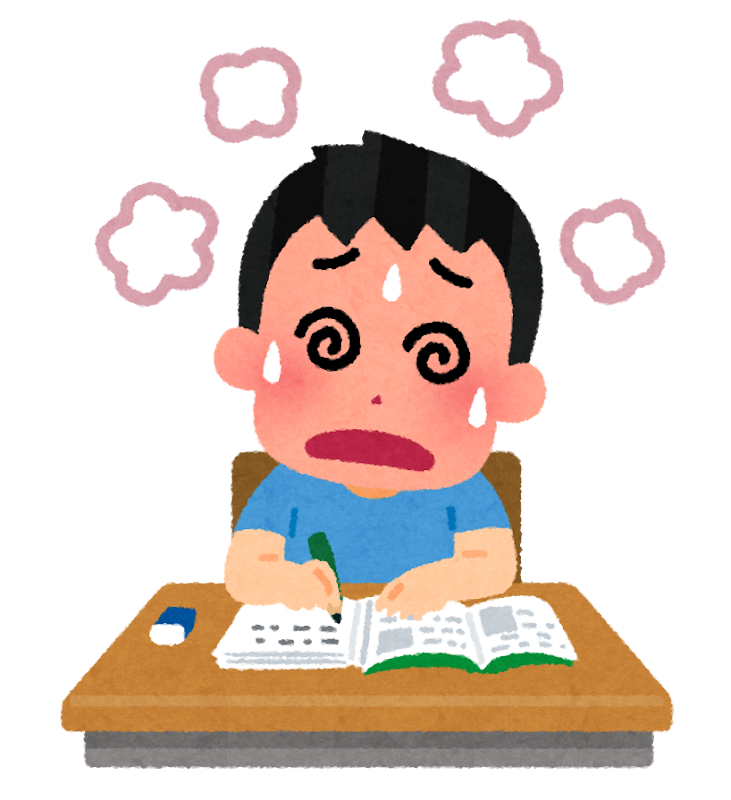
パターン② 読むことが苦手
文字の読み方を覚えたり、文字の読み方を思い出すのに時間がかかったりする子どもがいます。
文字を読む、ということができても単語のかたまりとして認識できなくて、内容の理解にまでつながらない子どももいます。
「しゃ」、「ちょっと」などを「しや」、「ちよつと」となどと呼んでしまい、拗音や促音を読むことが苦手なこともあります。
- 一文字ずつ読むので、読むのに時間がかかる
- 音読で行を飛ばしたり、同じ行を読んでしまったりする
- 単語だとわかることも、文章になると意味がわからなくなる
- 文字や言葉を抜かして読む

パターン③ 計算が苦手
いくら問題を練習しても計算ができるようにならない子どもがいます。
九九などを丸暗記してできたように思えても、実際の場面で応用して使うことができないなど理解にまで至っていないこともあります。
繰り上がりや繰り下がりなどが入ると、ひっ算の位取りを間違えてしまい時間がかかるということもあるかもしれません。
- 指を使って計算する
- 九九が暗記できない
- 位取りを間違える

パターン④ 話すことが苦手
文字の読み書きはできるのに、話すことが苦手な子どももいます。
たとえば、話しているうちに自分が何を言いたかったのかがわからなくなってしまい、話すことがめちゃくちゃになってしまうことが考えられます。
グループでの話し合いの時にも、言いたいことはあるのにうまく言葉にできなくて固まってしまうこともあるかもしれません。
- 話したいことを整理して話せない
- 話したい内容をすぐに思い出せない
- 助詞や接続詞をうまく使えない
- 筋道を立てて話せない
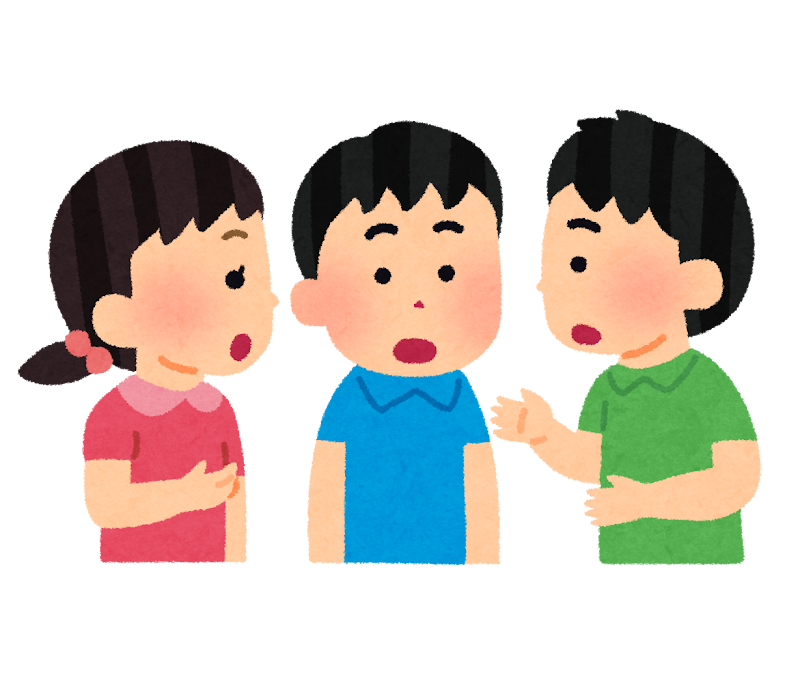
パターン⑤ 聞くことが苦手
先生やママの話を聞き間違えたり、聞き漏らしてしまったりする子どもがいます。
「プリントのここまでをやったら先生が〇付けをするから、終わったら先生に見せてください。そこまでできたら自分の席でできることを静かにやっていていいですよ」
のように複数の指示を出されてしまうと、何を言われたかが理解できずに行動できないこともあるかもしれません。
- 聞き間違いや聞き漏らしが多い
- 似ている音の聞き間違いや覚え間違いが多い
- 相手の言うことが理解できない

パターン⑥ 推論が苦手
計算問題は得意なのに、文章問題や図形やグラフの問題が苦手な子どももいます。
算数の文章問題を解くためには、問題文を読んでその意味を理解しなければなりません。
推論が苦手な子どもは、文章の中から関係する数字や式に置き換える部分を抜き出したり、立体の図形を展開させたりすることがとても難しく感じてしまいます。
- 文章問題が苦手
- 図形や表、グラフの問題が苦手
- 予測や推測が必要な課題が難しい

では、こうしたLDの症状は何が原因で引き起こされるのでしょうか。
LDの原因って何?
LDの子どもは知的な発達の遅れがないため、
- 怠けている
- ふざけている
- やる気が足りない
- やればできるのにやっていない
のように誤解されてしまうことがとても多いです。
子ども自身も説明のつかない難しさがあるため、どんどん自信をなくしてしまい、苦しくなって不登校を選択してしまう危険性があります。
LDの原因はすべてが明らかになっているわけではありませんが、脳の中枢神経に何かしらの機能障害があって引き起こされる、と考えられています。
LDの原因は、親の育て方や子ども自身の甘え・怠けではない!
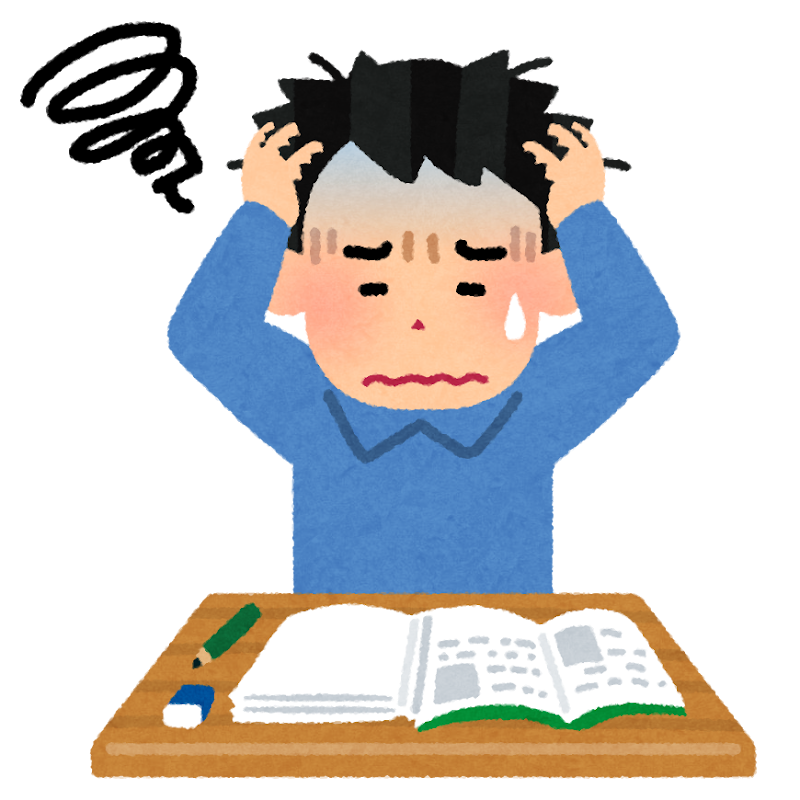
ここでいくつかLDの原因となるものについてお話ししていきます。
LDの原因① 聞く力が弱い
聴覚の機能に特に問題がなくても、先生の指示を聞き間違えたり聞き漏らしたりしてしまうことがあります。
普段の私たちの生活では、さまざまな音に囲まれて生活しています。
道路を走っている車の音、風や雨の音、他の人の話す声、こうしたさまざまな音の中から必要な音を選択して聞く力というものが私たちは求められます。
また、そうして聞いた音を頭の中で意味のある言葉に変換しなければならず、聞く力の弱い子どもはこの変換する機能が弱いと考えられています。
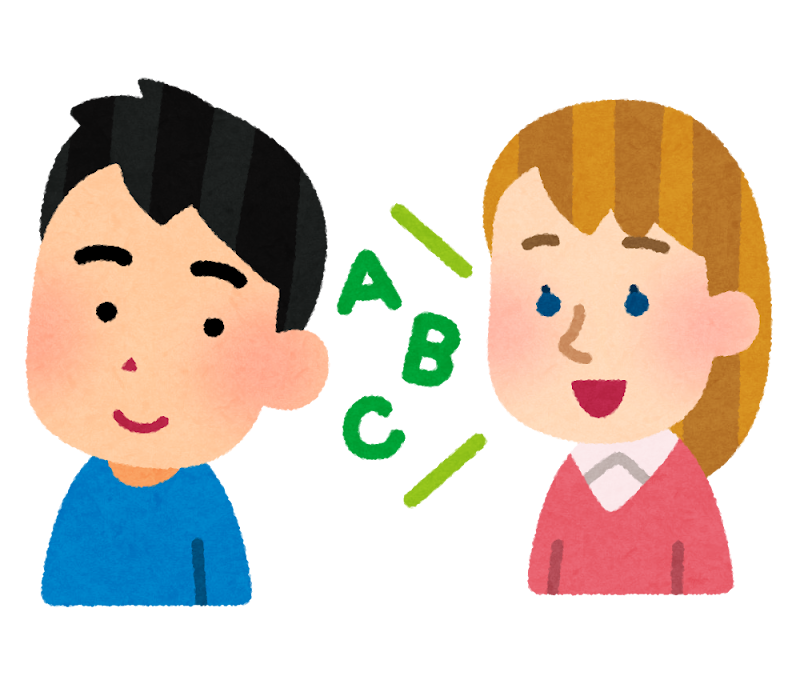
LDの原因② 見る力が弱い
私たちの目は、自然と見たいものにピントを合わせたり、見たいものに合わせて目を動かしたりできます。
そうして見たものを頭の中で処理して、色や形、動きなどを把握します。
LDの子どもの中には、こうした見る力が弱い子どもがいます。
見る力が弱いと、見たいものに合わせて目を動かしたり、物の形をとらえたりすることがとても難しいです。
また、見る力の弱さが原因で
- 板書に時間がかかる
- 図形の形をとらえられない
- ひっ算の桁をそろえられない
のような問題も出てきます。

LDの原因③ ワーキングメモリーが弱い
ワーキングメモリーとは、作業記憶とも呼ばれるもので人が頭の中に一時的に情報を記憶して処理するのにとても大切な機能です。
たとえば、
「お風呂の栓をして、お風呂を入れてきて」
と言われた時に、その指示の内容を記憶するためにワーキングメモリーが使われます。
LDの子どもの中には、こうしたワーキングメモリーが弱いため、授業中に先生の指示を覚えていられなかったり、テストでうっかりミスが多かったりしてしまうことがあります。
ミスをしないようにと気を張りすぎて疲れてしまい、ボーっとしたり忘れたりして失敗を重ねてしまう悪循環に陥ってしまうことも珍しくありません。

では、こうしたLDの子ども達にはどのように支援をしていけばいいのでしょうか。
家庭でできるLDの子どもへのサポート
LDのある子ども達は、
- 「一生懸命勉強しているのに結果が出ない」
- 「ちゃんとやっているのに、怠けているや努力が足りないと怒られる」
- 「どうせやっても変わらないからやりたくない」
のように自信をなくしていることがとても多いです。
そうした自信をなくした状態が長く続くと、不登校やうつなどの二次障害を起こしてしまう危険性が高くなります。
そうならないためにも、ご家庭では
- 何に困っているのかを把握する
- LDについて周囲の理解を得られるようにする
- 得意な方法を見つける
- 苦手なことは無理強いさせない
- 一緒に成功体験を積み重ねる
- 子どもにとってリラックスできる環境を整える
といったことを意識していただくといいと思います。
特に、子どもが勉強のどこにつまずいて困っているのかを把握することによって、子どもにとって必要な支援が見つけやすくなります。
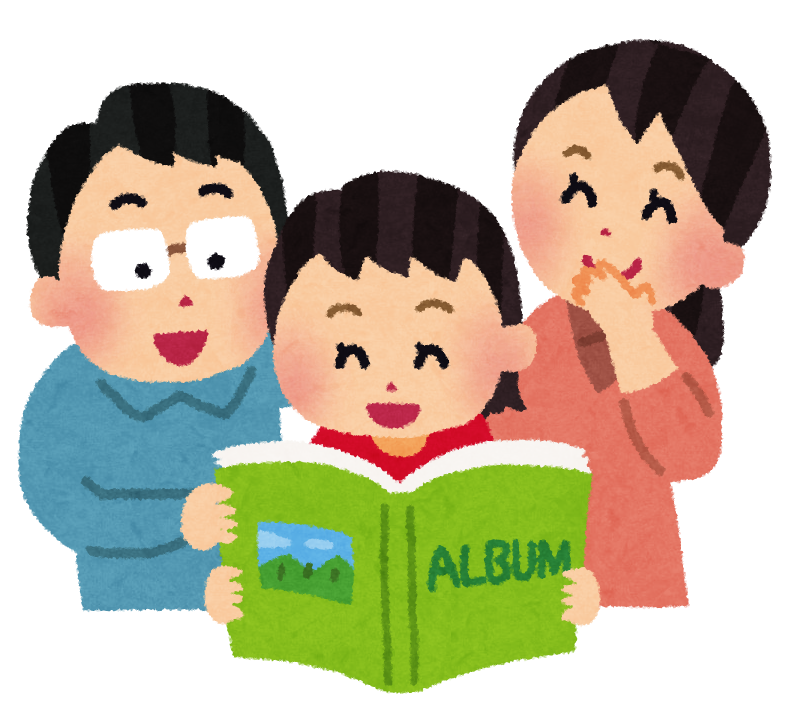
では、子どもがLDかもしれないと悩んだ時にはどこに相談にいけばいいのでしょうか。
LDはどこに相談に行けばいいの?
子どもがLDかもしれないと悩んだ時には、
《診断を求める場合》
- 療育センター
- 発達の専門医のいる病院・クリニック
《診断を求めない場合》
- 子育て相談窓口
- 児童相談所
- 地域の教育相談センター
- スクールカウンセラー
などに相談していただくといいと思います。
診断を受けた方がいいのか悩む、という場合にはスクールカウンセラーや子育て相談窓口などでどうしたらいいのか相談してみるのもいいのではないでしょうか。

LDの理解と支援におすすめの本
直接相談に行くのは抵抗がある、というママも中にはいるかもしれません。
直接相談に行かずとも、LDについて知識を得たりサポートの仕方を学んだりすることはできます。
私がこれまでに読んでわかりやすかった本が2冊あるので、簡単に紹介します。
まず1冊目は
この本は、LDに関する知識やサポートの仕方、相談の窓口などがわかりやすく解説してあります。
ご家庭でできる、見る力・聞く力を高めるあそびや年代別の子育てのポイントも載っているので、LDの入門書としておすすめです。
2冊目は
この本は、LDの子どもの悩みに合わせた支援方法がわかりやすく解説されていて、まずはご家庭で試してみたいと思った時におすすめできる本です。
おわりに
今回は、不登校の原因にもなるLDについておはなししていきました。
LDはなかなか気づかれず、気づいた時には子どもが自信をなくしていた、というパターンも少なくありません。
経験上、自信をなくしてからではなかなか支援が入りにくいことがとても多かったです。
なので、ご家庭での学習の様子を見て、
「何かおかしいな」
と感じたら、できるだけ早く相談に行くことが早期発見の秘訣です。
少しでもLDで苦しむ子どもを減らすために、この記事を参考にしてもらえたら嬉しいです。
今回も読んでいただきありがとうございました。







