子どものゲーム依存が心配なときに家庭でできる対応とルールづくり

スクールカウンセラーとして勤務している中で、
- 「子どもが1日中スマホを触っている」
- 「夜中までゲームをやっていて、朝起きられなくなっている」
- 「スマホを取り上げようとすると暴れて手が付けられない」
といった相談を受けることがあります。
以前までは中学校でこのような相談が多かったのですが、最近では小学校でも同様の相談が増えてきています。
WHOでも、ゲームやネットに依存することによって健康に支障をきたす人が増えたことから、「ゲーム症」という診断基準を設けるぐらい、ゲームやネットの依存は世界的にも深刻な問題です。
そこで今回は、子どもがゲーム・ネット依存かもしれないと思った時にできることについてお話ししていきます。

Contents
子どもがゲーム依存か見るポイント
一日中スマホを手放さない、生活のリズムがめちゃくちゃ、取り上げると暴れてしまう、こんな子どもの姿をみてゲーム依存かもしれないと不安に感じるママもいるのではないでしょうか。
「うちの子はただゲームが好きなだけ」
そんな風に不安を見ないようにしてきたという話を聞くことも少なくありませんでした。
ゲームやネットにハマっていても、普段の生活に支障がない範囲で楽しんでいるのであれば、それは依存とは言えません。
子どもが自分の意志でゲームやネットを止められず、普段の生活に支障が出てしまっている時に依存という診断につながります。

- 生活のリズムが乱れている
- 不登校傾向がある
- ゲームやネットをしていない時間はいつもイライラしている
- ゲームやスマホを取りあげると、普段の姿から考えられないくらいに暴れる
- ゲームやネットができないと、チック症状が出る
- 課金するために親の財布からお金を取る など
子どものこんな姿が見られたら、一度相談に行っていただくことをおすすめします。

そもそもなんでゲームやネットに依存するの?
どうしてもゲームやネットに依存している子どもに対して、
- 自制心がなくてだらしない子
- やりたいことを我慢できないダメな子
- 面倒なことから逃げている子
などのような見方をしてしまいがちです。
たしかに、子ども達の様子を見ているとそのように感じてしまう姿もあるかもしれません。
しかし、子どもの様子を注意深く見てみると、ゲームやネットに夢中にならざるを得ない場合もあります。

- 学校や家庭内で居場所がなく孤立感がある
- コミュニケーションが苦手などの本人の特性
- 好きなものに対してのめり込みすぎる性格 など
子ども達はこうした要因からストレスを多く抱えていることがあります。
そうしたストレスから逃げるために、ゲームやネットをしていることが今までの相談でも数多く見受けられました。
最初のうちは短い時間で満足できていたゲームやネットも、続けていくうちに物足りなさを感じてどんどんと時間が伸びてしまいます。
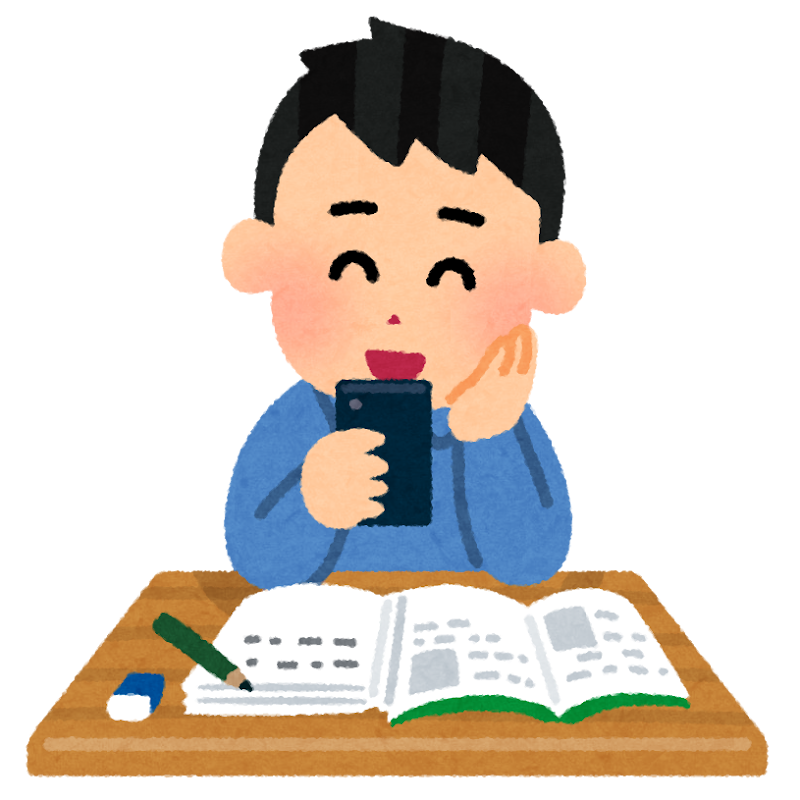
こうした要因を無視して、スマホやゲーム機器を取り上げるだけでは根本的な解決には至りません。
ゲームやネットは、子どもにとって心の拠り所!
取り上げるのではなく、認めた上で別の方法を一緒に探すことが大切!
では、子どもがゲームやネット依存かもしれないと思った時には、どのように対応すればいいのでしょうか。
ゲーム・ネット依存にはどのように対応すればいいの?
ただゲームやネットを遠ざければいいわけではないのが、ゲーム・ネット依存の対応の難しさでもあります。
子ども達にとってゲームやネットの世界というのは、
- SNSを通じて他者とのつながることができる
- ゲームによって日常では味わえないスリルや達成感が得られる
- 嫌なことを忘れてリラックスできる
こうした良さを味わえる場です。
子ども達なりに、日々のストレスとうまく付き合おうと思ってゲームやネットをしていることを理解することからゲーム・ネット依存の対応は始まります。
- 子どものストレスになっている要因を探す
- 相談先を探す
- 日常生活の中の楽しみを増やす
このような視点で、ゲーム・ネット依存に対応していただくといいと思います。
①ストレスの要因を探す
孤立感や子どもの特性など、さまざまなものが要因となってゲーム・ネット依存につながることがあります。
- 友達との関係がうまくいかず、学校で孤立している
- 勉強が苦手で、学校の授業を苦痛に感じている
- 好きな物へのこだわりが強い
今までの相談の中でも、こうした子どもの要因からゲーム・ネット依存につながっているケースが少なくありませんでした。
子ども本人から学校での様子などを聞くことは難しいかもしれないので、そうした時には担任の先生に相談していただくのもいいと思います。
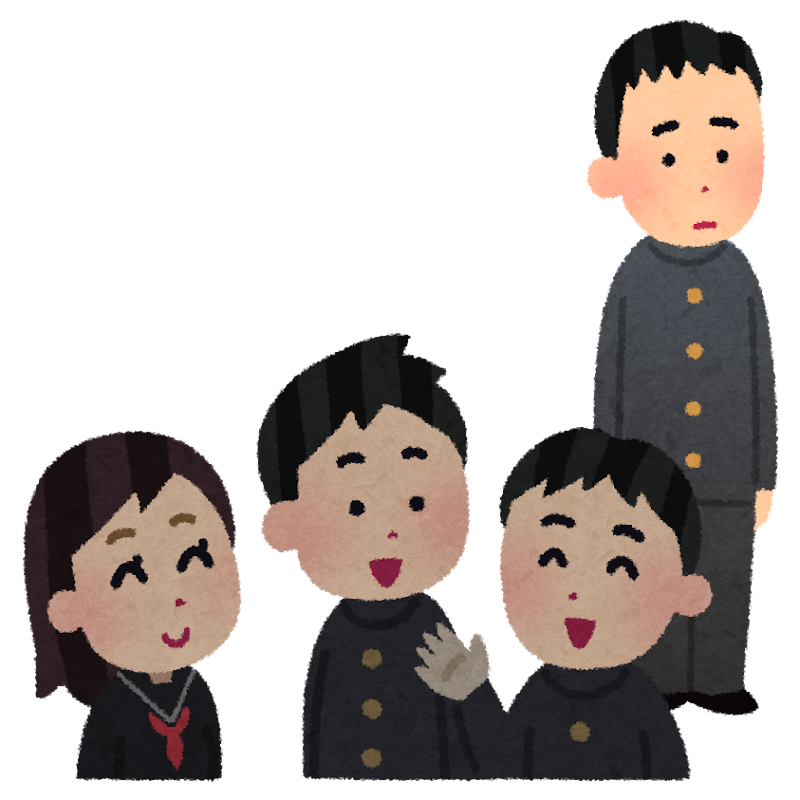
②相談先を探す
子どもを取り巻く環境が、ゲーム・ネット依存に影響しているとわかっても、いざゲームやネットをしている姿を見ると冷静に対応できないというケースを数多く見てきました。
家庭だけでどうにか対応しようとすると、子どもだけではなくママ達も孤立感を深めてしまう危険性があります。
そうならないためにも、
- 地域の教育相談センター
- 地域の子育て相談窓口
- 児童精神科のある病院
- スクールカウンセラー
などに相談していただくのをおすすめします。
第三者に相談することによって、現状を客観視できて対応にも余裕ができます。

③日常生活の中の楽しみを増やす
子ども達がゲームやネットに依存してしまうのには、それ以外の楽しみがないことも影響しています。
ゲームやネット以外にも、子どもが「楽しい」と思えるものが増えてくると、自然とゲームやネットに向かう時間は短くなっていきます。
今までの相談の中でも、
- アニメやゲームのイベントに参加する
- YouTubeで紹介されたレシピを見ながら料理をする
- 自転車で移動しながらポケモンGOのようなゲームをする
といった楽しみを見つけた子どももいました。

おわりに
今回は、子どもがゲーム・ネット依存かもしれないと思った時にできることについてお話ししていきました。
子ども達を取り巻く環境は、目まぐるしく変わってきています。
そうした環境の変化についていけない子ども達にとって、ゲームやネットの世界はとても魅力的な場所です。
ゲームやネットの世界を自分の居場所だと思ってしまう危険性は大人にもあります。
こうした本を読んで、ママ達もゲーム・ネット依存の知識を取り入れてみるのもおすすめです。
今回も読んでいただきありがとうございました。






