現役スクールカウンセラーが選ぶ!子どもと関わるためのおすすめ書籍

普段の相談の中で、
「子どものことを理解するために勉強したいけど、どんな本を読んだらいいですか?」
と質問されることが時折あります。
それ以外にも、子どもとの相談の中でも子どもの自己理解を深めるために本を紹介することも少なくありません。
そこで、今回は普段私が相談の中でおすすめしている本についてお話ししていきます。
Contents
子どもにおすすめの本
相談に来てくれた子ども達にも、本をおすすめすることがあります。
- 「不安な時にどうしたらいいのかわからない」
- 「自分が他の人と何だか違う気がする」
- 「ネガティブに考えるのをやめたい」
こんな話が出た時に、子どもの要望に応じて本を紹介していきます。
不安解消におすすめの本
この本は、認知行動療法のエッセンスを子ども向けに優しく解説している本です。
いろんなタイプの不安を感じる子どもを題材にしていて、自分に似た子どもがどんな風に不安を和らげていくのかがわかりやすく描かれています。
かわいらしい絵と取り組みやすいワークで構成されているので、不安の強い小学生の子どもに特におすすめです。
ご家庭では、ママも一緒になってワークに取り組んでいただくと、子どもも取り組みやすくなると思います。
自分のことを理解するための本
思春期の女の子の相談で時折出てくるものに、
「自分は何だか人と違う気がする」
というものがあります。
よくよく話を聞いていくと、HSCと呼ばれるような繊細な気質を持っている子も少なくありません。
そうした時に、上記の本を紹介して自分がどんな風に感じやすくて、そんな時にどんな風に過ごすと居心地がよくなるのかを考えてもらうことがあります。
小学校高学年から中学生になれば、本の中から自分に必要なものを選ぶことができるようになってくるため、こうした知識につながる本を読んでみるのもおすすめです。
ネガティブな気持ちを減らす本
自信がなく、何をするにもネガティブになってしまう子どもを相談の中でとても多く見てきました。
そんな時に、
「自分は大丈夫」
と思えるような自己肯定感を育てていくのにおすすめの本です。
さまざまなスイッチを試していく中で、少しずつ自己肯定感が育っていきます。
子どもでも読みやすい文章で書かれているので、小学生からでも読めます。
ご家庭でも、親子で一緒に取り組んでいただくとより効果的です。
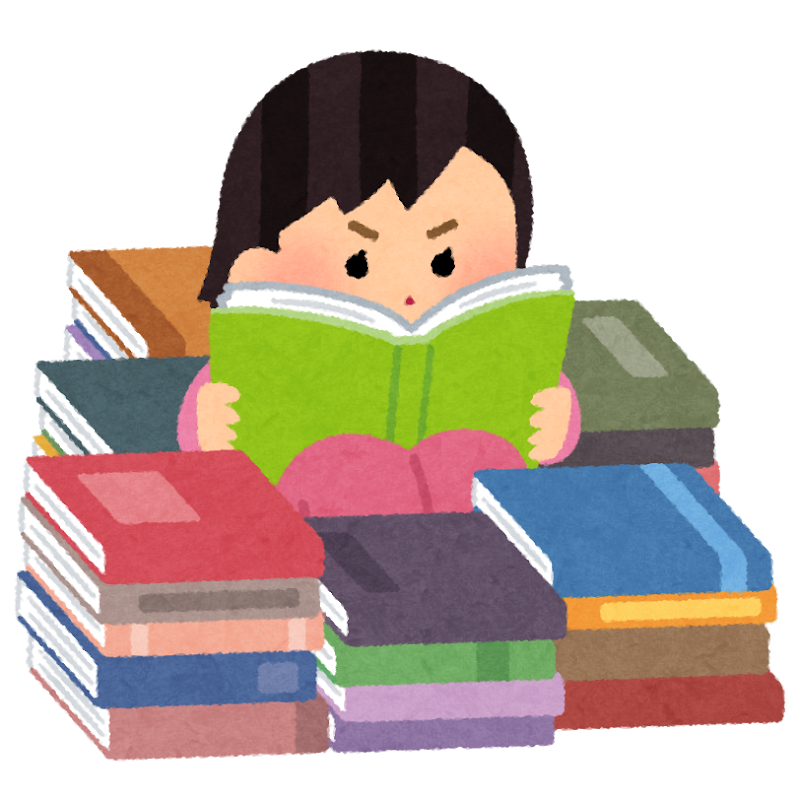
保護者におすすめの本
ママ達からは、
- 「子どもが何で朝起きられないのか理解できない」
- 「障害のある子どもの進路が心配」
- 「どうしても子どもに対して怒りすぎてしまう」
こんな相談を受けた時に、状況に応じて本をおすすめすることがあります。
朝起きられない子どもを理解する本
ここ数年で起立性調節障害という診断名が浸透しつつあります。
朝起きられない病気があると知ってもらえたことは、当事者の子ども達からすると嬉しいものです。
しかし、具体的にどんな症状があるのかやどんな支援が必要なのか、という点についてはまだまだ知られていないことが多いです。
そこで、上記の本を紹介して起立性調節障害について正しく理解してもらうために役立ててもらっています。
起立性調節障害という前提はありながらも、それぞれのシリーズの主人公が抱えている悩みは異なります。
なので、自分の子どもにも当てはまる部分はあるかもしれない、という視点で読んでいただくとより子どもの理解へとつながっていくと思います。
障害のある子どもの進路に役立つ本
この本は、障害のある子どもの進路についてご家庭でどんな風に考えていけばいいのかを分かりやすく書いています。
どうしても、教育の中では「今」を重視するあまりに「未来」について抜けてしまうところがあるので、 こうした進路に向けて考える時間を作ることが重要です。
学校の種別や就職など、子どもの「未来」についてさまざまな選択肢を示してくれるので、自分の子どもにはどんなものが必要かを考えるための手助けとなってくれると思います。
受験期に特性のある子どもの勉強がなかなか進まなくて困っている、という相談も時折あります。
子ども達自身もうまく勉強を進められないもどかしさを感じていることも少なくありません。
親が教えようと反発することも考えられるので、こうした本を活用して勉強方法を一緒に探っていくのもいいかもしれません。
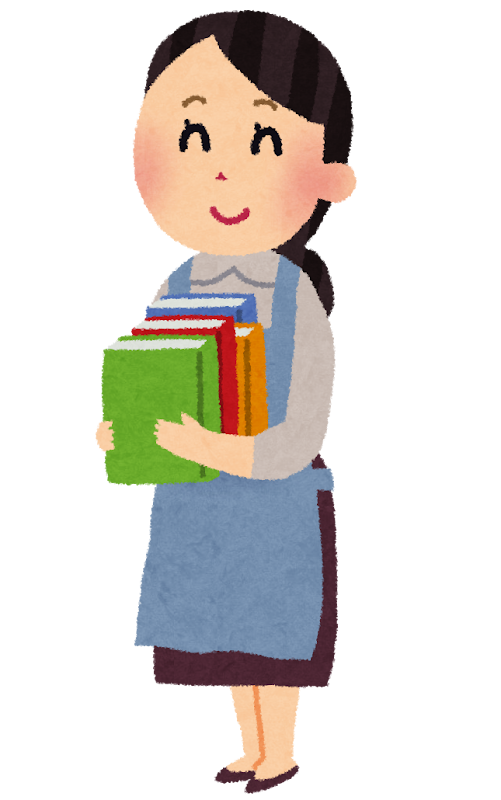
おわりに
今回は、普段の相談の中で子どもや保護者におすすめする本についてお話ししていきました。
こうした本の紹介は、認知行動療法の中でも読書療法と位置付けられるものでもあります。
50分という限られた相談時間の中では伝えきれないことを、本を通じて知ってもらえるようにおすすめさせていただくことが多いです。
相談に行くことへの抵抗感がある人にも、今回お話しした本を読むだけでも解決につながるものもあるかもしれません。
子どもの理解のきっかけの一つとしてこうした本を活用していただけたら嬉しいです。
今回も読んでいただきありがとうございました。







