子ども達との相談の中で、時折
「スクールカウンセラーになりたいけど、どんな風に勉強すればいいですか」
という質問をされることがあります。
特に、中学生など進路のことが身近に感じている子どもからそのような質問をされることが多いです。
そこで、今回はスクールカウンセラーの必須資格ともいえる、臨床心理士の合格までの道のりを私自身の体験を基にお話ししていきます。
Contents
どうやったら臨床心理士の受験資格が得られるの?
まず、臨床心理士になりたいな、と思ってもそもそも受験資格がないことにはスタートの位置にも立てません。
臨床心理士の受験資格は、
〈主な受験資格〉
●指定大学院(1種・2種)を修了し、所定の条件を充足している者
●臨床心理士養成に関する専門職大学院を修了した者
●諸外国で指定大学院と同等以上の教育歴があり、修了後の日本国内における心理臨床経験2年以上を有する者
●医師免許取得者で、取得後、心理臨床経験2年以上を有する者 など
とされています。
私自身は、一番上の受験資格である1種指定大学院を修了後に受験して一度の試験で合格しました。
多くの人が1種か2種の指定大学院を修了して受験資格を得ているかと思います。
では、1種と2種の違いは何かというと、大学院内に実習機関を備えているかどうか、ということです。
実習機関が何かというと、大学院の中に大学院生が実習を行える相談機関のことをいいます。
具体的には、実際にクライエントと呼ばれる相談者を大学院の相談室に招いて大学院生が実習として相談を担うものになります。
2種の指定大学院だと実習機関が併設されていないため、大学院修了後2年間の実務経験が求められます。
なので、大学院修了後、最短で受験資格を得たいのならば1種指定大学院、現場で実践を積んでから受験資格を得たいのならば2種指定大学院、という風に考えていただくといいと思います。

では、実際の大学院生活はどのようなものになるのでしょうか。
大学院生はどんな勉強をするの?
大学を卒業後、大学院は修士課程では2年間、その後博士課程まで進めばプラス3年間勉強することになります。
基本的には、修士課程の2年間を修了すれば臨床心理士の受験資格を得られます。
なので、研究を続けたい、という気持ちが強い場合を除いて修士課程のみの履修で問題ないと思います。
修士課程では、1年生のうちにいわゆる大学の時のような講義形式の授業を受けて知識を深めます。
大学の時とは異なり、より専門的で高度な内容になってくるので慣れるまでが大変かもしれません。
また、1年生のうちにも簡単な実習があり、私の場合は近隣の小学校でアシスタントのようなことを月に1回程度行いました。
大学院によっても実習先に違いがあるため、もし希望の分野などがあるようでしたら、そうした実習先のリストなども説明会などで情報収集するのがいいのではないでしょうか。
1年生の間に様々な知識を学び、2年生になったら本格的に研究と実習が始まります。
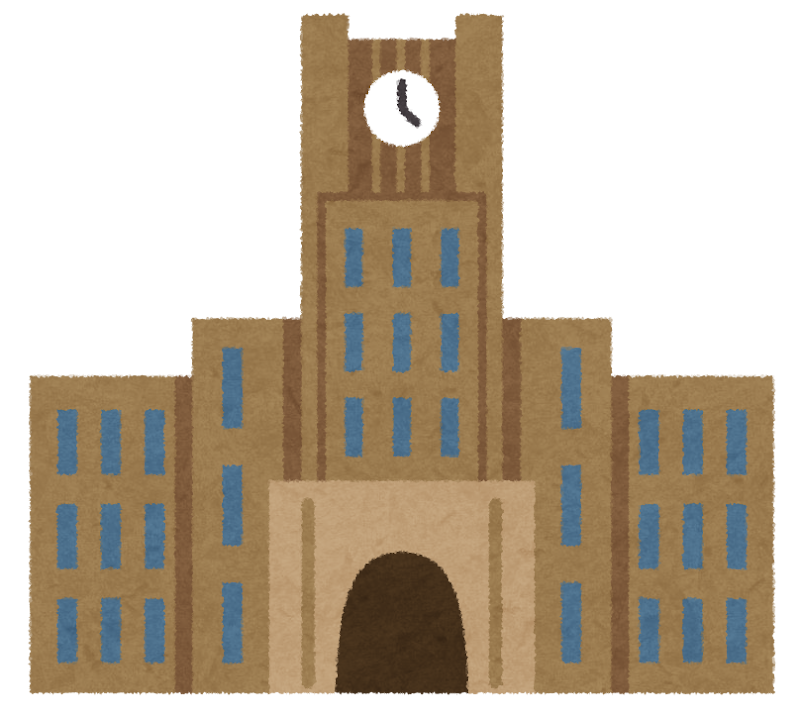
研究
この研究とは大学でいうところの卒業論文を、修士課程にちなんで修士論文という一つの論文に仕上げる研究を行います。
基本的にテーマは自分が興味のある分野からやりたいものを決めていきます。
ゼミによっては代々引き継がれている研究もあるので、そういったものをアップグレードする形で論文にまとめていきます。
ゼミは1年生の時に、どの教授のところに入りたいかの希望を聞かれるので、自分が興味のある分野の研究をしている教授のゼミに希望を出すことになります。
教授も分野の得意・不得意があるので、そうしたものを見極めてゼミ選びをする必要があります。
私自身は教育心理に興味があったため、教育心理を専門としている教授のゼミに入って研究を行いました。
テーマは自分で決めなければならないため、テーマ選びに時間がかかりすぎると研究の時間が短くなってしまい、修士論文を書くのが大変になるかもしれません。
なので、2年間の修士課程の中でどのように時間を使っていくかを、入学前から考えておくと安心です。
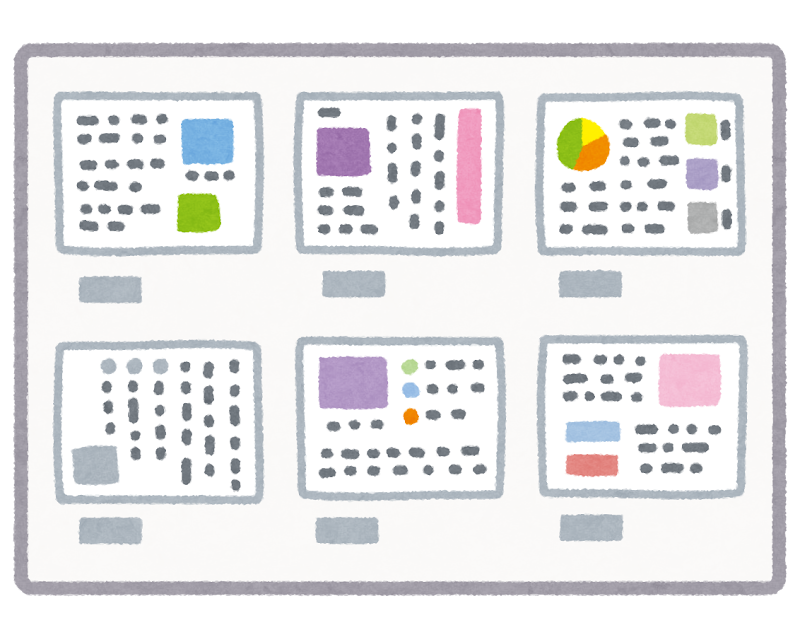
実習
実習は、私が通っていた大学院では病院や療育機関などの施設実習と大学院構内での相談実習の2つの実習がありました。
施設実習では、私が通っていた大学院では実習施設が一覧になっていてその中から選択して施設実習に行っていました。
選ぶ実習施設も修了後に働きたい分野か、働きたいかはともかく学んでみたい分野から自分で自由に選んでいました。
私自身、病院の実習も魅力的に感じていましたが、スクールカウンセラーとして勤務する時に療育の知識が役立つと思い、民間の療育施設を実習先に選びました。
こうした施設実習と併せて、大学院構内での相談実習も行います。
相談実習は、地域から実際に相談したい人を実際に招いて大学院生の技能向上のために実習として実際のカウンセリングと同じことを行います。
値段も民間のカウンセリングセンターに比べると格安で、予約も取りやすいことから大学院生が行う、ということが気にならなければ相談者の立場で行くのは穴場でいいかもしれません。
また、実習として行っているため、カウンセリングを行った後は指導教授の下で綿密な振り返りを行います。
振り返りをもただ闇雲にどうだったか、ということを話すわけではなく、逐語録と呼ばれるカウンセリングの内容を一言一句そのままに文章で書いたものを使って、指導教授と一緒になぜこの場面でこのような言葉を相談者に返したのか、ということを一つ一つ丁寧に見ていきます。
こうした振り返りの積み重ねによってカウンセリングの技能を高めていくことが相談実習の目的です。

では、大学院修了後はどのような生活になるのでしょうか。
大学院修了後の生活は?
ここまでこの記事を読んでいただいて、臨床心理士の資格の勉強をほとんどしていないことにお気づきの方も多いかもしれません。
実際に、臨床心理士の資格試験の勉強を始めるのは、大学院修了後に仕事を始めてからになります。
もしかしたら、とてもやる気のある勤勉な方は大学院在学中からも資格試験の勉強を始めているのかもしれませんが、私自身は大学院の生活にいっぱいいっぱいでとても資格試験の勉強をする余裕はありませんでした。
なので、ほとんどの人が資格試験の勉強を働きながら進めていくことになるかと思います。
臨床心理士の受験資格がそもそも大学院を修了後に与えられるため、大学院在学中に試験が受けられません。
そのため、大学院修了後は少なくとも1年間は無資格の状態で勤務することになります。
慣れない仕事をしながらの勉強生活になるため、一緒に勉強する仲間やいいリフレッシュ方法などを見つけておくと心強いと思います。
では、実際にどのような勉強方法がいいのでしょうか。
どんな勉強方法があるの?
今回は、私が実際に行っていた勉強方法を紹介します。
人によって合う合わないがあると思うので、試してみて違うなと感じたら自分なりの勉強方法を探してみてください。
私が行っていた勉強方法は、
- まとめノートを作って、自分だけの参考書を作る
- 大学院の同期と一緒に勉強会を開く
- 模擬テストや過去問を解いて問題の傾向を掴む
の3つで行っていました。
①自分だけの参考書作り
私は書いて覚えないと頭に入らないところがあるため、テキストなどを参考にノートに情報を整理してまとめてみました。
ノートの中にはテキストの情報だけではなく、③でやった模擬テストや過去問で間違えた問題を自分で調べて納得のいく解説などもまとめて、これさえ読めばとりあえずなんとかなるだろう、と思えるノートを作っていきました。
実際に当時作ったノートは後輩にあげてしまったのですが、全部でキャンパスノート5冊分の超大作で我ながらよく頑張ったと自画自賛してしまいました。
試験会場にも持っていき、「これだけやったんだから大丈夫」とお守り代わりにもなって、私個人としてはとてもやってよかったです。
この参考書作りにテキストとして使っていたのが、
の本です。
この本は1冊で臨床心理士試験の範囲を網羅するテキストとなっていて、基本的にはこの本に沿って勉強を進めていきました。
巻末には模擬試験もついているため、一通りテキストを読み込んだら模擬試験をして実力を試せたのもよかったです。
②仲間との勉強会
①と③は自分だけで勉強する方法でしたが、一人で勉強するのは息が詰まって長続きしないこともあります。
そんな時に、大学院の同期と月に2回ほどのペースで集まって、みんなで一緒に勉強会を開いていました。
勉強会では、私たちのやり方ではありますがそれぞれが受け持ちの分野を決めて、受け持ちの分野について情報を整理してみんなで共有する、というやり方をしていました。
心理検査の採点方法や、ややこしい偉人の名前、間違えやすい心理知識などについて思い思いにまとめたものを共有するのはとても有意義で楽しかったのを覚えています。
こうした仲間との勉強会は、知識を深めるだけではなくリフレッシュの場としても有効で、勉強会の後は一人の勉強もとても捗りました。

③模擬テストや過去問を解く
ある程度、勉強が進んだらあとはひたすら模擬テストや過去問を解いていました。
①で紹介したテキストについていた模擬テストだけではなく、
のような、公式の過去問を使ってたくさんの問題を解きました。
同じ問題が出る、というわけではありませんが、その年ごとに傾向が異なりある程度出てきそうな分野の目星がつくので、たくさんの問題に触れることはいいことだと思います。
こうした模擬テストなどの解説は簡略化されているものも多いため、その時に①でお話ししたようなノートに自分なりの解説をまとめる作業が振り返りに効果的になります。
 こうした勉強を経て、私自身は臨床心理士試験を一度で合格しました。
こうした勉強を経て、私自身は臨床心理士試験を一度で合格しました。
すべての人にこの勉強方法が合うわけではないと思いますが、少しでもスクールカウンセラーになりたいな、と思ってくれている人のお役に立てれば嬉しいです。
今回も読んでいただきありがとうございました。








