寝つきが悪い子どものために家庭でできる睡眠習慣づくり3つの工夫

スクールカウンセラーの相談の中で、時折あるのが睡眠に関する悩みです。
発達に特性がある子以外にも、思春期で昼夜逆転の生活をしているなど何かしらの睡眠の課題がある子が少なくありません。
- 寝つきが悪く、朝もなかなか起きられない
- 寝る時間になって急に何かをやりだす
- ゲームなどで夜更かししてしまう
どんな子どもでもこのような状態は少なからずあるのではないでしょうか。
そこで今回は、子どもの睡眠力を高めるためにご家庭でできることについてお話ししていきます。
Contents
そもそも何で睡眠は必要?
「何でもう寝なきゃいけないの?」
こんなことを子どもから言われた経験はありませんか?
子どもが納得するように説明を一生懸命するママもいれば、問答無用で寝室に連れて行くママもいると思います。
どちらのやり方が正解というわけではありませんが、睡眠がなんのために必要かを知ることは大人も子どもも関係なく大切なことです。
「眠気があるということは、人の体が眠ることを必要としているから」
シンプルに伝えるとこういうことかもしれませんが、子どもにとってはなかなか納得のいく答えではありません。
そんな時に知っておいてほしい知識は、
- レム睡眠
- ノンレム睡眠
という睡眠の仕組みです。

レム睡眠
身体は休んでいても、脳は休んでいない状態の睡眠のことを言います。
脳は休んでいないので、夢を見ることがこの睡眠状態の特徴です。
脳が動いているため、日中に活動した記憶を整理して定着させるといった働きもあります。
勉強した内容などを忘れないようにするためには、かのレム睡眠の働きが欠かせません。
テスト前に一夜漬けで勉強するよりも、短時間でも仮眠してレム睡眠の働きを促した方が効果的です。

ノンレム睡眠
身体も脳も休んでいる状態の睡眠のことを言います。
ノンレム睡眠には3つのレベルがあり、ウトウト→スヤスヤ→ぐっすりといった段階があります。
特に、スヤスヤの段階では体の動きを定着し、ぐっすりの段階では成長ホルモンが分泌されるといったとても大切な働きがあります。
- 「○○がうまくできるようになりたい」
- 「身長がもっと伸びてほしい」
- 「キレイな肌になりたい」
こんな想いを叶えるためにも、ノンレム睡眠が必要です。

では、子どもの睡眠がなかなか取れない状態はどのようなものがあるのでしょうか。
子どもの睡眠の困りごと
子どもがなかなか眠れない状態にはどのようなものがあるのかというと、
- 子どもの特性による寝つきの悪さ
- 子どものストレスによる寝つきの悪さ
大きく分けてこの2つが挙げられます。
①子どもの特性による寝つきの悪さ
ADHDやASDといった発達障害の特性の中には、子どもの眠りを妨げるものもあります。
ADHDの子どもの場合、衝動性によって寝る時間になって急にやることを思い出してバタバタと動き出してなかなか寝れないという話をよく聞きます。
ASDの子どもの場合、こだわりによってなかなかゲームやYouTubeから離れられずなかなか眠れないこともあります。
またこうした特性による眠りにくさの他にも、発達障害の子どもは体内時計が普通の人よりもずれやすくなっています。
実際の時間と身体の時間がずれてしまうことによって、子どもからすると起きた時間が早朝や深夜のような感覚になってしまうこともあります。
そうしたことが絡み合って発達障害の子どもは睡眠の困難さを抱えていることが多くなるのかもしれません。

②子どものストレスによる寝つきの悪さ
これは、不登校の子どもによく見られるタイプの睡眠の課題です。
- 朝が来るのが嫌でなかなか眠れない
- 登校している同級生の声を聞くのが嫌で朝は起きたくない
- 嫌な出来事を思い出してなかなか眠れない
こんな思いから寝つきが悪くなってしまう子どもも少なくありません。
今までの相談の中でも不安を見ないようにするために、ゲームやネットなどに没頭して昼夜逆転してしまうパターンがこのタイプの子どもにはとても多かったです。

では、こうした睡眠の課題を抱えている子ども達にご家庭でできることはどのようなものがあるのでしょうか。
子どもの睡眠力を高めるためにできること3選
ここでお話ししていくのは子どもが自分で睡眠について考えて実行できるようなものになっています。
強制してもなかなか効果は得られないので、ぜひ子どもとも睡眠についてお話ししていただくのもいいと思います。
- 朝、起きたら太陽の光を浴びる
- 朝食を食べる
- 睡眠記録をつける
この3つは普段相談に来てくれた人にもよくお願いしています。
①太陽の光を浴びる
体内時計がズレてしまっている子どもにとっては、ズレをリセットするのに太陽の光がとても効果的です。
必ずしも朝一に起こしてしなければならないというわけではなく、子どもが起きたタイミングで太陽の光を浴びるだけでも体内時計のズレは直っていきます。
できれば外に出て15分程度太陽の光を浴びることが理想ですが、不登校の子どもの場合外に出ることに抵抗を感じることもあるので、その場合にはベランダから顔だけ出すといった形でもいいと思います。
子ども自身が無理なくできる範囲で、起きたタイミングに太陽の光を浴びることを定着させられると体内時計のズレも起きにくくなります。
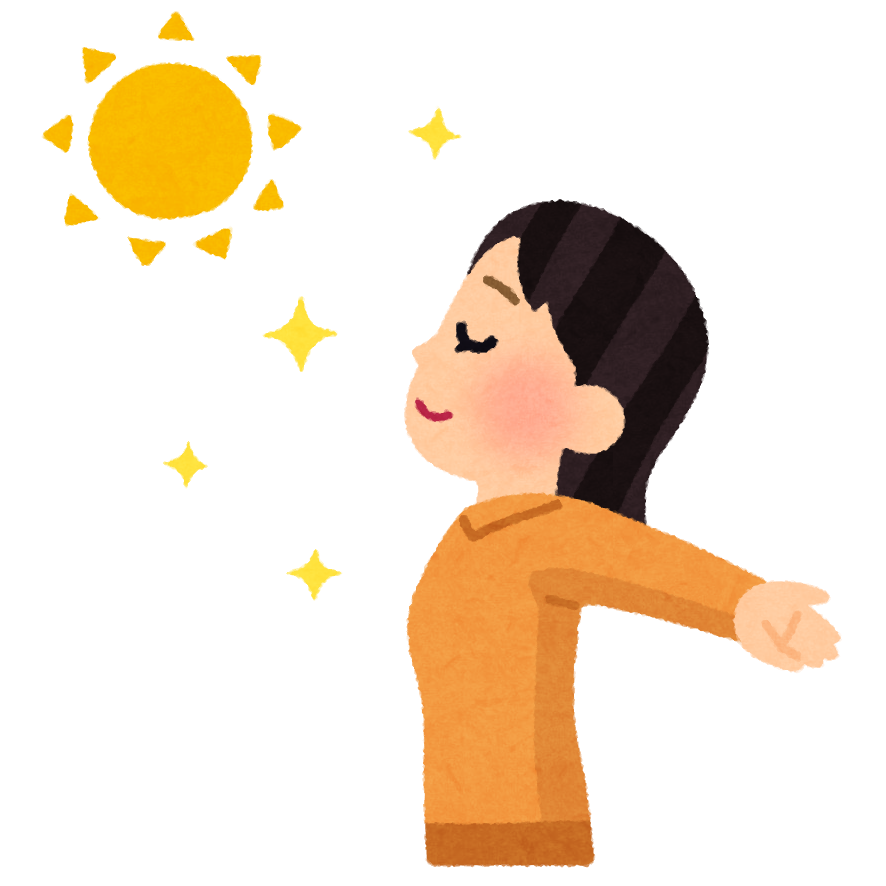
②朝食を食べる
体内時計をリセットするためには、太陽の光とプラスして朝食を食べるとより効果が高まります。
最近の子どもの中には朝食を食べずに学校に来ている子も多く、そうしたことの積み重ねが体内時計のズレにつながりやすいとも考えられます。
起きたばかりだと胃腸が働いていなくてなかなかご飯が食べられないこともあるかもしれません。
そうした時には無理をしなくていいのですが、できれば朝食を食べる習慣を身につけておくと体内時計のズレをリセットするのに役立ちます。
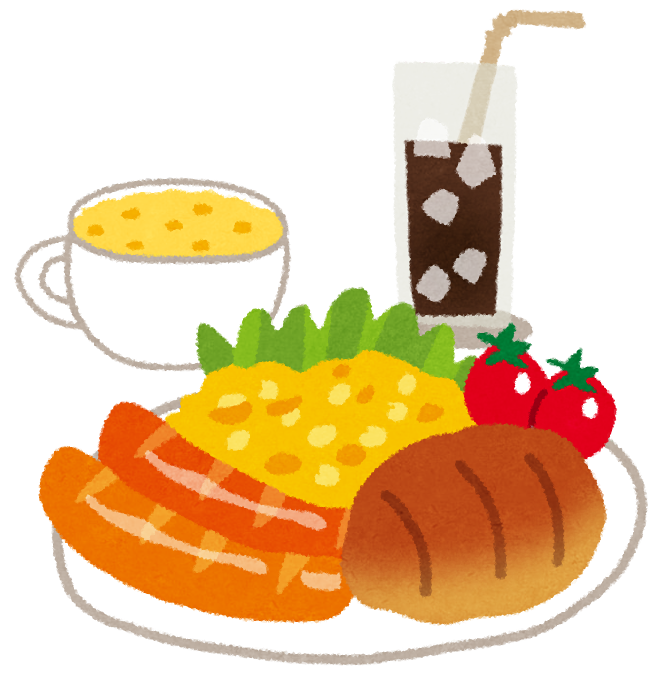
③睡眠記録をつける
睡眠の記録を付けることは、子どもの睡眠状況を知るためにもとても効果的な方法です。
もし、医療機関を受診しようと考えた時にも、睡眠記録があると診察もスムーズに行きやすいのでぜひご家庭でも取り組んでいただくといいと思います。
睡眠記録には、
- ベッドに入った時間
- 寝ていた時間
- その日の体調や出来事
といったものを記録しておくと、後で見返した時に参考になります。
睡眠記録を付けてみると、今までは漠然と眠れていないと感じていたものが、日によってばらつきがあることを発見して眠れない日の特徴が見えてきます。
最近では、スマートフォンのアプリでも記録できるものがあるので、子ども自身に記録してもらうのもいいかもしれません。
もし、一回一回記録するのが面倒くさいと感じるようでしたら、
こうしたグッズの力を借りるのもおすすめです。
夜更かしの原因にスマホが影響していることがとても多いです。子ども自身、スマホを手放したくても手放せない状況かもしれません。そんな時にできることについてまとめてみました。
朝起きられないから夜も眠れなくなっている、そんな子も中にはいるのではないでしょうか。もしかしたらその起きられない状態は起立性調節障害かもしれません。そんな起立性調節障害についてまとめてみました。
おわりに
今回は、子どもの睡眠力を高めるためにご家庭でできることについてお話ししていきました。
今回の内容を実践してもなかなか睡眠の状況が改善しない時には、一度病院の受診をしてみるのもおすすめです。
その際には、睡眠記録も併せて持って行っていただけるとより効果的です。
今回も読んでいただきありがとうございました。







