HSP(ひといちばい敏感な子)の特徴と日常生活でのサポート方法

スクールカウンセラーの相談の中で、
- 「子どもが小さいことを気にしすぎて困っている」
- 「ちょっとしたことで不安を感じやすい」
- 「友達関係で疲れやすい」
のような話を聞くことがあります。
そうした相談の時に、
「もしかして、こういった性格ってHSPですか?」
という質問をされることがここ数年で増えてきています。
そこで今回は、敏感で心が疲れやすいHSPについてお話ししていきます。
Contents
HSPってそもそも何?
HSPとは、Highly Sensitive Personの略称で「ひといちばい繊細な人」という意味で使われていて、心理学者のエレイン・アーロン博士が提唱した「人の気質」を表す名称です。
子どもに対しては、HSC:Highly Sensitive Childという言葉を使うこともあります。
研究では、人口の20%の人にHSP気質があると言われていて、こうした繊細さは「生きていくための戦略」として備わっているのではないかと考えられています。
社会で生きていくために些細な情報も見逃さずにキャッチできる、これだけならばとても素晴らしい気質だと思います。
しかし、現代社会ではこうした気質が職場や家庭など生活の中で気疲れしやすく、生きづらさにつながってしまうことがあるのです。

では、HSPには具体的にどのような特徴があるのでしょうか。
HSPの特徴ってどんなもの?
HSPの人は、さまざまなことに気づき悩んでしまうことがよくあります。
- 性格が内向的で、「内気」と言われることが多い
- 急な環境の変化に弱い
- 大きな音や強い光が苦手
- 些細なことでも、うじうじと悩んでしまう
- 忙しくなると、一人で部屋にこもりたくなる
- 他人の気分に振り回されやすく、対人関係に疲れがち
- 小さな音や匂いも気になる
- 人が怒られているのを見て、自分も怒られているように感じる
こうした悩みが、HSPの人から出てくることが多いです。
こうした悩みをアーロン博士は、DOESと呼ばれる4つの特性に分けました。
- D:深く処理する(Depth of processing)
- O:過剰に刺激を受けやすい(being easily Overstimulated)
- E:全体的に感情反応が強く、特に共感力が高い(being both Emotionally reactive generally and having high Empathy in particular)
- S:ささいな刺激を察知する(being aware of Subtle Stimuli)

では、これら4つの特性は具体的にどのようなものなのでしょうか。
D:深く処理する
HSPの人は、行動を起こすことに対して慎重で石橋を叩いて渡る、という人が多いです。
むしろ、石橋を叩いた結果渡らない、となるぐらい慎重派なのもHSPの特徴かもしれません。
- 物事を深く考えたり、深く読み取ったりする
- 慎重に考えてから行動するので、行動するのに時間がかかる
- あらゆる可能性を考えてなかなか決断できない
- 広く浅くの人間関係よりも、特定の人と深くつながる方が好き
こうした特徴が深く処理するHSPの性質にかかわってきます。

O:過剰に刺激を受けやすい
HSPは、刺激を受けやすく、疲れやすい性質があり、刺激が多すぎると普段の力を発揮できなくなることがあります。
例えば、家族や友達とテーマパークで楽しい時間を過ごしているはずなのに、ぐったりして元気がなくなってしまったり、帰りたくなってしまったりすることもあります。
これは楽しんでいないというわけではなく、刺激を受けすぎて疲れてしまったためにこうした反応が出てきてしまっているのです。
- 人の視線や反応が気になる
- 友達と楽しく過ごしていても気疲れしやすく、帰宅するとぐったりしてしまう
- 人の些細な言葉に傷つき、いつまでも忘れられない
- 人混みや大きな音が苦手
こうした特徴が刺激を受けやすいHSPの性質にかかわってきます。

E:感情反応が強く、共感力が高い
HSPの人は、とても感受性が豊かで共感力も高いため、他の人が何かをしているのを見ると、あたかも自分が同じことをしているかのように感じたり、相手の気持ちを自分の気持ちのように感じたりすることがあります。
- 映画や本などの登場人物に感情移入しすぎる
- 人の仕草や目線、声音などに敏感で、機嫌や思っていることがわかる
- 人が怒られていると自分のことのように感じてしまう
- ささいなミスでもとても気になってしまう
- 不公平なことや残酷なことに気づきやすい
こうした特徴が感情反応が強く、共感力が高いHSPの性質にかかわってきます。

S:ささいな刺激を察知する
過剰に刺激を受けやすいという点につながる部分でもありますが、HSPの人はほかの人なら気にならないような日常的な音や匂い、変化にすぐに気づけます。
- 強い光や日光のまぶしさなどが苦手
- 匂いに敏感で、近くの人の体臭や柔軟剤の匂いなどで気分が悪くなる
- 服の素材でチクチクするものは着られない
- 小さな音やかすかな匂いなど細かいことに気づく
- 人の髪型や服装の変化に気づく
- 家具の配置替えや置いてあったものがなくなるなどの変化がわかる
こうした特徴がささいな刺激を察知するHSPの性質にかかわってきます。

これら4つの特性を併せ持つ人が、HSPと言われている!
では、HSPの人はどのようにこうした気質と付き合っていけばいいのでしょうか。
上手なHSP気質との付き合い方
HSPは生まれ持った気質なので、「治療する」ことはできません。
しかし、敏感に察知した後の自分の行動や環境を変えることで対処できます。
例えば、共感力が高く、相手がしてほしいことを先回りして解消することに疲れてしまいがちなら、周りと少し距離をとるのも効果的です。
自分が聞きたくない話を聞くことも、苦手だと感じる人と仲良くすることも必要もありません。
自分が一緒にいて居心地がいいなと思える相手とだけ付き合うようにするだけで、人間関係で疲れてしまうことが格段に減ってきます。
それ以外にも、刺激を和らげるためにアイテムを使うのも効果的です。
| 視覚 |
|
|---|---|
| 嗅覚 |
|
| 聴覚 |
|
| 触覚 |
|
また、HSPに関する本や記事を読むことによって、心が楽になることもあかもしれません。
HSP=繊細さんと名付けてHSP気質のことをわかりやすく紹介してくれる1冊です。
自分と似ている人のことを知りたい、と思った思春期の子どもでも読みやすい本だと思います。
まずは、こうした本を読んでHSPの理解を深めるのもいいのでしょうか。
先ほどの本から発展して、HSPの人が毎日を元気に過ごすためにできることのメソッドが紹介されています。
さまざまな方法が紹介されているので、自分に合ったやり方を見つけられるかもしれません。
これは、当事者というよりもHSCの子どもを育てているママ向けの本です。
HSCの子どもに対しての接し方や工夫の仕方について紹介されているので、もしも自分の子どもがHSCかもしれないと悩んだ時に読んでいただくといいかもしれません。
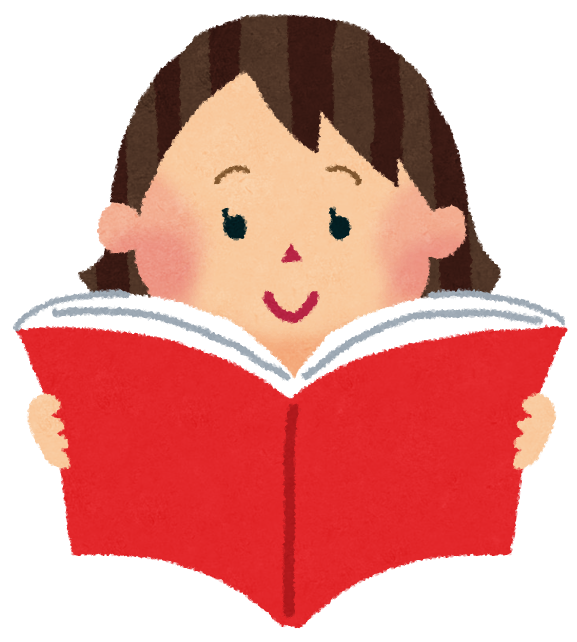
おわりに
今回はHSPについてお話ししていきました。
HSPは比較的新しい定義なので、まだまだ認知度が低く誤解されやすい面も多くあります。
この記事を読んでいただいて、少しでもHSPについての理解が深まってくれれば嬉しいです。
今回も読んでいただきありがとうございました。







