普段の相談の中で、
- 「子どもが話す時に言葉をつまらせることがよくある」
- 「どもることが多くて、話すのを嫌がるようになってきた」
のような話題が出ることが時折あります。
子どもの吃音に対してどのように対応したらいいのか、悩まれているママも少なくありません。
そこで、今回は子どもの吃音についてお話ししていきます。
そもそも吃音って何?
吃音とは、話し言葉が滑らかに出ない状態を指します。
具体的には、
- 音の繰り返し:例「あ、あ、あ、あのね」
- 引き伸ばし:例「あーーのね」
- 言葉を出すのに間があいてしまう:例「・・・・あのね」
のような3つの特徴が見られることが一般的です。
- こうした症状の他にも、話す前に顔をしかめたり舌を動かしたりなどのように体の一部に力が入り過ぎてしまうこともあります。

では、どうして吃音が出てきてしまうのでしょうか。
吃音の原因って何?
吃音の原因は、
- 小児期に他の原因となる疾患がない状態で起きる発達性吃音
- 疾患や心的ストレスなどの原因で起こる獲得性吃音
の2つがあります。
①発達性吃音
小児期や成人期にみられる吃音のほとんどは発達性吃音です。
2歳から5歳の幼児期に発症することが多く、成長するにつれて吃音が解消する人も多いと言われています。
遺伝や環境、発達などさまざまな要因が影響して吃音が発症すると考えられます。

②獲得性吃音
獲得性吃音は、
- 神経学的疾患や脳損傷などにより発症する、獲得性神経原性吃音
- 心的なストレスや外傷体験に続いて発症する、獲得性心因性吃音
の2つの原因があります。
2つとも発症時期は青年期(10代後半~)以降とされています。

今回は、上記の2つの中の発達性吃音をメインにお話ししていきます。
どんな時に吃音は出やすいの?
吃音には波があり、吃音が出やすい場面というものがあります。
具体的には、
- 授業中などの発表のような、周囲の目が気になる時
- どもらないようにしようなど、吃音を意識しすぎている時
- 自分にとって発音しにくい言葉を話す時
のような場面が考えられます。
吃音は子ども自身だけでなく、周囲からも気づかれやすいため、からかわれたり注意されたりすることが少なくありません。
そうした場面が多くなると、話すことに自信をなくしたり、吃音が悪化したりと子どもにとっても悪い影響を与えかねません。

では、吃音にはどのように対応したらいいのでしょうか。
吃音の対処法ってどんなもの?
吃音への対処の仕方は、
- 環境調整
- 子どもの自信につながるようなコミュニケーションのトレーニング
のようなものが考えられます。
環境調整
子ども自身が話すことへの不安が少なくなるように、学校などの環境を整えていくことが吃音にはとても大切です。
吃音について周囲に理解してもらったり、子どもが焦らずに話せるよう配慮してもらったりとさまざまな手立てを取ることによって、話すことが楽しくなってくると思います。
子どもにとってどのような支援があるとコミュニケーションが取りやすくなるのか、どういう場面だと気持ちが楽になるのかなどを子どもに確認しながら進められるといいのではないでしょうか。

コミュニケーションのトレーニング
環境調整だけでなく、子どもにとってやりやすいコミュニケーションの方法が身に付けられるように支援ができると、子どもの自信にもつながりやすいです。
具体的には、言語聴覚士などの言葉の専門家がいる療育センターなどの機関に相談に行ったり、ことばの通級指導教室の利用をしたりなどのような方法が考えられます。
どのような支援がお住まいの自治体でできるか知りたい場合には、
- 地域の子育て相談窓口
- 地域の教育相談センター
- スクールカウンセラー
- かかりつけの小児科
などに相談していただくといいと思います。
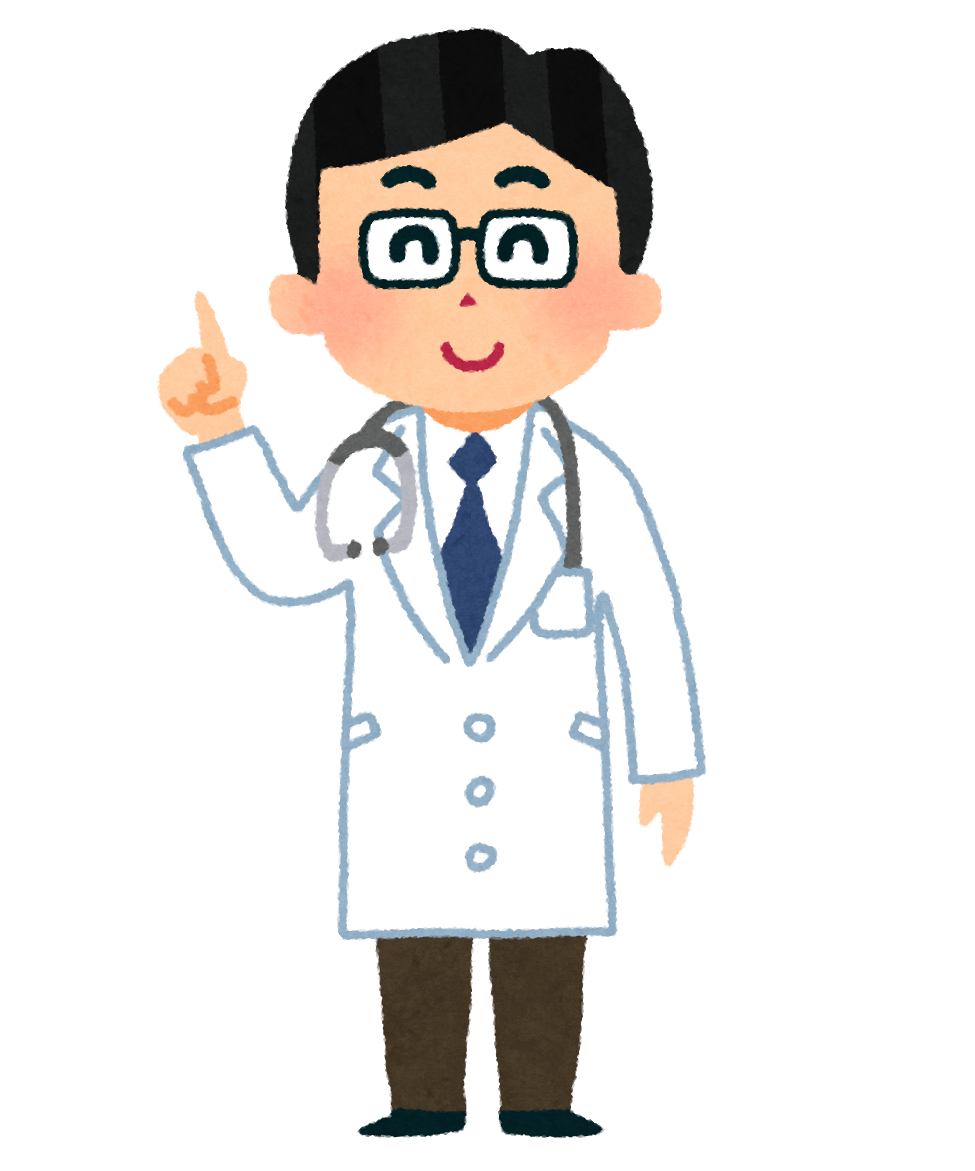
おわりに
今回は、吃音についてお話ししていきました。
これまで、スクールカウンセラーとして吃音の相談も何度か受けてきました。
通級の利用によってコミュニケーションに自信を持てるようになったり、周囲の理解を得て自分のペースで話せるようになったりと、子どもによって経過はさまざまでした。
吃音が完全になくなることもあれば、少なからず吃音の状態がありながらも子ども自身が上手に付き合えるようになることもありました。
どのような状態であれ、子どもが自分なりの対処の仕方を身に付けられれば、それだけで子どもにとっての自信につながるはずです。
どのような支援の仕方がいいのか悩んだ時には、ぜひ一緒に対処の仕方を考えるお手伝いをさせていただければ嬉しいです。
今回も読んでいただきありがとうございました。








