夏休み明けに不登校が増える理由と家庭でできる予防・対応策

お盆の時期も過ぎ、もうそろそろ夏休みの終わりが見えてきました。
この時期の子ども達の中には、
- 学校のことを考えて憂鬱な気持ちになっている
- ボーっとする時間が増えた
- 外出を嫌がるようになった
- 溜息をつくなど、気持ちがふさいでいる
のような姿が見られることもあるかもしれません。
ニュースでも、夏休みなどの長期休暇明けに不登校が増えると言われているので、心配になるママも多いのではないでしょうか。
そこで、今回は夏休み明けに不登校が増える原因とその解決法についてお話ししていきます。
Contents
そもそも何で夏休み明けに不登校が増えるの?
子ども達それぞれに不登校になった理由があります。
そこで、私が今までに受けた相談の中で特に多かったものを挙げると
- 夏休み中に生活習慣の乱れてしまった
- 夏休みの宿題が終わっていなかった
- 学校に行っていた感覚が薄くなり、登校の負担が大きく感じてしまった
- 友人関係の不安
の4つが主に話題として出てきました。

①夏休み中の生活習慣の乱れ
これはなんとなくイメージできるママも多いのではないでしょうか。
夏休み中の子ども達は、学校のない解放感から生活習慣が乱れることがよくあります。
部活などがないと、朝に起きなければならない理由もないので、何時に起きて何時に寝ようと子ども自身が困ることはさほどありません。
そうした生活を1週間、2週間と続けていると、いざ学校が始まるとなってもなかなか以前のような朝型の生活に戻ることが難しくなってしまいます。
朝起きられなくて体がダルいから学校に行けない…、そんな日が夏休み明けから1日、2日と増えていった不登校になってしまった、というパターンも少なくありませんでした。

②夏休みの宿題が終わらない
この理由も話を聞く中では多かったです。
夏休み中は、小学生も中学生も各教科からさまざまな宿題が出されます。
普段であれば「次の日に提出だから」と、済ませてしまう宿題も、提出が1か月後となるとなかなか計画を立てて宿題をするのが、子どもにとっては難しい作業になります。
焦って夏休みが終わる直前に宿題に取り組む場合はまだいいのですが、中には
「もうこんな量の宿題終わるわけないから、学校に行きたくないな」
という気持ちになってしまう子どもも少なからずいます。
特に、学年が上がって保護者の手が離れてくると、そうした気持ちになってしまう子どもが多いように感じます。
また、私立などで夏休み明けにテストを予定しているところなどでは、テスト勉強をしていないことも不登校へのきっかけとなりやすいです。
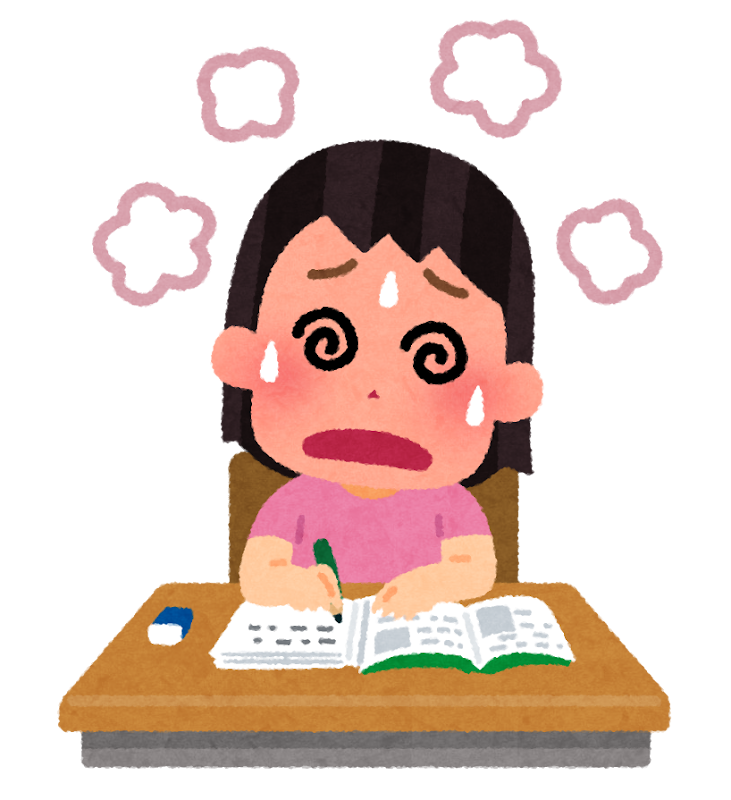
③学校に行っていた時の感覚がなくなる
普段だったら学校に行くことが、日常の習慣として当たり前になっている子どもも少なくありません。
しかし、そんな習慣も1か月以上やらなかったら感覚が鈍ってしまうのは、大人でもイメージができるのではないでしょうか。
夏休み前までだったら、前の日に学校に行く準備をして、学校では授業を受けて友達と過ごすことに対してそこまで負担には感じていなかった。
そんな子どもも、何だか夏休みの間に自分がどんな風に学校で過ごしていたのかわからなくなってしまい、学校に行くことがものすごく負担に感じてしまうというということもあります。

④友人関係の不安
学校がある日は当たり前に顔を合わせていた友達とも、夏休みの間はそれほど会う機会は多くありません。
最近では、SNSなどでこまめにつながれるのでそれほど不便には感じないかもしれません。
しかし、1学期の間にそこまでの関係を作れていなかった子どもからすると、夏休み明けはまた0から友達作りをするような気持ちになりやすいです。
それ以外にも、他のグループの子ども達の関係が変わっているかもしれない、という不安が生じやすいのも夏休み明けです。
こうした不安は実際にクラスの子に会ってみないと解消しない問題でもありますが、不安に立ち向かうエネルギーがないと難しい問題でもあります。

では、こうした原因に対してどのように対処していけばいいのでしょうか。
夏休み明けの対応はどうすればいいの?
上記でさまざまな不登校の原因をお話ししていきました。
こうした原因に対して、どうやって対応すればいいのかと頭を悩ませているママも少なくないのではないでしょうか。
ここでは、
- 子どものエネルギーを貯める活動
- 無理のない範囲からさまざまなチャレンジ
- 子ども自身の気持ちを整理する場を整える
の3つのポイントに沿った対応についてお話ししていきます。
①子どものエネルギーを貯める活動
不登校になってしまう子どもは、ほとんどの場合エネルギーが低下していることが多いです。
エネルギーが低下しているため、「何かをしよう」という気力もわかず日々悶々と過ごしている、という状態になっています。
こうした状態の時に、「学校に行ってほしい」と話をしても、そのためのエネルギーがない状態なので、何とか頑張って行っても続かないことがほとんどです。
なので、こうした状態の時にはできる限り負荷の少ない環境を整えてあげて、子どもが安心して休めるようにしていただくのがいいと思います。
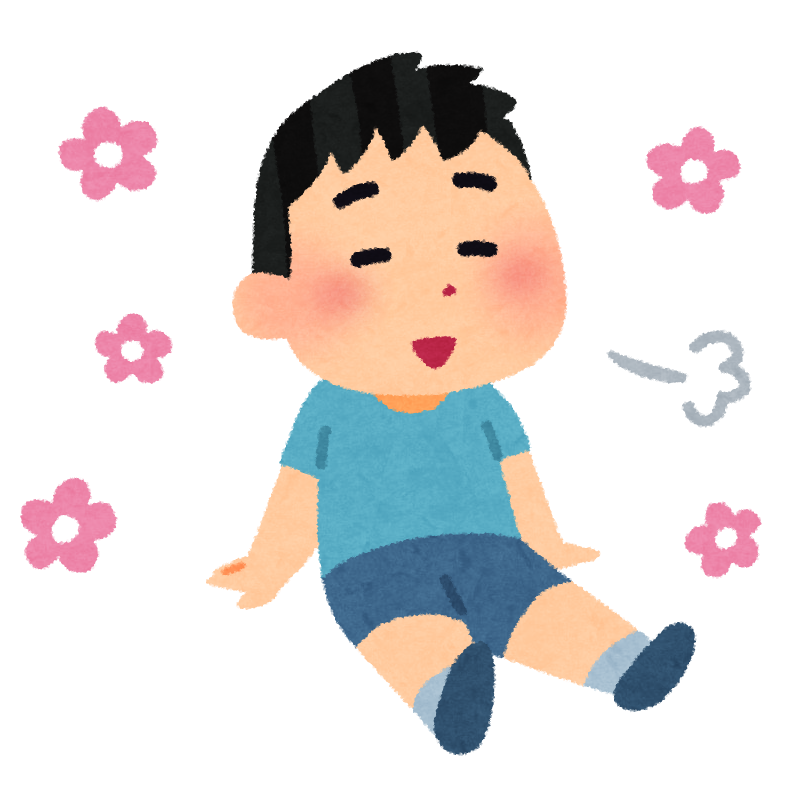
②無理のないチャレンジ
ただ休ませるだけだと何もしなくなるのではないかと不安、そんなママもいると思います。
実際には、子どもが安心して休める環境を整えて日々を過ごしていくうちに、子ども自身から何かしたいという欲求を話すことが今までの経験上とても多かったです。
しかし、そこでいきなり負荷の高い活動をしてしまうと、またエネルギーが低下してしまう危険性もあります。
なので、子ども自身の気持ちと体力と照らし合わせながらできる活動かどうか、ということをご家庭では一緒に考えてほしいです。
今までの活動で多かったのは、
- お菓子作り
- 写真撮影
- カードゲーム大会に参加
- 趣味の買い物のために遠出
のようなものでした。
子どもの興味・関心のあるところから、少しずつ活動の範囲を広げていくうちに学校や勉強に対して前向きになったパターンが結構ありました。

③子ども自身の気持ちを整理する場の設定
不登校になった子ども達は、とても多くのことを心の中で考えています。
しかし、それらの考えはなかなか表面には出てこず、周囲の人からすると何も考えていないように誤解されてしまいことがとても多いです。
子ども自身も言葉に表現できないさまざまな思いがあるので、なかなか話す気持ちになれないこともあります。
また、そうした子ども達の話を聞く中でよく出てくる言葉は、
- 「親には心配かけたくないから話せない」
- 「どうせわかってもらえないからはなしたくない」
- 「自分でもどう話したらいいのかわからなかった」
といったものでした。
大人でも言葉で言い表せない気持ちを抱える時があると思います。
そんな時に、いくら「話してくれたらいいのに」と言われても、話す気分にはならないのではないでしょうか。
不登校の子ども達も、そのような心境であると受け止めていただけると、少しだけ対応の仕方も変わってきます。
なので、「あなたのタイミングでいいから、いつでも話を聞くからね」というスタンスでいていただけると、子ども達にとっても安心感につながります。
中には、「親には話せない」と考える子どももいるので、そうした場合には子どもが話せそうな人に協力してもらうのもいいと思います。

おわりに
今回は、夏休み明けの不登校の原因と解決法についておはなししていきました。
さまざまなパターンを挙げましたが、不登校の理由は千差万別です。
なので、原因探しにこだわりすぎないようにすることも、子どもとママにとってもストレスが少なくていいと思います。
また、どうしても子どもが不登校だとさまざまなかかわりが制限されたような気持ちになりやすいです。
そんな孤立感を抱えた状態で日々を過ごすのはとても苦しいことだと思います。
そんな時には、お近くのスクールカウンセラーや信頼できる人に相談していただくのもおすすめです。
今回も読んでいただきありがとうございました。







