適応障害とは?不登校の背景にあるかもしれない心の変化と対応のヒント

学校の休みが増えてきた子どもの中には、
- 頭痛や腹痛などの身体症状を訴える
- 学校に行ったものの早退してしまう
- 苛立ったり落ち込んだりといつもと様子が違う
- 食欲がなくなり、夜も眠れなくなる
このような状態になる子がいます。
そうした子どもの姿に違和感を覚えて病院を受診したところ、
そこで今回は、
適応障害ってどんなもの?
適応障害と聞くと、適応障害と聞くと、
実際には、
適応障害は
- ストレスのある環境や状況に置かれていること
- そのストレスにより、生活に支障が出ていること
この2つの条件に当てはまった時に診断がつきます。
ストレス状態への抵抗力が下がることによって、
今までだと「甘えている」と捉えられていた状態に、

では、
適応障害ではどんな治療をするの?
適応障害では、
- 薬物療法
- 環境調整
- 心理療法
こうした治療を行なっていきます。
薬物療法
適応障害では、それぞれの症状に合わせたお薬が処方されます。
必ずしも精神に作用する薬が処方されるというわけではなく、頭痛がしんどいなら頭痛薬、夜なかなか寝付けないなら睡眠導入剤といった形で、今辛いと感じている症状を和らげるお薬が処方されます。
辛い症状を和らげて、今の自分の状況を整理する気持ちの余裕を作っていくことが薬物療法のメリットでもあります。

環境調整
適応障害は、ストレスが原因となって発症します。
お薬などで辛い症状を和らげることはできますが、根本的な解決とは言えません。
なので、ストレスの状況を整理してストレスを減らせるように環境調整をすることが適応障害の治療では求められます。
学校の中では、
- 部活動の負担が大きい場合には、どのぐらいの参加量が適切かを考える
- 授業中の発表への負担が大きい場合には、発表に頼らない表現方法がないかを考える
といったことができるかもしれません。
子ども達それぞれがストレスだと感じる要因は違うので、どんなことを辛いと感じているかを整理することが環境調整の第一歩です。
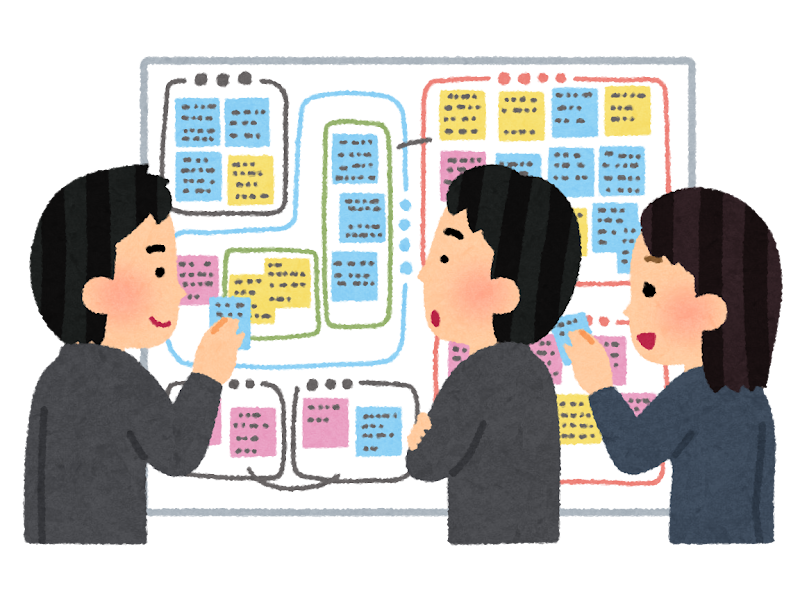
心理療法
適応障害と診断された子は、ストレスとの付き合い方があまり上手でない子が多いです。
ストレスを感じた時にどうやって気持ちを整えるか聞いてみても、
- 「我慢する」
- 「音楽を聞いてひたすら寝る」
- 「ずっとゲームや動画で過ごす」
といった回答をする子をよく見ました。
また、自分にとって嫌な出来事が起きた時に、ネガティブな捉え方しかできずに自分の首を絞めてしまうような状態に陥ってしまう子も中にはいました。
そこで心理療法によって、ストレスとの上手な付き合い方やネガティブな捉え方を変える方法を一緒にやっていくことによって子ども達自身のストレスへの対処力を高めていきます。

ストレスとの上手な付き合い方としてストレスコーピングという手法があります。
家族で一緒に考えてみると、自分一人では見つけられなかったストレスとの付き合い方が見つかるかもしれません。
物事をネガティブに捉えてしまうことは大人でもあると思います。
そんな時にご家庭で子どもと一緒にできるポジティブな捉え方の練習法についてまとめてみました。
では、こうした治療法以外に家庭でできる対処の仕方には何があるのでしょうか。
ご家庭でできる適応障害への対処の仕方
適応障害は、病院を受診しての治療も大事ですが、それ以外にもご家庭でのサポートがとても重要な役割を担っています。
ここでは、NGな対処の仕方とOKな対処の仕方をお話ししていくので、実際の場面に役立ててみてください。
- 心配しすぎ
子どもが普段と違った様子でいると心配になっていろいろとやってあげたくなる気持ちは、とても自然なことでそれ自体がわるいことではありません。
しかし、適応障害の場合は過剰に心配しすぎると心配をかけないようにと余計に疲れてしまう危険性が高まります。
- 症状を軽く考えすぎ
適応障害の子どもが抱えているストレスが、ママ達の目からみると「それぐらいでこんなに悩むの?」というものも少なくありません。
しかし、そんなことでと思われることも耐えられないくらい限界の状態であることをわかってもらいたいです。
それだけでなく、本人の思いを無視して休むように促すことも、子どもにとってのわかってもらえないという気持ちにつながりやすいので要注意です。
- 早く解決しようとしすぎ
大人になると問題がわかっていると、ついすぐにでも解決できる手立てを取ろうとしてしまいます。
あれこれとアドバイスをしたい気持ちになるのはわかりますが、適応障害の子どもは正論を受け止める心の準備ができていない時にアドバイスされるのを嫌います。
子どものペースに合わせて気持ちをまずは受け止めることを意識することが大切です。
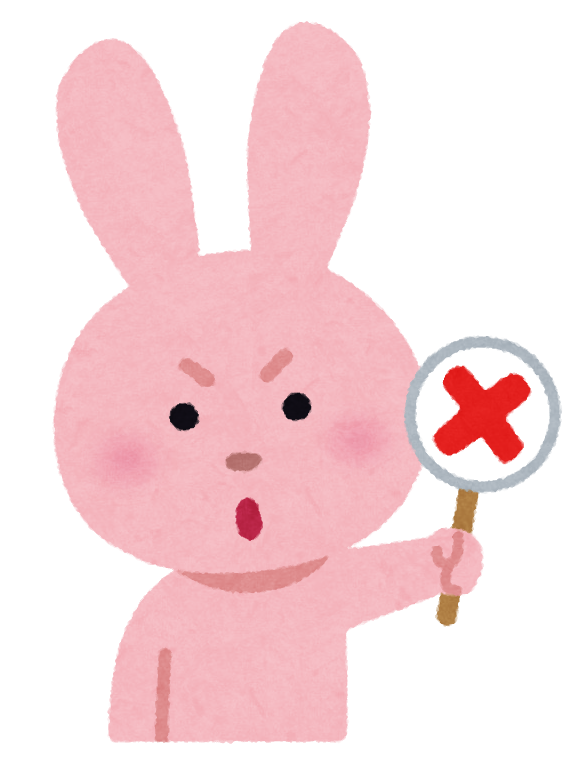
- 家庭でゆっくり休める環境を整える
適応障害は、ストレスによって体と心の疲れが極限まで高まっている状態です。
なので、ご家庭では本人がゆっくりと休める環境を整えることが大切です。
何もしないのは本人の精神的にあまりよくない、という場合には負荷の少ない作業をお願いしてみるのもいいかもしれません。
それも本人が無理なくできるもの、と限定されるので心配なら主治医とも相談して考えるのもおすすめです。
- 心配しすぎにならない程よい距離感を保つ
ゆっくりと休ませようと意識しすぎるあまり、そっと見守ってあまり声をかけないでいるご家庭も少なくないです。
しかし、見守っていることに子ども自身が気づかないのでは意味がありません。
普段通りの中にさりげない気遣いを見せるだけで、子どもの安心感につながります。
- 主治医としっかり治療計画について話をする
病院を受診した際に、診察は親子一緒か別々かは病院によっても異なります。
必ず一緒でも別々でもどちらでもいいので主治医としっかりお話しする時間を作っていただくことをおすすめします。
薬物療法や環境調整を行っていくと、2~3か月ほどで症状が落ち着くことが多いので、そうした時期も踏まえて今後の方針等をしっかりと確認しておくとご家庭でのサポートにも余裕が生まれると思います。
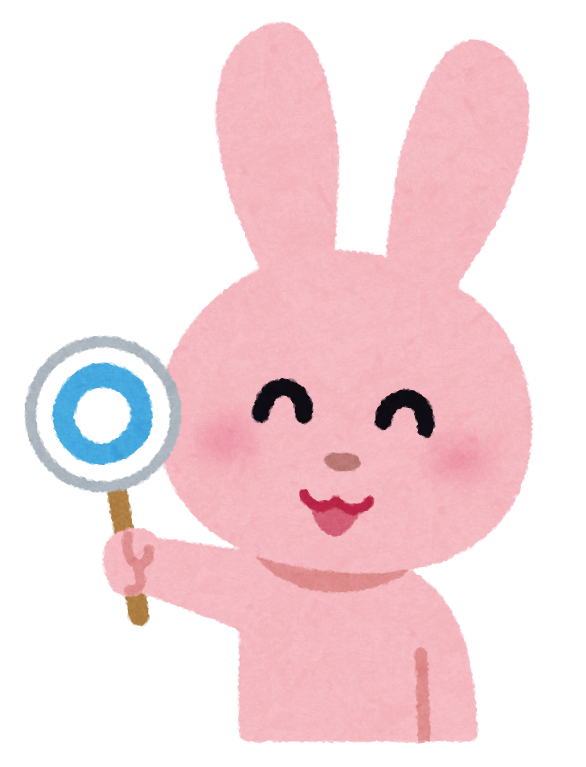
おわりに
今回は、不登校の要因にもつながる適応障害についてお話ししていきました。
適応障害は、症状の個人差が大きいので治療の経過も人それぞれです。
治療が長期に渡ることもあるので、家族全員が疲弊してしまわないように外部のサポートをお願いすることも大切です。
そんな時には、ぜひスクールカウンセラーに相談してみてください。
今回も読んでいただきありがとうございました。







